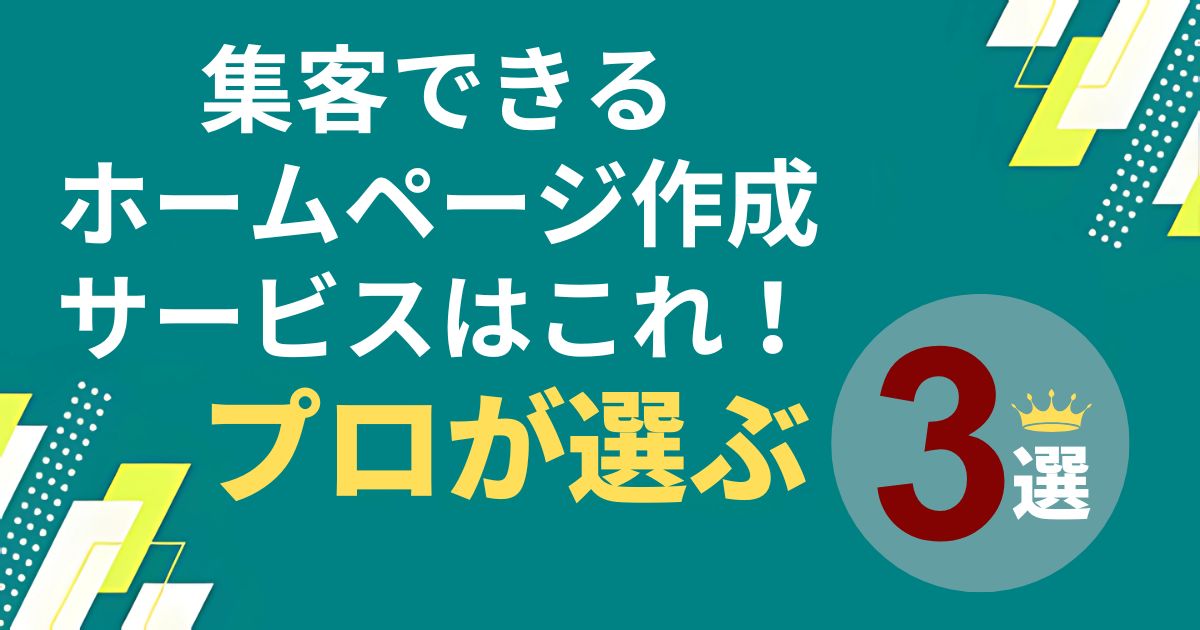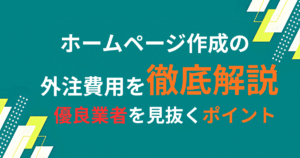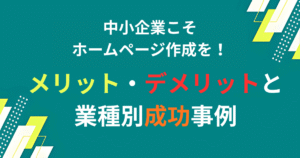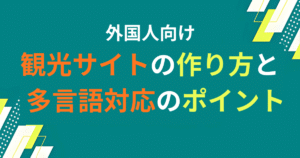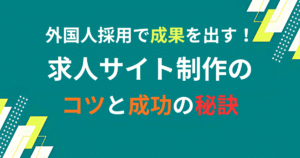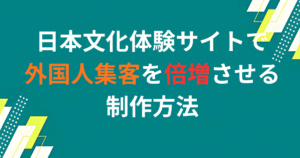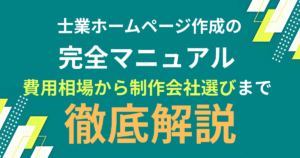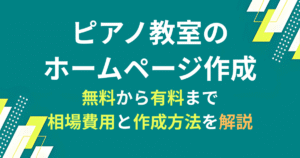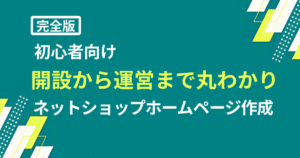「無料のホームページ作成サービスを使いたいけど、種類が多すぎて比較できない…」
そんなお悩みはありませんか?



この記事を読めば、各サービスで無料でできる範囲と、有料プランの費用対効果が明確になり、あなたの目的に合ったツールが必ず見つかります。
人気の無料サービスから、店舗に強い「グーペ」、デイサービス向けまで、おすすめのホームページ作成サービスを網羅的に解説。
もう迷わず、あなたのビジネスを加速させる最高のホームページ作成を、自信を持って始められるはずです。
初心者でも使いやすいホームページ作成サービスとは?


この章では、数多く存在するホームページ作成サービスの中から、特にWebの専門知識がない初心者や個人事業主の方でも、安心して直感的に利用できるサービスを厳選して紹介します。
「たくさんありすぎて、どれが自分に合っているのか分からない」という悩みを解消し、あなたの目的に最適な選択肢を見つける手助けをします。
この章には主に以下の内容があります。
- 無料で始められる初心者向けサービス
- 人気の定番サービス「グーペ(Goope)」の特徴
- 事業者におすすめのクラウド型ホームページ作成サービス
- 福祉・介護事業者向けの特化型サービス
- デザイン重視の「Wix」や「STUDIO」の活用法
- 旧NTTグループの安心感あるサービス
- MIRYOKU(ミリョク)が提供する独自の強み
無料で始められる初心者向けサービス
まずは費用をかけずにホームページ作成を試したい初心者の方には、「Wix」や「Jimdo」といった無料プランを持つサービスが最適です。
これらのサービスは、プログラミングなどの専門知識がなくても、マウスのドラッグ&ドロップといった直感的な操作でサイトを構築できるため、ホームページ作成の全体像や操作感を掴むのに適しています。
ただし、ビジネスで本格的に利用する際に重要となる独自ドメインの利用や、サイトに表示される広告の非表示には、有料プランへの移行が必要になる点は理解しておくべきです。



まずは無料プランで実際に触ってみて、操作感を確かめるのが失敗しないための第一歩と言えるでしょう。
その上で、本格的な運用を考えるなら、月額千円前後からの有料プランを検討するのが現実的です。
人気の定番サービス「グーペ(Goope)」の特徴
「グーペ(Goope)」は、飲食店や美容サロン、整体院といった店舗型のビジネスを運営する個人事業主や小規模事業者に特化した、ホームページ作成サービスです。
このサービスの最大の特徴は、予約機能、メニュー表、フォトアルバム、クーポン発行、お知らせ更新など、店舗運営に不可欠な機能があらかじめパッケージ化されており、専門知識がなくても簡単に設定できる点にあります。
デザインの自由度はWixなどと比較すると限定的ですが、その分、迷わず操作できる分かりやすさがあります。
月額1,100円からの有料プランが基本となりますが、無料お試し期間も用意されています。
専門知識はないけれど、予約受付や情報発信など、店舗集客に必要な機能をしっかりと使いたいオーナーにとって、非常にコストパフォーマンスの高い選択肢となります。
事業者におすすめのクラウド型ホームページ作成サービス
事業者がビジネス目的で本格的にホームページを運用する場合、サーバー管理が不要で、セキュリティ対策やシステムのアップデートもサービス提供側が行ってくれる、クラウド型のホームページ作成サービスが主流であり、最もおすすめです。
サーバーの契約や保守、ソフトウェアの専門的な作業を全てサービス提供側に任せられるため、IT担当者がいない個人事業主や中小企業でも、本来のビジネス活動に集中できるという大きなメリットがあります。
代表的なサービスには、手軽さと機能のバランスが良い「Wix」や「Jimdo」、ブログ機能が強力な「WordPress.com」などがあります。



専門的な手間をかけずに、安定したサイトを安心して運用したいと考える全ての事業者にとって、クラウド型サービスは最も現実的で合理的な選択肢と言えるでしょう。
福祉・介護事業者向けの特化型サービス
デイサービスや放課後等デイサービスといった福祉・介護事業者は、汎用的なサービスよりも、業界特有の情報公開の要件や、利用者・その家族が求める情報発信に特化したホームページ作成サービスを選ぶのが最も効果的です。
なぜなら、福祉・介護業界のサイトには、事業所の理念やサービス内容といった基本情報に加え、施設の温かい雰囲気を伝える写真や、日々の活動報告など、利用者と家族に安心感を与えるためのコンテンツが不可欠だからです。



業界特化型サービスは、これらの要素を満たすテンプレートや機能を標準で備えている場合が多く、例えば、お知らせ更新機能、施設内の写真ギャラリー、見学・相談フォーム、スタッフ紹介ページなどを迷わず簡単に作成できます。
汎用的なサービスでゼロから構成を考えるよりも、業界に特化したサービスや、福祉・介護施設の制作実績が豊富な業者を選ぶことで、信頼感を与えるホームページを効率的に作成できます。
デザイン重視の「Wix」や「STUDIO」の活用法
クリエイター、デザイナー、美容サロン、フォトグラファーなど、洗練されたビジュアルがビジネスの魅力を直接伝える業種には、デザインの自由度が非常に高い「Wix」や「STUDIO」といったホームページ作成サービスが最適です。



これらのサービスは、一般的なテンプレートの制約を超えて、自由なレイアウトや、動きのあるアニメーションといった表現を、プログラミング知識なしで実現できるからです。
競合他社との明確な差別化を図り、独自のブランドイメージをWeb上で強く打ち出すことが可能になります。
特に「Wix」はドラッグ&ドロップで直感的にパーツを配置でき、初心者でも比較的扱いやすいのが特徴です。
一方、「STUDIO」はよりプロ向けのUIで、細部までこだわり抜いた完全オリジナルのデザインを構築できます。
画一的なテンプレート感を脱し、自社のクリエイティビティやブランド力を視覚的にアピールしたいなら、これらのデザイン特化型サービスを活用する価値は非常に大きいでしょう。
旧NTTグループの安心感あるサービス
NTTグループが提供するホームページ作成サービスは、手厚い電話サポートとナショナルブランドとしての絶大な信頼感が最大の特徴です。
Webの知識が全くなく、パソコン操作にも強い不安を抱える事業者にとって、「何かあった時に電話ですぐに聞ける」「大手だから任せて安心」という点は、機能の豊富さや価格以上に重要な選択基準となります。
これらのサービスは、専門スタッフによるヒアリングや制作の代行、公開後の運用サポート(更新作業の代行など)がサービスに組み込まれていることが多く、自分で作るというよりは「プロに丸投げしたい」というニーズに強く応えます。



その分、デザインの自由度や機能のカスタマイズ性は限定的で、費用はWixなどのセルフサービス型と比較すると高額になる傾向があります。
多少費用がかかっても、制作から運用まで全面的にプロに任せ、ITに関する手間を一切かけずにホームページを持ちたいと考える事業者にとって、有力な選択肢となります。
MIRYOKU(ミリョク)が提供する独自の強み
MIRYOKU(ミリョク)のようなホームページ作成サービスは、士業やコンサルタント、各種教室運営といった特定の業種にターゲットを絞り、サイト制作だけでなく、その業界で成果を出すための集客ノウハウや専門的なコンテンツ提供までを含めた、オールインワンのソリューションを提供している点が独自の強みです。
単にサイトを作る「箱」を提供するだけでなく、その業界で成功するために必要なマーケティング戦略やコンテンツのひな形がサービスに組み込まれているため、利用者は自身の専門分野のビジネスに集中しながら、効果的なWebサイトを運用できます。
例えば、業界に特化したSEO対策済みテンプレートや、顧客管理システム(CRM)との連携機能などが考えられます。
もしご自身の業界に特化したサービスが存在する場合、汎用的なツールを自分でカスタマイズするよりも、業界知識と集客ノウハウが詰まった特化型サービスを利用する方が、成果への確実な近道となる可能性があります。
ホームページ作成サービスのメリット


この章では、ホームページを専門業者に依頼したり、ゼロから自作したりする場合と比較して、WixやJimdoのような「ホームページ作成サービス」を利用することの具体的なメリットを、初心者の視点から分かりやすく解説します。
ITに不慣れな方や、時間・予算が限られているビジネスオーナーにとって、なぜこの選択が合理的であるかを明らかにします。
この章には主に以下の内容があります。
- 専門知識がなくても簡単に作れる
- デザインテンプレートで美しいサイトが作れる
- 短期間でサイト公開まで完了できる
- スマホからの更新も手軽に可能
メリット(1)専門知識がなくても簡単に作れる
多くのサービスでは、テキストボックスや画像などのパーツをマウスのドラッグ&ドロップで好きな場所に配置したり、完成形を直接見ながら編集できるエディタが提供されています。
そのため、利用者は複雑なコードを学ぶ必要がなく、サイトに「何を載せるか」という中身の充実に集中して作業を進めることができます。
従来の方法では、テキストエディタでコードを書き、FTPソフトでサーバーにアップロードするといった専門的な手順が必要でしたが、作成サービスを使えば、ブラウザ上でログインし、まるでパワーポイントやワードを操作するような感覚で、見たまま簡単にページを作成できます。
これまで「ホームページ作成は専門家がやること」という高いハードルがありましたが、ITへの苦手意識がある人ほど、このメリットを大きく感じられるでしょう。
メリット(2)デザインテンプレートで美しいサイトが作れる
プロのデザイナーが作成した高品質なデザインテンプレートが豊富に用意されているため、デザインセンスに自信がない人でも、簡単に見栄えの良い美しいサイトを作ることができます。
ゼロからデザインを考えると、全体のレイアウト、配色のバランス、文字の読みやすさなどを考慮する必要があり、非常に高度な知識とセンスが求められます。
テンプレートを使えば、デザインの骨格はプロに任せ、自分は写真や文章といった中身の準備に集中できるため、効率的にクオリティの高いサイトが作れます。



多くのサービスでは、飲食店、美容サロン、士業など、自社の業種に合ったテンプレートが用意されており、それを選ぶだけで必要なページ構成やデザインの方向性が決まります。
また、テンプレートはPCだけでなくスマートフォンでの見やすさも考慮されているため、自分で難しい調整をしなくても、自動的にスマホ対応のサイトが完成します。
メリット(3)短期間でサイト公開まで完了できる
ホームページを作りたいと思い立ってから、実際にサイトをインターネット上に公開するまでの期間を劇的に短縮できることも、大きなメリットです。
これは、サーバー契約やドメイン設定、ソフトウェアのインストールといった、専門的で時間のかかる準備作業が一切不要なためです。
ホームページ作成サービスは、サイトを制作・公開するための環境が全て一つにパッケージ化されており、利用者はサービスにアカウントを登録すれば、すぐにページの作成作業に取り掛かることができます。
自作する場合、レンタルサーバーの契約から始まり、多くの専門的なステップを踏む必要がありますが、作成サービスならその手間を大幅に削減できます。
早い人なら数時間から1日で基本的なサイトを公開することも可能です。
ビジネスの世界ではスピードが重要であり、「すぐにでも名刺代わりのサイトが欲しい」「キャンペーンに合わせて急いで告知ページを作りたい」といったニーズに迅速に応えられるのが、作成サービスの大きな強みです。
メリット(4)スマホからの更新も手軽に可能
多くのホームページ作成サービスは、専用のスマートフォンアプリを提供しているため、パソコンが手元にない外出先からでも、ブログの投稿やお知らせの更新といった作業を簡単に行うことができます。
これらの専用アプリは、スマートフォンの小さな画面でもストレスなく操作できるようにUIが最適化されています。
記事のテキスト入力はもちろん、スマホで撮影した写真をそのままサイトにアップロードすることもできるので、非常にスムーズに情報発信が可能です。
例えば、飲食店オーナーが休憩中にその日のランチメニューをスマホから更新したり、フリーランスが移動中の電車内でブログ記事の下書きを投稿したりといった活用ができます。



Wix、Jimdo、ペライチ、BASEといった主要なサービスの多くが、使いやすいスマホアプリを提供しています。
ホームページ作成サービスのデメリットと注意点


この章では、ホームページ作成サービスの便利な点の裏側にある、利用する前に必ず知っておくべきデメリットや注意点を解説します。
良い面と悪い面の両方を正しく理解することで、「こんなはずじゃなかった」という後悔を防ぎ、ご自身の目的に本当に合った、賢いサービス選びができるようになります。
この章には主に以下の内容があります。
- 無料プランでは広告が表示されることがある
- 独自ドメインの使用に制限がある場合がある
- 突然のサービス終了リスクがある
- SEO対策の自由度が低いケースがある
デメリット(1)無料プランでは広告が表示されることがある
多くのホームページ作成サービスの無料プランでは、サイト上にサービス提供者の広告が自動的に表示されます。
これは、ビジネスで利用する上で、信頼性や専門性を損なう可能性がある最大のデメリットの一つです。
サービス提供者は、サーバー代やシステム開発費をまかなう対価として広告を表示させており、これはいわばサービスを無料で使えることの「代償」です。
例えば、サイトの最下部などに「Wixで作成」といったテキスト広告が表示されると、訪問者に「無料で作ったサイトだ」という印象を与え、プロフェッショナルなイメージを損ないかねません。



特に、信頼性が重要な士業やコンサルタントといったビジネスには不向きです。
ビジネスの顔としてホームページを使うのであれば、広告を非表示にできる月額千円前後の有料プランへのアップグレードは、サイトの信頼性を得るための必要経費と考えるのが賢明です。
デメリット(2)独自ドメインの使用に制限がある場合がある
無料プランの多くは、オリジナルのURLである「独自ドメイン」、例えば「your-company.com」といった形式が使えず、サービス名が含まれる「サブドメイン」での運用になるのが一般的です。
これは、独自ドメインの利用が有料プランの主要な付加価値として提供されているためです。
例えば「your-company.wixsite.com」のようなサブドメインは、URLが長くて覚えにくく、ビジネスとしての信頼性や本格的な印象を与えにくいというデメリットがあります。
一方、独自ドメインは、会社名やサービス名を含めることでブランディングに繋がり、顧客に安心感を与えます。
SEOの観点でも、独自ドメインのサイトの方が長期的な資産として評価されやすい傾向にあります。
名刺やパンフレットに記載する「会社の正式な住所」としてホームページを位置づけるなら、独自ドメインの取得は必須と考えましょう。
広告の非表示と並んで、有料プランを検討する最大の理由となります。
デメリット(3)突然のサービス終了リスクがある
WixやJimdoのようなクラウド型のホームページ作成サービスは、運営会社の経営判断によって、ある日突然サービスが終了したり、大幅な仕様変更や料金改定が行われたりするリスクがゼロではありません。
サイトのデータやシステムは全て運営会社のサーバー上にあり、利用者はそれを「間借り」している状態だからです。



そのため、良くも悪くも、自社のホームページの運命が運営会社の都合に左右されることになります。
過去には、大手企業が提供していた人気のホームページ作成サービスが突然終了を告知し、多くのユーザーがサイトの移転やデータのバックアップに追われた事例もあります。
サービスが終了すると、多くの場合サイトを他のサーバーにそのまま移すことはできず、一から作り直しになる可能性があります。
過度に恐れる必要はありませんが、こうしたリスクがあることは念頭に置き、運営会社の規模や実績を確認したり、定期的にコンテンツを手元に保存したりしておくことをお勧めします。
デメリット(4)SEO対策の自由度が低いケースがある
特に無料プランや、シンプルさを売りにしているサービスでは、Googleなどの検索エンジンで上位表示を目指すための、専門的で高度なSEO設定ができない、または機能が制限されている場合があります。



多くのサービスが「誰でも簡単」であることを優先するあまり、専門的で複雑な設定項目を意図的に削っているためです。
また、高度なSEO機能は有料プランの付加価値として提供されることが多いため、無料プランでは利用できないのが一般的です。
例えば、ページごとに詳細なメタタグ(検索結果に表示される説明文)を設定できなかったり、URLの構造を自由に変更できなかったりといった制限が考えられます。
一般的に、WordPressが最もSEOの自由度が高く、Wixなども有料プランではかなり詳細な設定が可能です。
名刺代わりのサイトであれば大きな問題にはなりませんが、「検索からの集客」を本格的に目指すのであれば、SEO設定の自由度はサービスを選ぶ上で重要な基準となります。
ホームページ制作会社に依頼する場合の料金相場とは?


この章では、DIYのホームページ作成サービスではなく、専門のホームページ制作会社に依頼する場合の料金相場について解説します。
クオリティの高いサイトを求める場合、プロに依頼する選択肢も視野に入ります。



その際に必要となる費用感を理解し、予算計画の参考にしてください。
この章には主に以下の内容があります。
- 小規模サイトの制作費用の目安
- 初期費用と運用費用(月額)の違い
- 依頼時に費用を抑えるための工夫
小規模サイトの制作費用の目安
個人事業主や中小企業が必要とする5〜10ページ程度の小規模なビジネスサイトを制作会社に依頼する場合、費用相場は30万円〜100万円程度が一般的です。
デザインの質や、導入する機能の複雑さによって価格は大きく変動します。
これは、制作会社の料金が、ディレクター、デザイナー、エンジニアといった専門家の人件費、すなわち作業工数がベースになっているためです。
テンプレートをほぼそのまま使うDIYサービスとは異なり、打ち合わせ、企画構成、オリジナルデザインの作成、プログラミング、公開前のテストなど、多くの工程に専門的なスキルと時間が必要となります。



例えば、30万円台からであればテンプレートをカスタマイズしたサイト、50万円以上で企業のブランディングを重視した完全オリジナルデザイン、100万円以上で予約システムやEC機能といった複雑な開発を伴うサイト、というのが一つの目安です。
初期費用と運用費用(月額)の違い
ホームページ制作の費用は、サイトを構築するために最初に一括で支払う「初期費用(制作費)」と、サイトを公開した後に毎月または毎年支払う「運用費用(保守管理費)」の2種類に大別されます。
初期費用がサイトを「建てる」ための費用であるのに対し、運用費用は建てたサイトを安全に「維持・管理」し、正常に機能させ続けるための費用です。
具体的には、サーバーやドメインの利用料、システムの定期的なアップデート、セキュリティ対策、データのバックアップなど、目に見えにくいですがサイト運営に不可欠な作業が含まれます。
月額の運用費用は5,000円〜3万円程度が目安ですが、簡単なテキスト修正や画像差し替えなどの軽微な更新作業をどこまで含んでくれるかは契約内容によって様々です。
見積もりを取る際は、初期費用の総額だけでなく、月々の運用費用がいくらかかり、その料金にどこまでのサポートが含まれるのかを必ず確認することが、長期的なコストを正確に把握する上で不可欠です。
依頼時に費用を抑えるための工夫
ホームページ作成を制作会社に依頼する際、依頼者側で事前の準備をしっかりと行い、制作会社に任せる作業範囲を明確にすることで、制作費用を効果的に抑えることが可能です。
制作費用は、ディレクターやデザイナーといった専門家の作業工数、つまり時間のかかり具合に大きく左右されます。
そのため、依頼者側でできることをやっておくことで、制作会社の作業時間を短縮でき、結果として人件費コストを削減できるのです。
例えば、サイトに掲載する写真素材や、各ページの文章原稿を自分で用意するだけでも、プロのカメラマンやライターに依頼する費用を削減できます。



また、サイトの目的やどのようなページが必要かを事前にまとめておくだけでも、企画・設計の工数を減らせます。
国のIT導入補助金や小規模事業者持続化補助金などが利用できないか調べてみるのも一つの手です。
「全ておまかせ」にするのではなく、自分で準備できることを積極的に行う姿勢が、品質を保ちながらコストを抑える最善の方法と言えるでしょう。
ホームページ作成サービスを選ぶときの比較ポイント


この章では、数多く存在するホームページ作成サービスの中から、ご自身の目的に合った最適なものを、初心者の方でも安心して選ぶための具体的な比較ポイントを解説します。
これらのポイントを押さえることで、「たくさんありすぎて、どれを選べばいいか分からない」という状態から抜け出し、自信を持ってサービスを比較検討できるようになります。
この章には主に以下の内容があります。
- 無料プランでどこまでできるかを確認する
- レスポンシブ対応の有無をチェックする
- サポート体制が整っているか確認する
- 将来的な機能拡張への対応力を見極める
無料プランでどこまでできるかを確認する
ホームページ作成サービスを選ぶ際、「無料」という言葉だけで判断するのは禁物です。
後悔しないためには、まず無料プランで①広告が表示されるか、②オリジナルのURLである独自ドメインが使えるか、③データ容量やページ数に制限はないか、④使いたい機能が制限されていないか、という4点を具体的に確認しましょう。
多くの無料プランは、ビジネスで本格的に使うには不十分な制約が設けられています。



サイトに広告が表示されたり、URLがサービス名を含む長いものになったりすると、プロフェッショナルな印象を損ないかねません。
また、ページ数や機能の制限で、伝えたい情報を十分に載せられないこともあります。
無料プランはあくまで「お試し版」と割り切り、どの制限が自分のビジネスにとって許容できないかを考えることが重要です。
レスポンシブ対応の有無をチェックする
作成するホームページが、パソコン、スマートフォン、タブレットなど、ユーザーが閲覧する機器の画面サイズに合わせて自動的にレイアウトを最適化する「レスポンシブ対応」であることは、現代において必須のチェック項目です。
現在、Webサイトへのアクセスの大半はスマートフォンからであり、スマホで文字が小さすぎたり、ボタンが押しにくかったりするサイトは、訪問者に即座に離脱される原因となります。
これは大きな機会損失に繋がるだけでなく、Googleなどの検索エンジンもスマホ対応をサイトの評価基準に含めているため、SEOの観点からも極めて重要です。
サービスの公式サイトで「スマホ最適化」といった表記を確認するとともに、テンプレートのデモサイトを実際に自身のスマートフォンで閲覧し、文字やボタンが適切な大きさか、レイアウトが崩れていないか、メニューが操作しやすいか、といった点を必ずチェックしましょう。
主要なサービスはほとんどが標準で対応していますが、その「質」には差があるため事前の確認が大切です。
サポート体制が整っているか確認する
特にWeb初心者にとって、操作方法に迷ったり、予期せぬトラブルが発生したりした際に、迅速で的確なサポートを受けられるかどうかは、サービスを安心して使い続けるための生命線とも言える重要な比較ポイントです。
サポート体制が不十分だと、簡単な問題の解決のために何時間も費やしてしまったり、最悪の場合、途中でホームページの作成や更新を挫折してしまったりする原因になります。
サポートにはメール、チャット、電話など様々な形式がありますが、まずは日本語でのサポートに完全に対応しているかを確認しましょう。



また、有料プランと無料プランでサポート内容に差があるのが一般的なので、その違いも把握しておくべきです。
海外製のサービスを選ぶ際は特に注意が必要です。
無料トライアル期間中に、実際にサポートに簡単な質問をしてみて、その対応の速さや丁寧さをご自身の目で確かめてみることを強くお勧めします。
将来的な機能拡張への対応力を見極める
サービス選びの際は、長期的な視点を持つことが非常に重要です。
今はシンプルなサイトで十分でも、将来ビジネスが成長した際に、ブログ、ネットショップ、予約システムといった機能を追加できる「拡張性」があるサービスを選びましょう。
拡張性の低いサービスを選んでしまうと、後から機能を追加したくなった場合に、サービス自体を乗り換えなければならなくなり、それまで費やした時間とコスト、労力が無駄になってしまう可能性があるからです。
例えば、最初は会社概要ページだけだったサイトに、後からブログ機能を追加して情報発信を始めたくなるかもしれません。
また、サービス紹介サイトから、商品を直接販売できるネットショップに移行したくなることも考えられます。
Wixの「App Market」やWordPressの「プラグイン」といった仕組みがあるサービスは、後から機能を追加しやすい代表例です。
現在のニーズだけでなく、「1〜2年後に自分のビジネスはどうなっていたいか」を想像し、その成長に対応できる柔軟性を持ったサービスを選ぶことが、後悔しないための賢い選択です。
まとめ


本記事では、無料ホームページ作成サービスの限界から、目的別の選び方、そして重要な比較ポイントまでを解説してきました。
最も大切なのは、広告の有無や独自ドメインといった無料プランの範囲を正しく理解し、サポート体制や将来性も踏まえて、ご自身のビジネスに最適なサービスを自信を持って選ぶことです。
もう「選択肢が多すぎて分からない」と悩むことはありません。



この記事で得た判断基準を元に、まずは気になるサービスの無料プランを試してみてください。
それがあなたのビジネスを成長させる、最高の第一歩となるはずです。