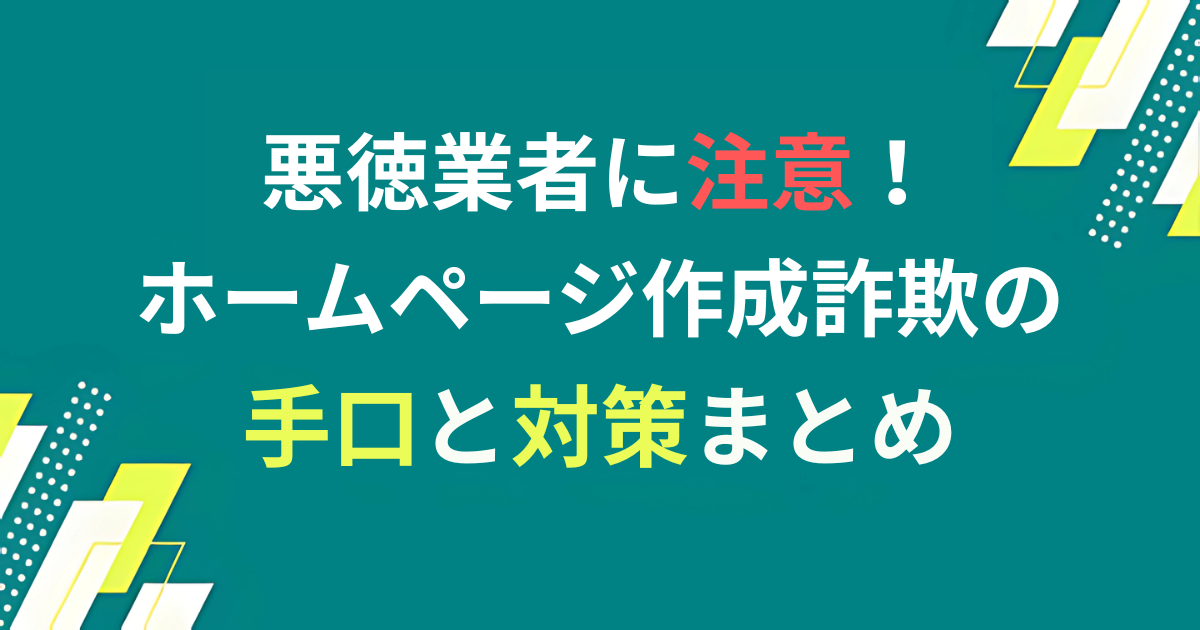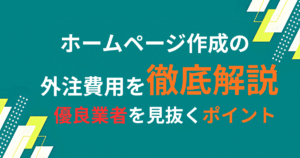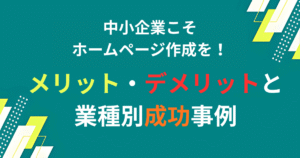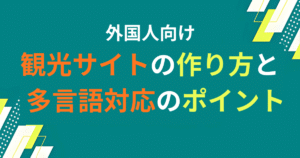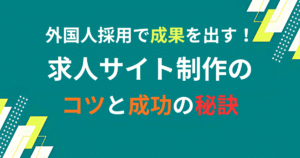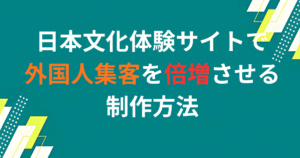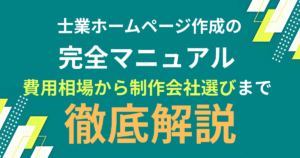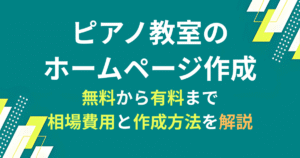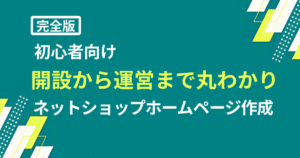ホームページ作成の悪徳業者に騙される中小企業経営者が後を絶たない中、あなたは信頼できる制作会社を正しく見分けられますか?
「格安で高品質」という甘い営業トークや、契約後の追加料金請求、完成後のサポート放棄など、被害事例は枚挙にいとまがありません。
料金相場の妥当性から見積もり内容のチェックポイント、契約書で確認すべき項目まで、騙されないための具体的な判断基準を解説します。



この記事を読めば、安心して任せられるパートナー選びができるようになり、理想のホームページを適正価格で手に入れられるでしょう。
ホームページ作成で悪徳業者の典型的手口は?


この章では、ホームページ制作で悪徳業者が使用する代表的な手口について紹介します。
悪徳業者の典型的手口には主に以下の内容があります。
- 解約不可能なリース契約による長期間の金銭的拘束
- 初期費用無料を謳いながら高額な月額料金や追加オプションでの収益確保
- 実現不可能な集客効果や順位保証による顧客の期待値操作
- 冷静な判断を妨げる契約の即決圧力と不安を煽る営業手法
- ドメインや制作データの所有権を業者側が保持する権利関係の不透明化
- 契約解除時のデータ返却拒否によるビジネス継続への圧力
手口(1)リース契約で長期縛り:解約金や総支払額が不明瞭
悪徳業者の最も悪質な手口は、ホームページ制作をリース契約として提供し、発注者を5年から7年の長期間にわたって金銭的に拘束することです。
本来サービスであるホームページ制作を、パソコンやソフトウェアといった物品のリース契約にすり替えることで、通常の制作契約では適用されるクーリングオフ制度を回避し、契約期間中の解約を事実上不可能にします。
月額3万円で60ヶ月契約の場合、総支払額は180万円に達し、相場の数倍の料金を支払わされることになります。
手口(2)「初期費用0円」の裏で高額な月額・オプション請求
初期費用0円という魅力的な言葉で顧客を惹きつけながら、実際は高額な月額費用や必須オプション料金で収益を確保する手口が横行しています。
資金繰りに悩む中小企業にとって初期費用0円は非常に魅力的に映りますが、悪徳業者はこの心理を巧みに利用します。
月額料金が相場より高額に設定されていたり、SEO対策必須オプション月額5万円、サーバー管理費月額3万円など、本来は基本料金に含まれるべきサービスを別途請求することで、結果的に通常制作費の数倍を支払わせる仕組みです。
手口(3)集客効果の誇大広告:順位保証・架空実績の提示
SEOで必ず1位表示、月間問い合わせ数50件保証といった実現不可能な集客効果を保証し、顧客の期待値を不当に高めて契約に導く手口が多発しています。
Googleの検索アルゴリズムは200以上の要因で決定される複雑なシステムで、特定のサイトを必ず1位にすることは技術的に不可能です。
また、ビジネスの成果は市場環境や競合状況、営業努力など多要因に依存するため、ホームページ制作だけで問い合わせ数保証することも現実的ではありません。
手口(4)契約を急がせる強引営業:即決割・不安を煽る説明
本日中の契約で50パーセント割引、今月末までの限定価格といった時間的プレッシャーや、競合他社に負けますよ、今やらないと手遅れになりますといった不安を煽る営業手法で冷静な判断を妨げます。
悪徳業者は顧客が他社と比較検討したり、契約書を詳細に確認したりする時間を与えたくないため、意図的に即決を迫ります。
優良な制作会社であれば顧客がじっくり検討することを歓迎するはずで、急かす必要はありません。
手口(5)権利を渡さない:ドメイン・デザイン・原稿が業者名義
制作したホームページのドメイン、デザインデータ、掲載原稿などの所有権を業者側が保持し続けることで、顧客を長期間にわたって支配下に置く手口が蔓延しています。
ドメインはインターネット上の住所であり、業者名義のままだと他社への移管ができません。
また、デザインデータや写真、原稿の著作権が業者側にあると、サイトのリニューアルや他社への移管時に膨大な制約が生じます。



これにより顧客は不満があっても業者を変更できず、不当な要求を受け入れざるを得ない状況に追い込まれます。
手口(6)解約後のデータ引き渡し拒否やサイト停止で圧力
契約解除や他社への移管を申し出た顧客に対し、サイトデータの引き渡しを拒否したり、突然サイトを停止したりして、ビジネス継続への圧力をかける悪質な手口が報告されています。



顧客が業者から離れようとする際、最後の切り札として使われるのがこの手法です。
現代のビジネスにとってホームページは不可欠なツールのため、サイト停止は大きな打撃となります。
悪徳業者はこの弱みにつけ込み、サイトを止められたくなければ言うことを聞けと脅迫的な圧力をかけてきます。
ホームページ作成の悪徳業者をどう見分ける?7つの警告サイン


この章では、ホームページ制作における悪徳業者を事前に見分けるための重要な警告サインについて紹介します。
悪徳業者を見分ける7つの警告サインには主に以下の内容があります。
- 料金体系の不透明さと見積内訳の提示拒否による金銭的リスクの隠蔽
- 制作実績の証拠提示拒否とURL・担当範囲・成果の曖昧な説明
- インターネット上の悪い口コミや被害報告の多発と評価の偏り
- 契約書の曖昧な条項設定と解約・所有権に関する不公平な取り決め
- コミュニケーション面での問題と連絡体制の不備
- 完成後のデータや所有権に関する不透明な取り扱い
- 根拠のない断言的な営業トークと非現実的な成果保証
サイン(1)料金体系が不透明:見積内訳や算定根拠を提示しない
悪徳業者の最も分かりやすい特徴は、料金体系が不透明で見積書に具体的な内訳や算定根拠を記載しないことです。
優良な制作会社であればデザイン費、コーディング費、ディレクション費など、どの作業にどれだけの費用がかかるかを明確に提示できます。
しかし悪徳業者はホームページ制作一式のような曖昧な項目で総額のみを提示し、後から別料金ですと追加請求する余地を残そうとします。
サイン(2)制作実績の証拠不提示:URL・担当範囲・成果が曖昧
制作実績として掲載されているサイトのURL提示を拒んだり、実際の担当範囲や達成した成果について曖昧な説明しかできない業者は信頼性に大きな疑問があります。
本当に優れた制作実績があればクライアントの許可を得た上でサイトURLを公開し、具体的な成果をアクセス数増加や問い合わせ件数向上などの数値で示すことができるはずです。
サイン(3)悪い口コミ・被害報告が多数:評価の偏りが顕著
インターネット上で継続的に悪い口コミや被害報告が投稿されており、評価に極端な偏りが見られる業者は避けるべきです。
現代では消費者が簡単に口コミを投稿できるため、悪徳業者の被害情報は必ずインターネット上に蓄積されます。
Googleマップのレビュー、SNS、比較サイトなどで複数の被害報告が確認できる場合、それは偶然ではなく構造的な問題があることを示しています。
サイン(4)契約書が曖昧・不公平:解約・所有権条項が不利
契約書の内容が曖昧で、特に解約条項や所有権に関する取り決めが発注者に著しく不利な業者は悪徳業者の典型的特徴です。
優良な制作会社は公平で明確な契約条件を提示しますが、悪徳業者は自社に有利で顧客に不利な条項を盛り込み、トラブル時に法的優位性を確保しようとします。



飲食店が契約書を弁護士にチェックしてもらったところ、発注者都合による解約の場合は残り契約期間分の料金を全額支払う、制作されたデザインとコンテンツの著作権は制作会社に帰属する、ドメインの所有権は制作会社が保持するといった極めて発注者に不利な条項が多数発見され、通常の制作契約では考えられない一方的な内容でした。
サイン(5)連絡が途絶えがち:返信遅延・担当窓口が不明確
契約前の段階で既に連絡が途絶えがちで、メールや電話の返信が遅い、担当者が頻繁に変わる業者は契約後により深刻なコミュニケーション問題を起こす可能性が高いです。
ホームページ制作は密接なコミュニケーションが必要なプロジェクトであり、制作会社の対応品質は最終的な成果物の品質に直結します。
税理士事務所が複数社に相談した際、ある制作会社は初回の電話から3日後にやっと返信があり、担当者名も田中としか名乗らず会社での役職や連絡先も教えてくれませんでした。
サイン(6)所有権・データ納品なし:源データやアカウント非開示
完成したホームページのソースコード、デザインデータ、各種アカウント情報の納品や権利移譲について明確な説明ができない業者は、顧客を長期間拘束する意図があります。
正当な制作会社であれば制作物の所有権や必要なデータの引き渡しについて明確なポリシーを持っているはずです。
しかし悪徳業者はドメイン、サーバー、各種アカウントの所有権を自社に残すことで、顧客が他社に移管できない状況を作り出し継続的な収益を確保しようとします。
サイン(7)根拠なき断言:「必ず集客」「検索1位保証」など
必ず集客できます、検索で1位を保証しますといった根拠のない断言的な営業トークを使う業者は、専門知識が不足しているか意図的に顧客を騙そうとしています。
Webマーケティングの成果は競合状況、市場環境、継続的な運用など多くの要因に左右される複雑なものです。
特にGoogleの検索順位は200以上のアルゴリズム要因で決定されるため、特定の順位を絶対的に保証することは技術的に不可能です。
美容室の経営者が弊社のSEO技術で必ず地域名プラス美容室で1位表示を保証します、月間50件の予約を約束しますという提案を受けましたが、専門家に相談したところ該当キーワードの競合は30社以上あり1位保証は不可能であること、予約数は立地や価格設定、サービス内容に大きく左右されるためホームページだけで保証できるものではないことが判明しました。
悪徳業者被害を防ぐ対策法は?


この章では、ホームページ制作で悪徳業者の被害に遭わないための具体的な対策法について紹介します。
悪徳業者被害を防ぐ対策法には主に以下の内容があります。
- 複数社からの相見積もり取得による料金と条件の適正性判断
- 制作実績の詳細確認とURL・担当範囲・具体的成果の証拠要求
- 口コミ情報と法人登記・所在地の実在性確認による信頼性検証
- 契約書条項の専門家チェックによる不利条件の事前排除
- 即日契約回避と十分な検討期間確保による冷静な判断の実現
対策(1)必ず複数社で相見積もり:同一仕様で条件比較
悪徳業者を見抜く最も効果的な対策は、必ず3社以上から同一仕様での相見積もりを取得し、料金・条件・提案内容を詳細比較することです。
1社だけの見積もりでは価格や条件が適正かどうか判断できません。
悪徳業者は相場より高額な料金設定や不利な契約条件を提示してきますが、複数社を比較することでこれらの異常性が明確になります。
税理士事務所が4社に同一条件で見積もりを依頼した結果、A社80万円、B社85万円、C社70万円と詳細内訳があったのに対し、D社は150万円で税理士向け特別パッケージ一式としか記載されず、内訳を求めると他社と比較されるのは心外ですと感情的な対応を示した事例があります。
相見積もりを取る際はページ数、機能、デザインの方向性、納期などの条件を統一し、書面で各社に提示することが重要です。
対策(2)制作実績の詳細確認:URL・担当範囲・KPIの提示を要求
制作会社の実力と信頼性を正確に判断するため、制作実績の詳細確認として実際のサイトURL、担当範囲、達成したKPI(成果指標)の具体的な提示を必ず要求してください。
悪徳業者は実績を偽装したり誇張したりする傾向があるため、口頭の説明だけでは真偽を判断できません。
実際のサイトURLを確認することで、デザインの質、機能の充実度、ユーザビリティを自分の目で評価できます。
美容院経営者がホームページ制作会社に美容業界で多数の実績がありますという説明に対し、具体的なURL提示を求めたところ、その会社が担当したのはトップページのデザインのみで、機能開発や運用は別会社が担当していたことが判明し、リニューアル後の来店客数30%増加という説明の根拠となる数値データも提示されませんでした。
対策(3)口コミ・法人情報・所在地の実在確認:電話・登記・地図
業者の信頼性を確認するため、インターネットの口コミ情報、法人登記情報、実際の所在地を複数の方法で実在確認することが不可欠です。
悪徳業者は会社の実体が不明確だったり、登記上の住所と実際の営業場所が異なったりするケースが多くあります。
法人登記情報を確認することで、会社の設立年月日、資本金、代表者名などの基本情報が正確かどうかを確認でき、所在地の実在確認により実際に営業活動を行っている会社かどうかを判断できます。
整骨院経営者が制作会社の信頼性を調査した際、Google検索での評価確認、国税庁の法人番号公表サイトでの法人登記確認、Googleマップでの所在地確認、記載電話番号への架電確認を行った結果、登記上の住所がワンルームマンションで実際のオフィスが存在しない業者を事前に排除できました。
対策(4)契約書の専門家チェック:解約・所有権・瑕疵担保・SLA
契約書の内容について、弁護士や中小企業診断士などの専門家によるチェックを受け、特に解約条項・所有権・瑕疵担保責任・SLA(サービス品質保証)の条項を重点的に確認することが重要です。
ホームページ制作契約書には専門的な法律用語や技術用語が多く含まれており、素人では不利な条項を見抜くことが困難です。
悪徳業者は巧妙に不公平な条項を盛り込み、トラブル時に法的優位性を確保しようとします。
工務店が制作会社から提示された契約書を弁護士にチェックしてもらったところ、発注者都合による解約時は全制作費の80%を違約金として支払う過重な負担、制作物の著作権は制作会社に帰属する制約、納品後30日を超えた不具合については一切責任を負わない短期限定といった問題が発見され、適正な内容に修正させることができました。
対策(5)即日契約を避ける:冷却期間と社内合意プロセスを設定
悪徳業者の即決営業に惑わされないよう、契約前に必ず1週間以上の冷却期間を設け、社内での十分な検討と合意プロセスを経てから最終判断を行ってください。
悪徳業者は本日限りの特別価格や今月末までのキャンペーンなどの時間的プレッシャーで冷静な判断を妨げようとします。
しかしホームページ制作は数十万円から数百万円の重要な投資であり、性急な判断は失敗の原因となります。
飲食店経営者が制作会社から今日契約していただければ通常150万円のところを100万円でご提供しますという提案を受けましたが、1週間検討させてくださいと回答し、その間に他社3社からも見積もりを取得したところ、同等の内容で70万円から90万円が相場であることが判明し、検討期間を求めた途端に態度が豹変した業者を悪徳業者と判断して契約を回避できました。
信頼できるホームページ制作会社の選び方は?


この章では、ホームページ制作を依頼する際に信頼できる制作会社を見極めるための具体的な選び方について紹介します。
信頼できるホームページ制作会社の選び方には主に以下の内容があります。
- 透明性の高い料金体系と見積もり内訳の詳細提示による信頼性の確認
- 具体的な制作実績と顧客評価の公開による実力の客観的判断
- 丁寧なヒアリングと専門的な提案力による顧客理解度の評価
- 充実したアフターサポート体制とSLA(サービス品質保証)の明示
- 著作権やドメインなどの権利関係とデータ納品に関する明確な取り決め
- 解約条項や検収基準など契約条件の透明性と公平性の確保
選び方(1)透明な料金と根拠:見積内訳・算定式・増減条件の明示
信頼できる制作会社は見積書に詳細な内訳と算定根拠を明記し、追加費用が発生する条件も事前に明示してくれます。
優良な制作会社は自社の作業プロセスとコスト構造を把握しており、どの工程にどれだけの時間と費用がかかるかを正確に算出できます。
また顧客との信頼関係を重視するため、後から追加請求で驚かせるような不透明な料金設定は行いません。
優良な制作会社の事例では、ディレクション費20万円(工数40時間×時給5000円)、デザイン費30万円(トップページ15万円+下層ページ5ページ×3万円)、コーディング費25万円(レスポンシブ対応含む)といった詳細内訳を提示し、さらにページ追加時は1ページあたり3万円、修正は3回まで無料、以降は1回1万円といった増減条件も明記していました。
選び方(2)実績と顧客の声:公開URL・担当範囲・評価の具体性
信頼できる制作会社は制作実績のURLを公開し、担当した具体的な作業範囲と顧客からの評価を詳細に提示してくれます。
本当に実力のある制作会社であればクライアントの許可を得た上で制作実績を堂々と公開し、自社の担当範囲と達成した成果を具体的に説明できるはずです。
また顧客からの評価も抽象的な賞賛ではなく、具体的なプロジェクト内容や成果について言及された信頼性の高いものを提示できます。
優良な制作会社の実績例では、○○クリニック様として実際のサイトURLを提示し、企画・デザイン・開発・運用まで一貫対応、リニューアル後月間問い合わせ数が15件から45件に増加(3倍向上)、クライアント評価として「SEO対策の提案が的確で実際に検索順位が大幅に向上した」といった具体的な実績を提示していました。
選び方(3)丁寧なヒアリングと提案力:要件定義・代替案・リスク説明
信頼できる制作会社は丁寧なヒアリングを通じて顧客の真のニーズを理解し、複数の代替案とリスクも含めて提案してくれます。
ホームページ制作の成功は顧客のビジネス課題や目標を正確に理解することから始まります。
優良な制作会社は単にホームページを作るのではなく、そのホームページで何を達成したいのかを深く掘り下げて要件定義を行います。
飲食店の相談に対し優良な制作会社は2時間のヒアリングを実施し、集客が目的であればWebサイトだけでなくInstagramとの連携も重要、予算を抑えたい場合はWordPressテンプレート活用案もあるがオリジナルデザインと比べて差別化が困難、Googleマイビジネス最適化も同時に行うことで相乗効果が期待できるといった多角的な提案を実施していました。
選び方(4)アフターサポート体制:保守範囲・SLA・改善提案の頻度
信頼できる制作会社は公開後のサポート範囲とSLA(サービス品質保証)を明確に定義し、継続的な改善提案も行ってくれます。
ホームページは作って終わりではなく、継続的な運用と改善が成功の鍵となります。
優良な制作会社はサーバー管理、セキュリティ対策、バックアップ、軽微な修正対応などサポート内容を具体的に定義し、応答時間や復旧時間などのSLAも明示します。
優良な制作会社のサポート内容例では、月額2万円で24時間サーバー監視、バックアップ、SSL証明書更新、軽微な修正月3回まで無料、障害時は2時間以内に対応開始、24時間以内に復旧完了をSLAとして保証、四半期ごとにアクセス解析レポートと改善提案を提供といった具体的な内容が明示されていました。
選び方(5)権利・データの取り扱い:著作権・ドメイン・納品形式
信頼できる制作会社は著作権、ドメイン、制作データなどの権利関係と納品形式について契約書で明確に定義してくれます。
将来的なサイトリニューアルや業者変更の際、権利関係が不明確だと大きなトラブルの原因となります。
優良な制作会社は制作物の著作権譲渡、ドメインの所有権、ソースコードや画像データの納品について、顧客の権利を尊重した明確な取り決めを行います。
優良な制作会社の権利関係条項例では、制作費全額支払い完了をもってデザイン・コンテンツ・プログラムの著作権は発注者に譲渡、ドメインは発注者名義で取得・管理、納品時にはWordPressファイル一式、データベースエクスポート、使用画像の高解像度データをすべて提供するといった顧客に有利な条件が設定されていました。
選び方(6)契約条件の明確さ:解約条項・再委託・検収基準
信頼できる制作会社は解約条項、再委託の条件、検収基準などの契約条件を公平かつ明確に定義し、顧客が不利にならない内容で契約を締結してくれます。
契約条件の明確さはその会社の法的リテラシーと顧客に対する誠実さを表す重要な指標です。
優良な制作会社は万が一のトラブルや契約解除の際にも双方が納得できる公平な条件を設定します。
優良な制作会社の契約条件例では、正当な理由による解約時は完了済み作業分のみ請求、再委託は事前書面承諾制で委託先の責任も当社が負担、検収期間は2週間とし軽微な修正は無制限に対応といった公平で顧客に配慮した条件が設定されていました。
契約条件の確認では解約時の費用負担と条件、再委託の可否と責任範囲、検収期間と修正対応の範囲を重点的にチェックすることが重要です。
契約前の最終チェックリストは?


この章では、ホームページ制作会社との契約前に必ず確認すべき最終チェックリストについて紹介します。
契約前の最終チェックリストには主に以下の内容があります。
- 要件定義書・RFPの整備によるページ数・機能・プロジェクトスコープの明文化
- 初期費用・月額費用・更新費用・解約費用を含む総額の正確な把握
- 著作権・制作データ・ドメインなどの権利関係における帰属先の明確化
- 検収基準とテスト観点・納品形式・受け渡し期限の詳細確認
- 運用開始後の体制と担当者・SLA・緊急時対応手順の事前確認
チェック(1)要件定義書・RFPの整備:ページ数・機能・スコープを明文化
契約前に必ず要件定義書またはRFP(提案依頼書)を作成し、制作するページ数、実装する機能、プロジェクトのスコープを書面で明文化することが重要です。
口約束や曖昧な仕様のまま契約を進めると、聞いていた内容と違う、それは契約範囲外ですといったトラブルが必ず発生します。
悪徳業者は意図的に仕様を曖昧にしておき、後から追加料金を請求する口実を作ろうとします。
整骨院のホームページ制作で曖昧な要件のまま契約した結果、お客様の声ページは別途20万円、予約システム連携は初期設定で30万円プラス月額5万円、Googleマップ埋め込みは追加料金10万円と次々に追加請求された事例があります。
要件定義書には最低限、制作ページ数と各ページの内容、実装する機能の詳細、対応ブラウザとデバイス、SEO対策の範囲を明記してください。
チェック(2)総額の把握:初期・月額・更新・解約費を合算
契約期間全体を通じて発生する総費用を正確に把握するため、初期費用、月額費用、更新費用、解約費用をすべて合算して総額を計算することが不可欠です。
悪徳業者は初期費用0円、月額料金格安といった一部分だけを強調し、実際の総額を分かりにくくする戦術を使います。
ホームページ制作の真のコストは契約期間全体で発生する総額であり、これを正確に把握しなければ適正価格かどうか判断できません。
美容院が2つの業者を比較した際、A社は初期費用50万円、月額1万円、3年契約で総額86万円に対し、B社は初期費用0円、月額3.5万円、5年契約、途中解約時は残額の80パーセント支払いで総額210万円となることが判明しました。
総額計算では初期制作費用、月額保守・運用費用かける契約月数、契約更新時の費用、途中解約時の違約金を全て含めて比較してください。
チェック(3)権利関係の確認:著作権・データ・ドメインの帰属
制作されるホームページの著作権、制作データ、ドメインの所有権が最終的にどこに帰属するのかを契約書で明確に確認し、顧客側に権利が移転されることを確実にすることが重要です。
権利関係が不明確だと将来のサイトリニューアルや業者変更時に大きな制約となります。
悪徳業者は著作権や所有権を自社に残すことで顧客を囲い込み、継続的な収益を確保しようとします。
工務店が制作会社と5年契約を結んだ際、契約書に制作物の著作権は制作会社に帰属、ドメインは制作会社名義で管理と記載されていました。
3年後にサービスに不満を感じて他社への移管を検討したところ、サイトのデザインやコンテンツは弊社の著作物のため使用不可、ドメイン移管には移管料200万円が必要と要求されました。
権利関係の確認では制作物の著作権移転条件、ドメインの所有権者と管理権限を必ず明文化してもらってください。
チェック(4)検収基準と受け渡し物:テスト観点・納品形式・期限
完成したホームページを正式に受け入れる検収基準と、納品される成果物の形式・内容・期限を事前に詳細に定義し、双方で合意しておくことが必要です。
検収基準が曖昧だと、完成したと思ったら多数の不具合があった、期待していた機能が実装されていないといった問題が発生した際に責任の所在が不明確になります。
悪徳業者は検収期間が過ぎたので追加料金、軽微な修正も有料対応といった追加請求の口実にします。
レストランのホームページ制作で検収基準を詳細に定めた結果、全ページのスマートフォン表示確認、お問い合わせフォームのメール送受信テスト、メニューページの画像表示テスト、Google検索での表示確認などの項目で不具合を事前に発見し、追加費用なしで修正対応してもらえました。
検収基準では動作確認項目、対応ブラウザ・デバイスでの表示確認、検収期間と修正回数の上限を明確に定義してください。
チェック(5)運用体制と連絡窓口:担当者・SLA・緊急時の手順
ホームページ公開後の運用体制として、担当者の明確化、SLA(サービス品質保証)の定義、緊急時の連絡手順を事前に確立し、継続的なサポートの質を確保することが重要です。
ホームページは公開後の運用が成功の鍵となりますが、サポート体制が不明確だと担当者が分からない、連絡しても返事が来ない、障害時の対応が遅いといった問題が発生します。
悪徳業者は契約時だけ手厚い対応を見せ、公開後は対応が著しく悪化する傾向があります。
クリニックが制作会社と契約した際の運用体制では、専任担当者田中(メール・電話での直接連絡可能)、バックアップ担当佐藤、メール問い合わせは営業日24時間以内に返信、緊急時(サイト停止等)は2時間以内に対応開始、月1回の定期レポート提供が明示されていました。
運用体制の確認では専任担当者の氏名・連絡先・役職、問い合わせ応答時間のSLA、緊急時の連絡手順を必ず明文化してもらってください。
まとめ
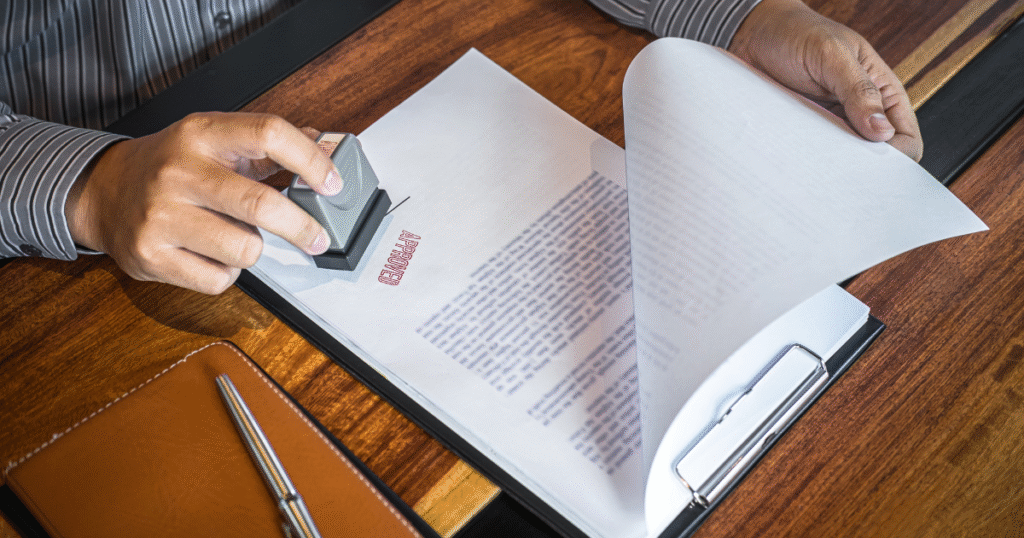
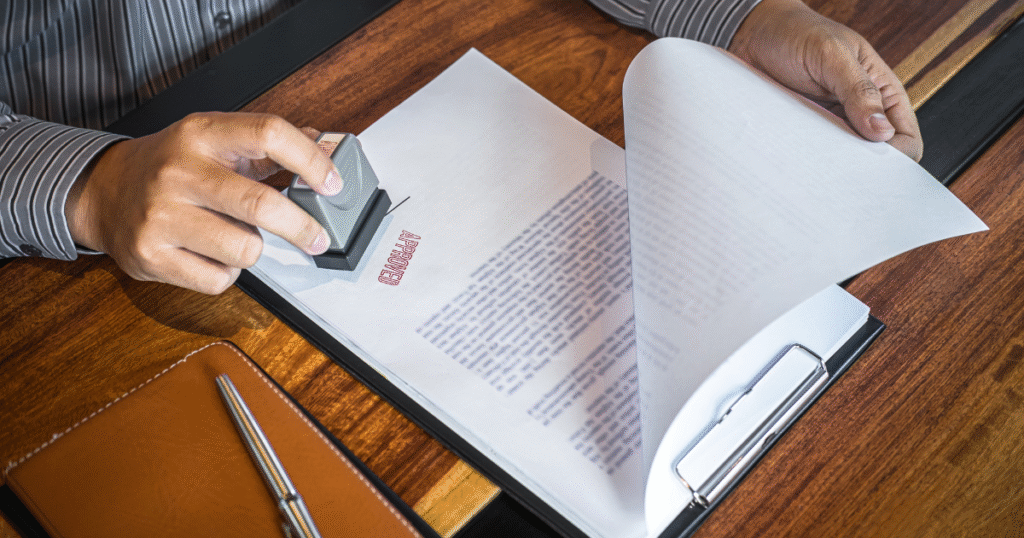
悪徳ホームページ制作業者による高額請求や契約トラブルを避けるには、その手口を知り、契約前に相手を冷静に見極めることが不可欠です。



見積もりの内訳が不透明、制作実績のURL提示を渋る、「必ず儲かる」と断言するなど、本記事で紹介した「警告サイン」が一つでも見られたら、その場で契約してはいけません。
必ず複数社から相見積もりを取り、契約書の内容、特にサイトの所有権が自社にあるかをしっかり確認しましょう。



この一手間を惜しまないことが、信頼できるパートナーと出会い、後悔のないホームページ制作を実現する最も確実な方法です。