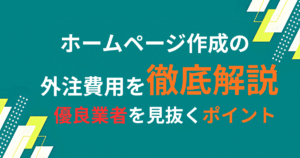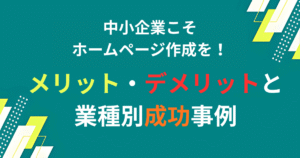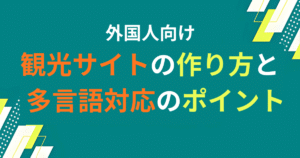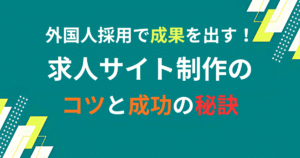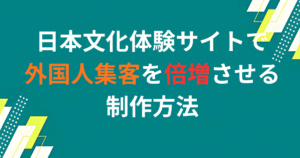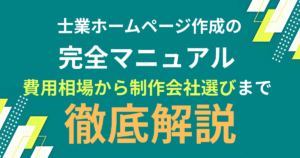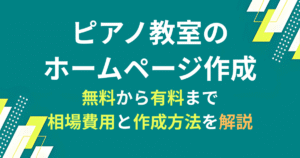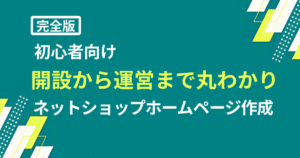「今のホームページでは集客できない…」「不動産のホームページ作成は費用が高そうで、どこに頼めばいいか分からない」そんな悩みを抱えていませんか?
この記事を読めば、Webの専門知識がなくても、失敗しない制作会社の選び方と成果を出すサイトの作り方が明確になります。
本記事では、不動産ホームページ作成の費用相場や目的、必要な機能から、業者選びの具体的なポイントまで網羅的に解説。

あなたもこの記事を実践すれば、反響の鳴りやまない「会社の資産となるホームページ」を自信を持って手に入れられます。
不動産業界におけるホームページ作成の目的とは?


この章では、不動産会社がホームページを持つべき「本当の目的」を、単なる会社案内以上の戦略的ツールとして解説します。
多くの経営者が抱える「サイトはあるが集客できない」という悩みの原因を突き止め、ホームページが「集客」「信頼獲得」「業務効率化」「ブランド構築」という4つの重要な経営資産になり得ることを明らかにします。
この章を読むことで、読者は自社のホームページに何を期待し、どのような目的意識を持って制作に臨むべきかを具体的に理解できます。
- 目的(1)集客とお問い合わせ獲得を促進する
- 目的(2)会社の信頼性・安心感を高める
- 目的(3)業務効率化と情報共有の強化
- 目的(4)企業ブランディングを構築する
目的(1)集客とお問い合わせ獲得を促進する
ホームページ作成における最大の目的は、高額な掲載費用がかかるポータルサイトへの依存から抜け出し、自社で直接、質の高い見込み客を獲得する仕組みを構築することです。
現代のユーザーは、賃貸や売買を問わず、まずWebで情報を探します。



自社のホームページは、広告費を抑えながら24時間体制で会社の魅力を伝え、反響を生み出す強力な営業ツールとなり得ます。
例えば、ある不動産会社では、地域のニーズを捉え「学区から探す」という独自の検索機能を導入し、問い合わせを大幅に増やした実績があります。
「ペット可」や「駐車場完備」といった特定の条件で探せる詳細な検索機能や、自社しか持たない物件情報を充実させることで、ユーザーの具体的な悩みに応え、来店や契約へとつなげることが可能です。
このように目的を明確にしたサイト設計が、持続的な集客を実現します。
目的(2)会社の信頼性・安心感を高める
不動産業は、お客様の人生における大きな決断に寄り添う仕事です。
だからこそ、ホームページ作成を通じて会社の信頼性や安心感を伝えることは極めて重要になります。
情報が古い、またはスマホ表示に対応していないサイトは、専門知識を疑われ、お客様が離れる原因になりかねません。
信頼を獲得するためには、スタッフの顔写真付きプロフィールや、お客様からの直筆の感謝メッセージといった「人の温かみ」が伝わるコンテンツが有効です。



さらに、宅地建物取引士など保有資格の明記や、会社の理念、過去の実績を明記することで、企業としての誠実な姿勢を示すことができます。
実際に、物件の周辺情報を地図で分かりやすく案内するデザイン改善で、ユーザーの不安を解消し、サイトからの離脱率を大幅に下げた成功事例もあります。
問い合わせ前の段階でいかに安心感を与えられるかが、成約への分かれ道となるのです。
目的(3)業務効率化と情報共有の強化
不動産会社のホームページは、集客だけでなく、日々の煩雑な業務を効率化し、生産性を向上させるという重要な目的も担います。



特に物件情報の管理は、多くの担当者が悩む点ではないでしょうか。
手作業でのデータ入力や、複数のポータルサイトへの個別登録は、多大な時間と手間を要し、入力ミスの原因にもなります。
しかし、専門の制作会社が開発する不動産業向けのホームページには、物件管理システム(CMS)が搭載されていることが多く、この課題を解決できます。
例えば、一つの管理画面に物件情報を入力するだけで、自社サイトはもちろん、SUUMOやHOME’Sといった大手ポータルサイトにもデータを一括で反映・連動させることが可能です。
目的(4)企業ブランディングを構築する



ホームページは、自社の「強み」や「専門性」を顧客に伝え、他社との明確な差別化を図るための強力なブランディングツールです。
特に地域に根差した不動産会社にとって、価格競争に陥りがちなポータルサイトと同じ戦い方をするのではなく、「このエリアのことなら、この会社に任せたい」とお客様から選ばれる存在になることが不可欠です。
ホームページのデザインや色使い一つで、企業イメージ(例:高級感を出す黒、親しみやすい緑)を演出できます。
さらに、「〇〇区の子育て環境徹底リサーチ」といった、その地域に住む人ならではの視点で作成した独自のコンテンツを発信することは、自社の専門性をアピールし、顧客との間に深い信頼関係を築くためのマーケティング施策として非常に有効です。
このように自社の魅力を最大限に伝えることで、独自のブランドを確立し、安定した経営基盤を築くことができます。
不動産ホームページの主な作成方法とは?


この章では、不動産会社のホームページを作成するための具体的な4つの方法を、それぞれのメリット・デメリットと共に解説します。
ホームページ作成と一口に言っても、「制作会社への依頼」から「自社での制作」まで選択肢は様々です。
Webの専門知識に不安があったり、予算が限られていたりする経営者・担当者様が、自社の状況や目的に最も合った方法を見つけられるよう、費用相場、品質、必要な手間といった観点から各手法を徹底比較します。
- 方法(1)制作会社へ依頼する
- 方法(2)不動産専用の作成ツールを使う
- 方法(3)CMSを活用して自社制作する
- 方法(4)フリーランスに依頼する
方法(1)制作会社へ依頼する



専門のホームページ制作会社へ依頼する方法は、品質と成果を最も重視する場合に最適な選択です。
特に不動産業界に特化した企業は、効果的な集客ノウハウや物件管理システムとのデータ連動といった専門知識を蓄積しています。
戦略的な提案からオリジナルのデザイン作成、開発、公開後の運用サポートまで一括して任せられるため、Webの専門スタッフがいない会社でも安心です。
費用は高額になる傾向がありますが、自社の強みを最大限に反映した設計で競合との差別化を図り、企業のブランドイメージを向上させる効果が期待できます。
依頼する際は、過去の制作実績、特に不動産サイトでの成功事例をよく確認し、丁寧なヒアリングを通じて要望を深く理解してくれるパートナーを選ぶことが成功の鍵となります。
方法(2)不動産専用の作成ツールを使う



高額な初期費用を抑えつつ、迅速に高機能なホームページを導入したい不動産会社には、業界に特化した作成ツールの利用がおすすめです。
これらのクラウドサービスは、反響獲得に不可欠な物件検索機能や、SUUMOなどのポータルサイトとのデータ一括連動、顧客管理システム(CMS)といった機能が予めパッケージ化されています。
そのため、ゼロから開発する必要がなく、低コストかつ短期間でのサイト公開が可能です。
料金体系は月額制が多く、システムの保守やアップデートは提供元が行うため、Webの専門知識がない担当者でも安心して運用を続けられます。
デザインはテンプレートがベースとなりますが、プロが設計した実績ある構成を利用できるため、効率的に成果を出したい企業にとって非常に合理的な選択肢と言えるでしょう。
方法(3)CMSを活用して自社制作する
WordPressなどのCMSを活用した自社制作は、金銭的な初期費用を最も低く抑えられる方法です。



「ホームページ 作成 無料」といったキーワードで探せる情報の多くがこのタイプにあたります。
「ホームページ 作成 無料」といったキーワードで探せる情報の多くがこのタイプにあたります。
しかし、この選択肢には専門知識と多大な時間という、目に見えないコストが伴うことを理解しなくてはなりません。
サーバーやドメインの契約から、デザインテーマの選定、物件検索機能を追加するプラグインの導入、そして日々のセキュリティ対策まで、すべてを自らの手で行う必要があります。
Webに詳しくない方がゼロから挑戦した場合、デザインが崩れたり、操作性が悪かったりと、かえって会社の信頼を損なうサイトになってしまう危険性が高いです。
プロのクオリティを実現するには相当な労力が必要なため、安易な選択はおすすめできません。
方法(4)フリーランスに依頼する
制作会社への依頼と自社制作の中間的な選択肢として、個人のWeb制作者であるフリーランスに依頼する方法があります。
制作会社に比べて費用を抑えながら、テンプレートではないオリジナルデザインのホームページを持てる可能性があるのが大きなメリットです。
ただし、この方法を成功させるには、依頼者側にも注意が必要です。
フリーランスはスキルや経験、対応の速さに個人差が大きいため、過去の実績、特に不動産業界のサイト制作経験があるかを慎重に見極めなくてはなりません。



また、進行管理や細かな仕様の伝達は自社で行う必要があり、発注者の負担は比較的大きくなります。
作りたいサイトのイメージが明確で、プロジェクト管理を自ら行える場合は、費用対効果の高い選択肢となり得ますが、信頼できるパートナー選びがすべてを左右します。
不動産ホームページ作成にかかる費用の目安


この章では、不動産会社の経営者様が最も気になる「ホームページ作成の費用」について、その内訳から相場、コストを抑える方法までを具体的かつ網羅的に解説します。
「一体いくらかかるのか」「高額な請求をされないか」といった不安を解消するため、費用の内訳を「初期費用」と「月額・運用費用」に分解し、それぞれの相場感を提示します。
さらに、選ぶ制作方法によって費用がどう変わるのか、そして賢くコストを抑えるための実践的なポイントまで紹介し、予算内で最大の効果を得るための道筋を明らかにします。
- 費用(1)初期費用の内訳と相場
- 費用(2)月額・運用費用の目安
- 費用(3)制作方法による費用の違い
- 費用(4)費用を抑えるためのポイント
費用(1)初期費用の内訳と相場
不動産ホームページの作成にかかる初期費用は、サイトの規模や機能の複雑さによって数万円から数百万円までと大きな幅があります。
この費用は主に、どのようなサイトにするかを決める「企画・設計費」、見た目を作る「デザイン費」、そして物件検索などの仕組みを構築する「システム開発費」から構成されています。
例えば、フルオーダーメイドで制作する場合、企画費に15万円以上、デザイン費に30万円以上、複雑なシステム開発には50万円以上の費用がかかることも珍しくありません。



一方で、テンプレートを活用すればこれらの制作費用を大幅に抑えることが可能です。
複数の制作会社から見積もりを取る際は、総額だけでなく、こうした項目ごとの内訳を必ず確認し、価格の妥当性を判断することが重要です。
費用(2)月額・運用費用の目安
ホームページは公開したら終わりではなく、その価値を維持するために月々の運用費用が継続的に発生します。
このコストを見落とすと、後々のトラブルにつながりかねません。
主な内訳は、サイトのデータを保管する「サーバー代」と「ドメイン代」、そしてセキュリティの維持やシステムの更新を行う「保守・管理費」です。



相場としては月々1万円から5万円程度が一般的ですが、これには軽微な修正作業や操作に関する質問への対応といったサポート費用が含まれている場合もあります。
また、サイトへのアクセス増加に伴うサーバーの増強費用や、SSL証明書の年間更新料など、別途必要となる料金もあるため、契約前にサポートの範囲と内容を詳細に確認しておくことが、安心してサイト運用を続けるための鍵となります。
費用(3)制作方法による費用の違い
ホームページ作成の費用は、「どの方法で作るか」によって、その構造が全く異なります。
自社の予算や事業計画に合わせて、最適な料金体系を選択することが重要です。



例えば、専門の制作会社に依頼する場合、初期費用は高額ですが、その後の月額費用は保守費のみに抑えられます。
一方、不動産専用のクラウドツールを利用する場合、初期費用は無料か安価な代わりに、月額のシステム利用料が発生します。
WordPressなどを利用した自社制作は、金銭的なコストは最低限ですが、担当者の膨大な時間と労力という、見えないコストが最もかかります。
初期投資を抑えて月々支払うか、最初にまとめて投資するか、自社の経営状況に合わせた賢い選択が求められます。
費用(4)費用を抑えるためのポイント
ホームページの制作費用は、いくつかのポイントを押さえることで、品質を保ちながら賢く抑えることが可能です。
最も重要なのは、サイト制作の目的を明確にし、本当に必要な機能を見極めることです。



「あれもこれも」と要望を詰め込むと、予算はすぐに膨れ上がります。
まずは集客や業務効率化など、絶対に達成したい目標を一つに絞り、最低限の機能でスタートする「スモールスタート」を心がけましょう。
また、国の「IT導入補助金」や「小規模事業者持続化補助金」といった制度を活用することも非常に有効な手段です。
これらの補助金を利用すれば、制作費用の半分から3分の2程度の補助を受けられる場合があります。
活用できる制度がないか、依頼を検討している制作会社に一度相談してみることをお勧めします。
不動産ホームページに必要な機能とは?


この章では、成果を出す不動産ホームページに欠かせない「5つの必須機能」を解説します。
単にデザインが綺麗なだけでは、お客様からの問い合わせには繋がりません。
「物件の探しやすさ」から「会社の信頼性のアピール」まで、ユーザーの行動と心理に基づいた機能を漏れなく搭載することが、集客成功の鍵となります。



これから紹介する機能が自社のサイトに備わっているか、また制作会社への依頼時に要件として伝えられるか、チェックリストとしてご活用ください。
- 機能(1)物件検索・登録システム
- 機能(2)お問い合わせフォームの設置
- 機能(3)スマートフォン対応の表示設計
- 機能(4)会社情報やアクセス情報の掲載
- 機能(5)スタッフ紹介や実績紹介ページ
機能(1)物件検索・登録システム
ユーザーが目的の物件をストレスなく、かつ効率的に見つけ出せる「物件検索システム」は、不動産ホームページの心臓部であり、最も重要な機能です。



サイト訪問者の最大の目的は「物件を探すこと」であり、検索機能が使いにくかったり、絞り込み条件が少なかったりすると、ユーザーは即座にサイトを離脱してしまいます。
エリアや価格といった基本条件はもちろん、「駅徒歩〇分以内」「ペット可」「特定の学校区内」など、顧客ニーズに合わせた詳細な条件で絞り込めるようにすることが、顧客満足度の向上に直結します。
また、スタッフが物件情報を簡単に追加・更新できる管理システム(CMS)の使いやすさも、日々の業務効率を左右する重要な選定ポイントです。
使いやすい検索機能への投資は、質の高い反響を得るための最も効果的な投資と言えるでしょう。
機能(2)お問い合わせフォームの設置



サイトを訪れた見込み客を、実際の来店や契約へとつなげるためには、分かりやすく入力しやすい「お問い合わせフォーム」の設置が不可欠です。
ユーザーが物件に興味を持っても、問い合わせへの道のりが複雑であれば、その熱意は冷めてしまいます。
「問い合わせたい」と思った瞬間に、その行動を後押しできるシンプルな仕組みを用意することが、機会損失を防ぐ上で極めて重要です。
各物件の詳細ページに「この物件について問い合わせる」ボタンを大きく設置するのは基本とし、入力項目は必要最低限に絞り込み、手間を減らす工夫が求められます。
さらに、「来店予約フォーム」や「資料請求フォーム」など、問い合わせのハードルが異なる複数の選択肢を用意することで、様々な温度感の顧客を取り込むことが可能になります。
電話が苦手なユーザーも多いため、Web上で完結できるフォームは必須の機能です。
機能(3)スマートフォン対応の表示設計
現代の物件探しにおいて、スマートフォンでの快適な閲覧体験を提供する「レスポンシブデザイン」は、もはや特別な機能ではなく、必須の基本設計です。
多くのユーザーは、通勤中や外出先といった隙間時間にスマートフォンで物件情報を探します。
その際、文字や画像が小さすぎて指で拡大しないと見られないサイトは、非常に大きなストレスを与え、即座に離脱されてしまいます。
また、Googleもスマホ対応サイトを検索結果で優遇する「モバイルファーストインデックス」を推進しているため、SEO対策の観点からも不可欠です。
物件写真がスワイプで切り替えられ、問い合わせボタンがタップしやすい位置にあるかなど、スマホでの操作性を第一に考えた設計が、機会損失を防ぎ、集客力の最大化に繋がります。
古いホームページのままの会社は特に注意が必要です。
機能(4)会社情報やアクセス情報の掲載
企業の信頼性を示し、来店を促すために、会社の基本情報や店舗へのアクセス方法を分かりやすく掲載した「会社概要ページ」は、必ず設けるべき基本的な機能です。
不動産という高額な商品を扱う以上、顧客は「どんな会社が運営しているのか」を必ず確認します。
運営元が不明瞭なサイトは、それだけで敬遠されてしまいます。



会社の透明性を示すことは、顧客に安心感を与えるための第一歩です。
会社名、所在地、電話番号、免許番号といった基本情報に加え、事業内容や会社の沿革、代表者の挨拶などを掲載すると、より会社の姿勢が伝わります。
特に、店舗の所在地は、Googleマップを埋め込む形式で掲載すると、ユーザーが現在地からのルートをすぐに検索できるため非常に親切で、来店促進に直接的な効果が期待できます。
機能(5)スタッフ紹介や実績紹介ページ
担当者の人柄を伝える「スタッフ紹介」や、顧客からの声を紹介する「お客様の声・実績紹介」ページは、会社の信頼性をさらに高め、競合との差別化を図るための強力な機能です。
不動産選びは、最終的に「どの会社の、誰に任せるか」という点が重要になります。
事前にスタッフの顔や得意分野が分かっていると、顧客は安心して問い合わせや訪問ができます。



また、第三者である既存顧客からの良い評価は、何よりもの説得力を持ちます。
お客様の声は、可能であればお客様の写真や直筆のメッセージを添えると、信頼性が格段に向上します。
「年間成約〇〇件」といった具体的な実績のアピールも有効で、物件情報だけでは伝わらない「会社の魅力」を伝える重要な投資となります。
不動産ホームページ作成のメリット


この章では、不動産会社が自社のホームページを持つことによって得られる具体的な「3つのメリット」について掘り下げて解説します。
ホームページの作成は単なる経費ではなく、会社の未来を支える戦略的な「投資」です。
24時間働き続ける営業マンの役割から、お客様との新たな接点の創出、そして何よりも代えがたい「信頼」の獲得まで、ホームページがビジネスをいかに力強く後押しするのか。



その具体的な利点を理解することで、作成への決意と目的意識がより明確になるでしょう。
- メリット(1)営業活動の自動化・効率化
- メリット(2)オンラインでの顧客接点を強化
- メリット(3)信頼感・安心感を与えられる
メリット(1)営業活動の自動化・効率化
適切に設計されたホームページは、問い合わせ対応や物件案内といった営業活動の一部を自動化し、スタッフの業務を大幅に効率化する強力なツールとなります。



日々の業務では、電話による物件の空き状況の確認や、基本的な質問への回答など、繰り返し発生するタスクに多くの時間が割かれています。
ホームページがこれらの役割を24時間365日代行することで、スタッフはより専門的なコンサルティングや、契約といったコア業務に集中できるようになります。
また、物件管理システムを導入すれば、一つの物件情報を登録するだけで自社サイトとポータルサイトへ一括反映できるため、手作業によるデータ入力の手間とミスを劇的に削減することが可能です。
メリット(2)オンラインでの顧客接点を強化
自社ホームページは、ポータルサイトの制約を受けない自由な情報発信拠点となり、オンライン上での新たな顧客接点を能動的に強化することができます。
大手の物件ポータルサイトは集客力がありますが、掲載できる情報には限りがあり、競合他社の中に埋もれてしまいがちです。
自社サイトであれば、デザインやコンテンツを自由に設計し、独自の魅力を存分に伝えることで、他社との差別化を図り、直接見込み客と繋がることが可能になります。
また、「〇〇エリアの治安情報」といった地域密着のブログ記事を発信すれば、今すぐ物件を探していない潜在顧客にも会社の存在を認知させ、将来の見込み客として育成していくことができます。
メリット(3)信頼感・安心感を与えられる
プロフェッショナルで情報が充実したホームページは、会社の公的な「顔」として機能し、お客様に取引への信頼感と安心感を与える上で決定的な役割を果たします。
不動産という高額な商品を扱う上で、お客様が最も重視するのは「その会社が信頼できるか」という点です。
情報が古かったり、デザインが素人っぽかったりするサイトは、それだけで会社の信頼性を損ない、お客様を不安にさせてしまいます。



しっかり作り込まれたサイトは、企業の誠実な姿勢の表れと受け取られます。
会社の理念や設立からの歴史、代表者のメッセージを掲載することで企業の想いを伝え、資格を持つスタッフの顔写真付きプロフィールを公開すれば、専門性の高さをアピールできます。
お客様から寄せられた感謝の声や、過去の成約事例を具体的に紹介することも、第三者からの客観的な評価として非常に有効です。
不動産ホームページ作成のデメリットと注意点


この章では、ホームページ作成のメリットだけでなく、事前に知っておくべき「デメリットと注意点」についても正直に解説します。
多くのメリットがある一方で、ホームページは「作れば自動で成功する魔法の杖」ではありません。作成・運用には相応のコストや手間がかかります。
これらの現実的な側面を事前に理解し、対策を講じておくことが、後悔しないホームページ作成の第一歩です。



デメリットを知ることで、より戦略的で、地に足の着いた計画を立てられるようになります。
- デメリット(1)初期費用・維持費が発生する
- デメリット(2)コンテンツ更新の手間がかかる
- デメリット(3)ツール・業者選びで差が出る
デメリット(1)初期費用・維持費が発生する
専門的なホームページを作成し、それを維持していくためには、初期費用と月々の運用・維持費という継続的なコストが発生します。
これは、ホームページを持つ上で避けては通れない、最も大きなデメリットと言えます。
ホームページは、会社の資産です。



例えば、営業車を購入すれば本体価格だけでなく、駐車場代やガソリン代、保険料がかかるのと同じように、ホームページも制作費に加え、サーバー代やシステムの保守管理費といったランニングコストが必要不可欠です。
初期費用は、制作方法により数万円から数百万円。
月々の維持費は、サーバー代や保守費用で数千円から数万円程度が相場です。
一見「無料」で作成できるツールもありますが、機能に制限があったり、結局は専門知識を持つ担当者の人件費という「見えないコスト」が発生したりするケースがほとんどです。
ホームページ作成を単なる「経費」ではなく、将来の利益を生む「投資」として捉え、明確な予算を立てることが重要です。
初期費用と維持費を合わせた総額を把握し、費用対効果を冷静に判断する視点を持ちましょう。
デメリット(2)コンテンツ更新の手間がかかる
ホームページは一度作って終わりではなく、その価値を維持・向上させるためには、物件情報やブログといったコンテンツを継続的に更新する「手間」と「時間」がかかります。
何ヶ月も情報が更新されていないホームページは、訪問者に「この会社はきちんと営業しているのだろうか」という不信感を与えてしまいます。
また、新しい情報が追加されないサイトは、Googleからの評価も下がり、検索結果に表示されにくくなります。



新鮮な情報発信こそが、集客力の維持に繋がります。
具体的には、成約済み物件の情報を速やかに更新したり、新しい物件の写真を撮影して登録したりする作業が日常的に発生します。
さらに、集客効果を高めるためには、「〇〇エリアの住みやすさレポート」のような地域情報をテーマにしたブログ記事などを定期的に作成・公開する努力も求められます。
ホームページの作成を計画する段階で、「誰が、どのくらいの頻度で、何を更新するのか」という運用体制を具体的に決めておくことが極めて重要です。
社内での対応が難しい場合は、コンテンツ更新の代行まで含めたサポートプランを制作会社に相談しましょう。
デメリット(3)ツール・業者選びで差が出る
ホームページ作成の成否は、依頼する制作会社や利用するツールの質に大きく左右されます。
パートナー選びの失敗は、時間とお金を無駄にし、全く成果が出ないという最悪の結果を招く最大のデメリットです。
制作会社と一口に言っても、不動産業界の専門知識や集客ノウハウのレベルは千差万別です。



業界への理解が浅い業者に依頼してしまうと、デザインは綺麗でも反響に繋がらない、物件管理がしにくいといった問題が発生しがちです。
例えば、初期費用が格安な業者に依頼した結果、サポート体制が不十分だったり、契約上サイトの所有権が自社になく、業者変更ができなかったりするトラブルが実際にあります。
また、安価なテンプレートツールを選んだ場合、将来的に機能を追加したくても、システムの制約で対応できないといった事態も考えられます。
費用だけで安易に業者を決めず、不動産業界での実績が豊富か、自社の要望を親身にヒアリングしてくれるか、契約内容は明確か、といった点を多角的に評価しましょう。
信頼できるパートナー選びこそが、ホームページ作成を成功させる最も重要な要素です。
無料で不動産ホームページは作れるのか?


この章では、「不動産会社のホームページは無料で作成できるのか?」という、多くの経営者様が抱く疑問にお答えします。
「ホームページ 作成 無料」というキーワードは非常に魅力的ですが、その実態と、ビジネスで利用する上での注意点を正しく理解することが不可欠です。
無料作成ツールの具体的な活用法から、そのメリット、そして事業用としては致命的になりかねないデメリットや機能制限までを詳しく解説します。
この章を読めば、「無料」という言葉の裏にある本当の意味を理解し、自社にとって賢い選択ができるようになります。
- ポイント(1)無料作成ツールの活用方法
- ポイント(2)無料ツールのメリットとは?
- ポイント(3)無料ツールのデメリットとは?
- ポイント(4)無料プランの機能制限に注意
ポイント(1)無料作成ツールの活用方法
無料でホームページを作成する場合、一般的にはWixやペライチといった、専門知識がなくてもサイトが作れる「ホームページビルダー」と呼ばれるサービスを利用します。
これらのサービスは、あらかじめ用意されたデザインテンプレートと、マウス操作で直感的にパーツを配置できる編集機能を提供しています。
そのため、HTMLやCSSといった専門的なWeb制作の知識がない方でも、ブログを更新するような感覚で簡単なページを作成することが可能です。
具体的な手順としては、サービスに登録後、好みのテンプレートを選び、そこにご自身の会社の情報や物件の画像・テキスト情報を手作業で入力していく形になります。
ただし、不動産専用ではないため、物件検索システムなどはなく、物件紹介は1ページずつ手動で作成・更新する必要があります。
ポイント(2)無料ツールのメリットとは?
無料作成ツールを利用する最大のメリットは、名前の通り「金銭的な初期費用が一切かからない」という一点に尽きます。
通常、ホームページ制作を専門業者に依頼すれば数十万円以上の初期費用がかかりますが、この費用をゼロにできるのは、特に創業間もない会社や、広告宣伝費に全く予算を割けない状況の事業者にとっては、非常に大きな魅力となります。



制作会社との打ち合わせや契約といった煩雑なプロセスも不要です。
思い立ったその日にアカウントを登録し、すぐにでもホームページ作成に取り掛かることができます。
Webの知識がなくても、サービス側が用意した枠組みの中で作業を進められるため、とにかく手軽に、最低限のネット上の名刺代わりが欲しい、というニーズには応えることができます。
ポイント(3)無料ツールのデメリットとは?
無料ツールには、ビジネスで利用するには致命的となる多くのデメリットが存在し、「安かろう悪かろう」という結果になりかねない大きなリスクを伴います。
無料サービスは、運営会社の広告を表示したり、有料プランへ誘導したりすることで収益を得ています。
そのため、無料プランには意図的に多くの制約が課せられており、企業の信頼性や本格的な集客活動を阻害する要因が含まれています。
具体的には、①自社サイトに他社の広告が表示される、②URLが独自ドメインでなく信頼性が低い、③デザインの自由度が低く他社と差別化できない、④SEOに弱く検索しても見つけてもらえない、といった点が挙げられます。



目先の費用は無料でも、ビジネスチャンスの損失という、より大きな代償を払う可能性があります。
ポイント(4)無料プランの機能制限に注意
無料作成ツールは、特に不動産ホームページに必須の機能において、致命的な制限があるため注意が必要です。
不動産サイトの運営には、多数の物件写真を掲載するための大容量のデータ保存領域や、専門的な検索機能が不可欠です。
しかし、無料の汎用ツールは、これらの不動産業特有のニーズを全く想定して作られていません。
例えば、無料プランではデータ保存容量が非常に少なく、高画質な物件写真を数十枚アップロードしただけで上限に達してしまうことがあります。



また、当然ながら物件管理システムやポータルサイトとの連動機能は存在しません。
さらに、サイトに問題が発生した際に、電話やメールでのサポートが受けられないケースがほとんどで、すべて自己責任での対応となります。
これらの機能制限は事業の足かせとなるため、有料プランの選択が賢明です。
不動産ホームページ業者を選ぶ際のポイント


この章では、ホームページ作成の成否を分ける最も重要な要素、「制作会社・業者の選び方」について、具体的な5つのチェックポイントを解説します。
「どこに依頼すればいいか分からない」「高額な費用を払って失敗したくない」という不安は、すべての経営者様が抱える共通の悩みです。
この章で紹介するポイントに沿って業者を比較検討することで、自社の目的を理解し、予算内で最高の成果を出してくれる、信頼できるパートナーを見極めることができるようになります。
- 選び方(1)不動産業界の制作実績を確認
- 選び方(2)提供機能やサポート体制を比較
- 選び方(3)見積もり内容が明確かどうか
- 選び方(4)担当者との相性をチェックする
- 選び方(5)デザイン事例を事前に確認する
選び方(1)不動産業界の制作実績を確認



制作業者を選ぶ上で最も重要なのは、「不動産業界に特化したホームページの制作実績が豊富にあるか」を確認することです。
不動産のホームページには、物件検索システムやポータルサイト連携など、業界特有の専門的な機能が求められます。
また、広告表示に関する法規制など、専門知識も必要です。
業界経験のない業者に依頼すると、見た目は良くても集客に繋がらない、使い勝手の悪いサイトになるリスクが高まります。
業者の公式サイトで「制作実績」のページを必ず確認し、実際にリンク先の不動産会社のサイトを訪れて、デザインや使い心地を体感することが大切です。
「過去に手掛けたサイトで、どのような集客効果がありましたか?」といった具体的な質問を投げかけてみるのも有効な手段です。
その業者が持つ業界特有のノウハウこそが、あなたの会社の成功を左右します。
選び方(2)提供機能やサポート体制を比較
サイト公開後の運用を見据え、自社の業務に必要な機能が搭載されているか、そしてトラブル発生時に迅速に対応してくれるサポート体制が整っているかを比較検討することが重要です。



ホームページは作って終わりではなく、運用していく中で「こんな機能が欲しかった」「急にサイトが表示されなくなった」といった問題が必ず発生します。
その際に、必要な機能が不足していたり、サポートが手薄だったりすると、サイトが事業の足かせになりかねません。
機能面では、「物件データをCSVで一括登録できるか」「スマホからでも簡単に情報を更新できるか」などをチェックします。
サポート面では、「対応してくれる時間帯は平日だけか」「電話でのサポートはあるか」などを契約前に書面で確認することが不可欠です。
長期的な運用まで見据えた機能の充実度と、安心できるサポート体制の有無を必ず確認しましょう。
選び方(3)見積もり内容が明確かどうか
信頼できる業者は、「ホームページ制作一式」といった大雑把なものではなく、何にいくらかかるのかが一目で分かる、詳細で透明性の高い見積書を提示します。
不透明な見積もりは、後から「これは別途費用です」といった追加請求が発生するトラブルの元です。
また、作業内容が不明確なため、他社との比較検討も正しく行えません。
見積もりの明確さは、その業者の誠実さや仕事の丁寧さを測るバロメーターとなります。
良い見積もりには、「企画・ディレクション費」「デザイン費」「システム開発費」といった項目ごとに、単価と数量が明記されています。



もし不明な項目があれば、遠慮なく質問し、納得できるまで説明を求めましょう。
その際の回答が曖昧な業者は注意が必要です。
総額の安さだけで判断せず、自社の要望がきちんと反映された、詳細で分かりやすい見積もりを提出してくれる業者を選びましょう。
選び方(4)担当者との相性をチェックする
ホームページ制作は業者と二人三脚で進める長期的なプロジェクトのため、会社の看板だけでなく、実際に窓口となる「担当者」との相性やコミュニケーションのしやすさも極めて重要です。
Webに詳しくないこちらの悩みを親身になって聞いてくれるか、専門用語を分かりやすく説明してくれるか、レスポンスは迅速か、といった担当者の姿勢が、プロジェクトの進行速度と満足度を大きく左右します。



相性が悪いと、要望がうまく伝わらず、意図と違うサイトが出来上がってしまうことさえあります。
最初の問い合わせやヒアリングの段階が、担当者を見極める絶好の機会です。
こちらの話を遮って一方的に話を進める担当者は避けた方が賢明です。
「この人になら安心して任せられる」と直感的に思えるかどうかも、意外と重要な判断基準となります。
選び方(5)デザイン事例を事前に確認する
自社のブランドイメージやターゲット顧客に合ったホームページを実現するために、業者の過去のデザイン事例を事前に確認し、そのデザインの方向性が自社の理想と合致しているかを見極めることが重要です。



ホームページのデザインは、会社の「顔」であり、ユーザーに与える第一印象を決定づけます。
業者によって得意なデザインのテイスト(例えば、高級感のあるデザイン、温かみのあるデザインなど)は異なります。
自社のイメージと異なるデザインを押し付けられても、満足のいく結果にはなりません。
業者の制作実績を見て、デザインの幅広さを確認しましょう。
「こういう雰囲気のサイトにしたい」という参考サイトをいくつか提示し、そのイメージを正確に汲み取ってくれるか、具体的なデザイン案に落とし込む提案力があるか、といった点を確認します。
デザインは単なる好みだけでなく、集客戦略にも関わる重要な要素です。
契約前に確認したい落とし穴と対策
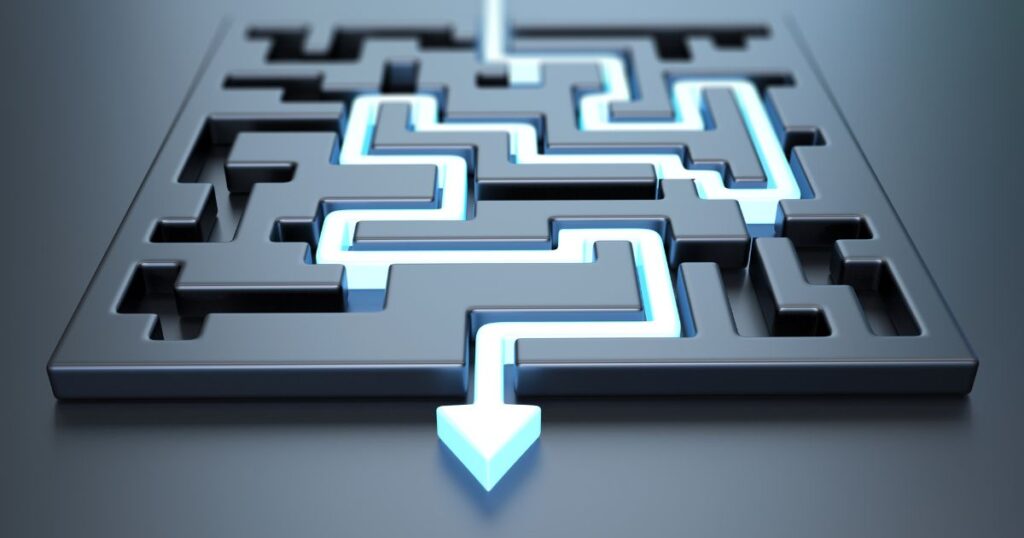
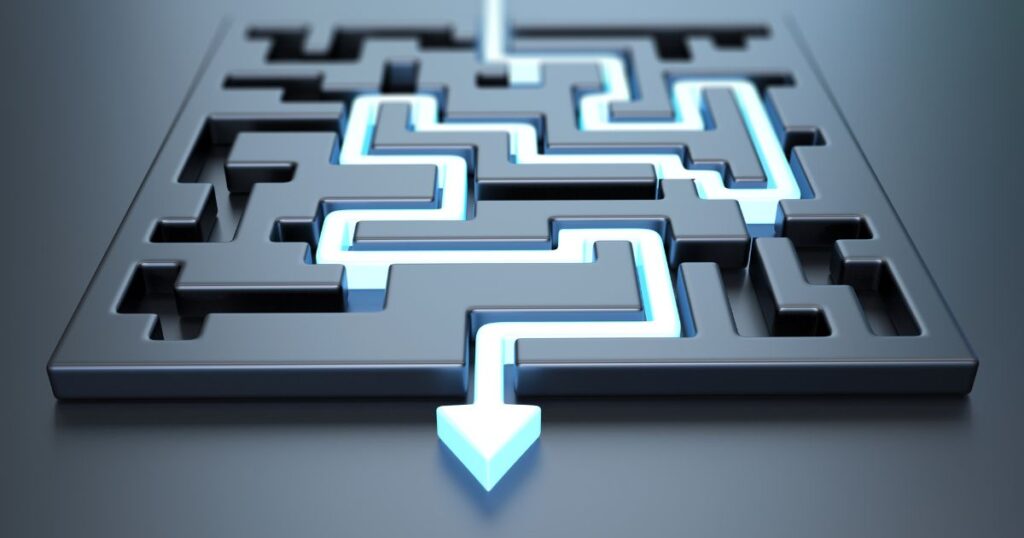
この章では、ホームページ制作の契約直前に必ず確認すべき「3つの落とし穴」と、その対策について具体的に解説します。
素晴らしいホームページが完成間近でも、契約内容の確認を怠ると、後々「こんなはずではなかった」という深刻なトラブルに発展しかねません。
サイトの所有権、予期せぬ追加費用、そしてサポートや解約の条件。



これらの重要ポイントを事前にしっかりと押さえておくことが、安心して制作を任せ、長期的に良好な関係を築くための最大の防御策となります。
- 落とし穴(1)サイトの所有権・著作権の扱い
- 落とし穴(2)修正範囲と追加費用の条件
- 落とし穴(3)サポート体制と解約条件の確認
落とし穴(1)サイトの所有権・著作権の扱い
契約時に最も重要かつ絶対に見逃してはならないのが、「完成したホームページの所有権(サーバー上のデータやドメインを含む)が、自社に帰属する」という条項の確認です。
万が一、所有権が制作会社側にある「リース契約」のような形式だと、自社のホームページであるにも関わらず、自由に修正したり、他の業者に管理を移したりすることができません。



結果的に、その業者に依存し続けるしかなくなり、非常に不利な立場に置かれてしまいます。
契約書に「納品後、サイトデータ一式の所有権は発注者に移管する」といった文言が明記されているかを確認します。
特に、サイトの住所にあたる「ドメイン」が、自社の名義で取得・管理されているかは必ずチェックすべき重要項目です。
ホームページは会社の資産です。その資産の所有権が自社にあることを、契約書上で明確にしましょう。
落とし穴(2)修正範囲と追加費用の条件
予期せぬ予算オーバーを防ぐため、「どこまでの修正が無料で、どこからが追加費用になるのか」という線引きを、契約前に具体的かつ明確に定めておく必要があります。
「軽微な修正は無料」といった曖昧な表現は、トラブルの温床です。



こちらが「軽微」だと思った修正でも、業者側から「仕様変更にあたるため追加費用です」と請求されるケースは後を絶ちません。
この認識のズレが、不信感や予算超過の原因となります。
例えば、「デザインの修正は2回まで無料」「公開後1ヶ月以内のテキスト修正は無料対応」のように、回数や期間を具体的に定めてもらうのが有効です。
また、追加費用が発生する場合の料金体系も、事前に確認しておくことで、安心して修正を依頼できます。修正に関するルールは、口約束ではなく、必ず契約書に明記してもらいましょう。
落とし穴(3)サポート体制と解約条件の確認
サイト公開後の長期的な運用を見据え、具体的なサポート内容と、万が一の場合の「契約期間」や「解約条件」を事前に確認しておくことが、リスク管理において非常に重要です。



ホームページは、公開後もサーバーやシステムの保守・管理が続きます。
その月額費用の対価として、どのようなサポートが受けられるのかが不明確だと、いざという時に助けてもらえません。
また、不当に長い契約期間や高額な違約金は、業者変更の自由を奪う「縛り」となり得ます。「最低契約期間は1年か2年か」「解約の申し出は何ヶ月前までに行う必要があるか」「途中解約した場合の違約金の有無」といった解約に関する条項は、隅々まで目を通す必要があります。
特に「初期費用無料」を謳うプランは、長期の契約期間で費用を回収するモデルが多いため、解約条件の確認は必須です。
不動産ホームページ運用で気をつけるべきこと


この章では、ホームページが無事完成し、公開された「後」に気をつけるべき、重要な5つの運用上の注意点を解説します。
ホームページは作って終わりではなく、むしろ公開してからが本当のスタートです。
法令遵守から日々の情報更新、そして見落としがちな技術的な管理まで、適切な運用を継続することが、ホームページを真の「資産」へと育てていきます。



ここで紹介するポイントを実践することで、サイトの価値を維持・向上させ、安定した集客を実現することができます。
- 注意点(1)宅建業法など法令の遵守
- 注意点(2)物件情報の正確性と定期的な更新
- 注意点(3)ドメイン・サーバーの管理体制
- 注意点(4)SEO対策と地域集客戦略の設計
- 注意点(5)セキュリティ対策の強化
注意点(1)宅建業法など法令の遵守
不動産ホームページを運用する上で、宅地建物取引業法や景品表示法で定められた広告に関するルールを遵守することは、絶対的な義務です。
これらの法律に違反した場合、行政指導や罰金、最悪の場合は営業停止といった厳しい罰則が科される可能性があります。



特に、意図せずとも結果的にユーザーを欺くことになった「おとり広告」に対する監視は年々厳しくなっており、「知らなかった」では済まされません。
具体的には、会社名や免許番号の明記、物件の所在地・価格・面積の正確な表示、取引態様(仲介・売主など)の別、そして情報の更新日を必ず記載する必要があります。
すでに契約済みの物件を掲載し続けることは、おとり広告と見なされる典型的な例です。
企業の信頼を守り、健全な事業を継続するために、広告に関する法令を常に意識したサイト運用を徹底しましょう。
注意点(2)物件情報の正確性と定期的な更新
お客様からの信頼を維持し、おとり広告のリスクを避けるため、掲載している物件情報の「正確性」を保ち、その状況を「定期的」に更新し続けることが極めて重要です。
お客様がサイトを見て問い合わせた物件が、実際には「すでに契約済みだった」という事態は、顧客満足度を著しく低下させ、会社の信用を大きく損ないます。
情報の鮮度が、そのまま会社の信頼性に直結します。
物件の価格が変更された場合や、申し込みが入って募集を停止した場合など、物件の状況に変化があれば、速やかにホームページ上の情報を修正・更新する社内ルールを確立する必要があります。
物件管理システム(CMS)を使えば、管理画面から簡単に情報を変更でき、手間を大幅に削減できます。
情報の最終更新日を各物件ページに表示することも、誠実さを示す上で有効です。
注意点(3)ドメイン・サーバーの管理体制
サイトの「住所」であるドメインと、「土地」であるサーバーの管理を徹底し、更新忘れや技術トラブルによってサイトがある日突然消えてしまう事態を防がなくてはなりません。
ドメインやサーバーは、通常1年ごとの契約更新が必要です。
この更新手続きを忘れてしまうと、サイトが表示されなくなり、最悪の場合、第三者にドメインを取得されてしまうリスクもあります。



これはビジネスにとって計り知れない損失です。
ドメインとサーバーの管理を制作会社に委託しているのか、自社で行っているのか、その管理体制を明確に把握しておく必要があります。
特に、誰が更新手続きの責任者で、いつ更新日が来るのかをリマインダーに設定するなどして管理しましょう。
サイトの技術的な基盤であるドメインとサーバーの管理は、決して疎かにしてはいけない重要事項です。
注意点(4)SEO対策と地域集客戦略の設計



作成したホームページを「見つけてもらう」ためには、Googleなどの検索エンジンで上位に表示させるための「SEO対策」、特に自社の強みを活かした地域集客戦略が不可欠です。
どれだけ素晴らしいホームページを作っても、お客様の目に触れなければ存在しないのと同じです。
特に不動産を探すユーザーの多くは、「〇〇市 賃貸」のように「地域名+キーワード」で検索するため、この地域検索(ローカルSEO)を制することが集客の鍵となります。
例えば、「〇〇駅周辺の住みやすさ」や「△△小学校区の物件特集」といった、地域に密着した専門的な内容のブログ記事を定期的に公開することが有効です。
こうしたコンテンツは、大手ポータルサイトにはない独自の価値を提供し、地域で物件を探している見込みの濃いユーザーを引きつけることに繋がります。
注意点(5)セキュリティ対策の強化
不正アクセスや情報漏洩といったサイバー攻撃からサイトと顧客情報を守るため、継続的なセキュリティ対策の強化が必須となります。
万が一、サイトが改ざんされたり、お問い合わせフォームから得た顧客情報が流出したりすれば、会社の信用は失墜し、事業の継続に深刻な影響を及ぼします。
セキュリティのリスク管理は、現代の企業にとって重要な経営課題の一つです。
具体的な対策として、サイトの基盤となっているシステム(CMSなど)やプラグインを常に最新の状態に保ち、脆弱性をなくすことが基本です。
また、管理画面へのログインパスワードを複雑なものに設定し、定期的に変更することも重要です。



サイト全体の通信を暗号化する「SSL化」も、今や必須の対策です。
セキュリティ対策は専門的な知識を要するため、制作会社の保守管理プランに内容が含まれているかを確認しましょう。
まとめ


不動産ホームページの作成には、費用や専門知識、業者選びなど多くの不安が伴います。



本記事では、そうした悩みを解消するため、目的設定から費用相場、信頼できる制作会社の選び方、契約・運用の注意点まで、成果を出すために必要な全知識を解説しました。
最も重要なのは、明確な目的意識を持ち、価格だけで判断せず、長期的な視点で信頼できるパートナーを選ぶことです。
この記事で得た知識を武器に、ホームページを「会社の資産」として育て、ポータルサイトに頼らない安定した集客を実現する第一歩を踏み出しましょう。