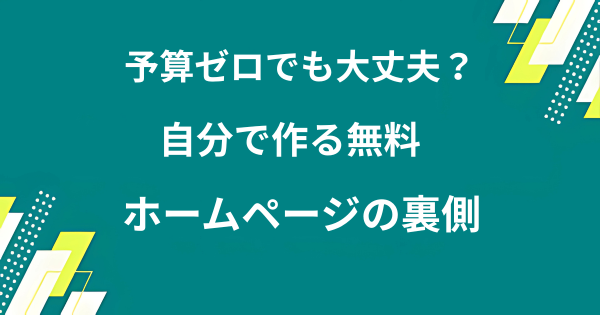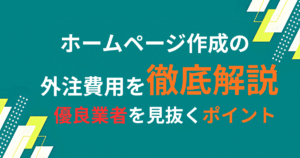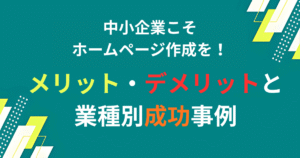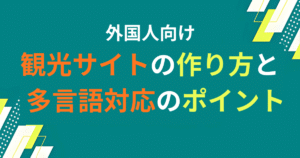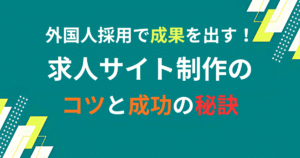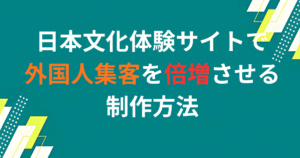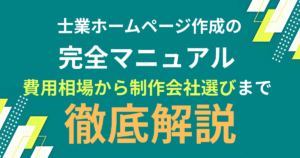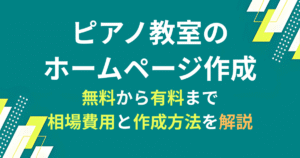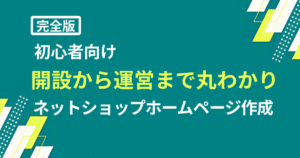「ホームページを自分で作成したいけど、時間も知識もないし、費用も抑えたい…」「無料ツールは気になるけど、安っぽいデザインにならないか不安…」そんな悩みを抱えていませんか?
この記事を読めば、専門知識がなくても、時間とコストを最小限に抑えつつプロ品質のホームページを作る具体的な方法がわかります。
主要作成ツールの比較から、無料と有料プランの賢い選び方、初心者でも安心のデザイン・SEOの基本、そして無理なく運用を続けるヒントまで丁寧に解説。



あなたも理想のホームページを自分の手で実現し、ビジネスを力強く加速させましょう。
ホームページを自分で作成するにはどんな方法がある?


この章では、専門知識がない初心者の方が「自分でホームページを作成する」ための、代表的な4つの方法を紹介します。
この記事を読むことで、それぞれの方法のメリット・デメリット、必要な時間や費用感を理解し、ご自身の目的やスキルに最適な選択肢を見つけることができます。
ホームページを自分で作成する方法には、主に以下の内容があります。
- 作成ツール:専門知識不要で、パワーポイントのような直感的な操作で作成する方法。
- WordPress:ブログから本格的なビジネスサイトまで作れる、世界で最も人気のあるシステム。
- HTML/CSS:デザインや機能をゼロから作り上げる、完全オリジナルのプロ向けの方法。
- スマホアプリ:PCを使わず、スマホだけでホームページを作成・更新する方法。
方法(1)作成ツールなら初心者も安心
専門的な知識がゼロでも、まるでパワーポイントやワープロソフトを扱うような直感的な操作で、本格的なホームページを「自分で作成」できるのが、この方法の最大の魅力です。
Wix(ウィックス)やJimdo(ジンドゥー)に代表されるホームページ作成ツールは、あらかじめプロのデザイナーが制作した高品質なデザインテンプレートを数多く用意しています。
気に入ったテンプレートを選び、あとは文章や写真をご自身のものに差し替えていくだけで、驚くほど簡単に見栄えの良いWebサイトが完成します。
サーバーの契約や管理といった専門的な作業は一切不要で、アカウントを登録すればすぐに始められるため、とにかく早く、手間をかけずに公開したい初心者の方に最適な選択肢と言えるでしょう。
多くのツールには「無料」プランがありますが、ビジネスで活用するなら注意が必要です。
無料プランではサイトに広告が表示されたり、URLにサービス名(例: 〇〇.wixsite.com)が入ってしまったりするため、信頼性が求められる企業のホームページには不向きなケースが多いです。



まずは無料プランで操作感を試し、本格的に運用するタイミングで広告の出ない有料プラン(月額1,000円程度から)へ切り替えるのが、失敗のない賢いステップです。
方法(2)WordPressで本格構築する
将来的にブログやコラムで本格的に集客をしたい、あるいは細部までこだわったオリジナルのサイトを育てていきたい、と考えるなら「WordPress(ワードプレス)」が最も強力な選択肢となります。
世界中のWebサイトの約4割がWordPressで作られていると言われるほど、圧倒的な人気と実績を誇るシステムです。
この方法では、自分でレンタルサーバー(エックスサーバーなど)と独自ドメインを契約し、そこにWordPressをインストールしてサイトを構築します。



最初の設定に少し学習が必要ですが、一度慣れてしまえば、その後の自由度は他のツールを圧倒します。
デザインのテンプレートである「テーマ」や、機能を追加する「プラグイン」が世界中で開発されており、そのほとんどが無料で利用できるため、本格的なSEO対策機能やお問い合わせフォーム、ネットショップ機能まで、思い通りのサイトにカスタマイズしていくことが可能です。
月々の費用もサーバー代の500円~1,000円程度で済むことが多く、長期的に見れば非常にコストパフォーマンスの高い方法と言えます。



操作に慣れるまで少し「時間」がかかる点はデメリットですが、使い方に関する情報はインターネット上に豊富にあるため、やる気さえあれば初心者でも十分に乗り越えることができます。
方法(3)HTML/CSSで完全オリジナル
ホームページを「自分で作成」する方法の中で、最も専門的かつ原始的な方法が、HTMLやCSSといった専門言語を使ってゼロからコードを記述していくやり方です。
この方法は、既存のテンプレートやツールに一切縛られることなく、デザインやレイアウト、機能のすべてを完全にオリジナルで作り上げることができるため、世界に一つだけのWebサイトを構築できます。
しかし、そのためにはHTML(文章の構造を作る言語)やCSS(デザインを装飾する言語)、さらにはJavaScript(動きを加える言語)といった複数のプログラミング言語を深く理解し、自在に操るスキルが必須となります。
例えば、テキストを見出しにしたり、ボタンを一つ配置したりするだけでも、専門的なコードを正確に記述する必要があり、習得には膨大な学習時間と労力がかかります。
Web制作のプロを目指すのであれば避けては通れない道ですが、ビジネスのオーナーや担当者が自分でホームページを持つための選択肢としては、費用対効果や時間の観点から見て現実的ではありません。



この方法は、むしろ後述の作成ツールやWordPressがいかに効率的で、初心者に優しい仕組みであるかを理解するための比較対象として捉えていただくと良いでしょう。
方法(4)スマホだけでどこまで作れる?
「パソコンを持っていない」「PC作業は苦手…」という方でも、諦める必要はまったくありません。
現代では、スマートフォン一つでホームページを作成し、日々の運用を行うことが十分に可能です。
WixやJimdoといった人気の作成ツールは、PC版に引けを取らないほど高機能なスマホアプリを提供しています。
これらのアプリを使えば、テンプレートの選択からテキストの入力、スマホで撮影した写真のアップロードまで、すべて指先だけの直感的な操作で完了させることができます。
例えば、飲食店の店主が、その日のランチメニューの写真を厨房で撮影し、すぐにトップページに掲載する。
フリーランスの方が、移動中の電車内でお客様の声をまとめたブログ記事を下書きする、といったスピーディーな情報発信が実現できます。
ただし、万能というわけではありません。
サイト全体の構成を考えたり、複数の画像やテキストをミリ単位で調整したりといった精密な作業は、やはり画面の大きいPCの方が効率的です。
日常のちょっとした更新はスマホで手軽に行い、デザインの大幅な変更や新しいページの追加など、腰を据えて作業したい時だけPCを使う、というハイブリッドな使い方が、無理なく、そして賢くホームページを育てていくための秘訣です。
自分でホームページを作成するメリット


この章では、専門のWeb制作会社に依頼するのではなく、「自分で」ホームページを作成し、運用することの大きなメリットを4つの視点から紹介します。
「大変そう…」というイメージがあるかもしれませんが、自分で作るからこそ得られる、コスト面だけではない長期的な価値を知ることで、ホームページ作成へのモチベーションがきっと高まるはずです。
自分でホームページを作成するメリットには、主に以下の内容があります。
- コスト削減:制作会社に依頼する際に発生する高額な費用を大幅にカットできる。
- スキル習得:サイトを運用する中で、Webマーケティングに関する実践的な知識が身につく。
- 自由度の高さ:ビジネスの成長に合わせて、デザインや機能をいつでも自由に変更・追加できる。
- 更新の速さ:キャンペーン情報などを、業者を介さず、思い立った瞬間に自分で発信できる。
メリット(1)制作・運用コストを大幅削減
ホームページを自分で作成する最大のメリットは、なんといっても制作と運用にかかる費用を劇的に抑えられる点です。
Web制作会社に依頼すると、簡単なサイトでも数十万円、デザインや機能にこだわれば百万円以上の初期費用が発生することも珍しくありません。
例えばWordPress(ワードプレス)で自作すれば、必要な費用はレンタルサーバー代と独自ドメイン代で、月々のランニングコストは1,000円程度から始めることが可能です。
Wix(ウィックス)やJimdo(ジンドゥー)といったホームページ作成ツールを使っても、広告の出ない有料プランが月額数千円から用意されており、圧倒的に低コストでスタートできます。
もちろん、そのためには自分で作業する「時間」というコストはかかりますが、事業の運転資金を圧迫せずにオンラインの拠点を構えられるのは、特に予算の限られる個人事業主や小規模ビジネスにとって計り知れないメリットです。



削減できた費用を広告宣伝や新たな設備投資に回すことで、ビジネス全体の成長を力強く後押しすることができるでしょう。
メリット(2)ウェブ知識・技術が身につく
自分でホームページを作成し、運用していく過程は、お金には代えがたい「一生モノのスキル」を習得する絶好の機会となります。
最初は手探りでも、サイトの構成を考え、訪問者の心に響く文章を書き、どうすればもっと見てもらえるか試行錯誤するうちに、Webマーケティングの基本的な知識や考え方が自然と身についていきます。
例えば、「どんなキーワードで検索するお客様に来てほしいか」を考えればSEOの基礎が、「どのページがよく読まれているか」をアクセス解析ツールで確認すればデータに基づいた改善策を考える力が養われます。



簡単なトラブルを自力で解決した経験は、自信とともにより深い技術理解へと繋がるでしょう。
こうしたスキルは、ホームページ運用だけでなく、SNSでの情報発信やネット広告の出稿、メールマガジンの作成など、あらゆるオンラインでのビジネス活動に必ず活きてきます。
たとえ将来、サイト制作を外部のプロに依頼する機会が訪れたとしても、基本的な知識があることで的確な要望を伝えられるようになり、より良いパートナーシップを築き、望んだ通りの成果を得ることができるのです。
メリット(3)デザイン・機能を自由に実現
ビジネスは生き物のように日々変化し、成長していくものです。
その変化に合わせて、ホームページのデザインや機能をいつでも、費用をかけずに、自分の手で自由自在に進化させられる点は、自作ならではの大きな強みです。
Web制作会社に依頼している場合、「このボタンの色を変えたい」「新しいサービスページを追加したい」といった細かな修正や変更のたびに、連絡を取り、見積もりを取り、作業を待つという手間と時間、そして追加費用が発生します。
しかし、自分でサイトを管理していれば、管理画面から思い立ったその時に、自分の手で思い通りにカスタマイズすることが可能です。
例えばWordPressなら、季節やキャンペーンに合わせてサイト全体のデザインテーマを気軽に変更したり、「ネットショップを始めたい」と思ったらECサイト化のプラグインを追加してすぐに販売を開始したりできます。
Wixなどの作成ツールでも、豊富なアプリを追加することで予約機能や問い合わせフォームなどを簡単に導入可能です。



「まずは小さくスタートして、事業の成長に合わせてサイトも育てていきたい」という柔軟な運用が実現できるため、常にビジネスの現状に最適化されたホームページを保つことができるのです。
メリット(4)情報をスピーディーに更新



ビジネスの世界では、情報の「鮮度」がチャンスを掴むための鍵となります。
自分でホームページを管理していれば、キャンペーンのお知らせや新商品の案内、ブログ記事などを、外部の業者を介さず、まさに「思い立ったその瞬間」に自分で世界中に発信できます。
この圧倒的なスピード感は、ビジネスを加速させる強力な武器です。
例えば、「テレビで紹介されました!」といった旬なニュースを放送直後にトップページに掲載したり、お客様からよくある質問とその回答をすぐにブログ記事として公開したりすることで、ユーザーの関心を強く引きつけ、信頼を獲得することができます。
Web制作会社に更新を依頼した場合、連絡から公開までに数日かかることもあり、その間にビジネスチャンスを逃してしまうかもしれません。
特に、多くの作成ツールには優れたスマホアプリが用意されており、外出先や店舗からでも、スマートフォン一つで手軽に更新作業が可能です。
常にサイトが「生きている」という活気ある状態を保つことは、訪問者に安心感を与えるだけでなく、定期的に新しい情報を評価する検索エンジン対策(SEO)の観点からも非常に有効な手段と言えるでしょう。
自分でホームページを作成するデメリット


この章では、自分でホームページを作成する際に直面する可能性のある、現実的なデメリットや注意点を5つの視点から正直に解説します。
メリットだけでなく、こうした課題を事前に知っておくことが、途中で挫折しないための最大の秘訣です。対策も合わせて紹介しますので、ぜひ前向きな気持ちで読み進めてください。
自分でホームページを作成するデメリットには、主に以下の内容があります。
- 時間と手間:本業の合間に作業するため、想像以上に完成までの時間がかかる。
- 知識の習得:ツールの操作だけでなく、トラブル対応のためにある程度の専門知識が必要になる。
- デザイン品質:テンプレートを使っても、プロの作品と比べると「素人っぽさ」が出てしまう可能性がある。
- セキュリティ:サイトの安全を守る対策は、基本的にすべて自己責任となる。
- 集客(SEO):ホームページは作って終わりではなく、集客のためには別途、継続的な努力が必要。
デメリット(1)完成までに時間と手間がかかる
Web制作会社にホームページ制作を依頼する場合と比べて、自分で作成する際には、どうしても完成までに多くの「時間」と手間がかかることを理解しておく必要があります。
サイト全体の構成を考え、各ページに掲載する文章を書き、ビジネスのイメージに合った写真や画像を用意し、ツールの操作を覚えながらデザインを調整する。
これら全ての作業を、本業の合間に自分一人で行うのは、想像以上に大変な作業です。
特にWeb制作の経験がない初心者の方であれば、一つひとつの手順を調べながら進めることになるため、簡単なホームページであっても公開までに数ヶ月を要することも決して珍しくありません。
例えば、WordPressでサイトを構築する場合、レンタルサーバーの契約からドメインの設定、WordPressのインストール、そして無数のテーマやプラグインの中から最適なものを選ぶといった準備段階だけでも、相応の作業時間が必要です。



対策としては、最初から完璧を目指さないことです。
まずは会社概要やサービス紹介、お問い合わせフォームといった最低限のページ構成でスピーディーに公開し、後から少しずつ内容を充実させていく方法がおすすめです。
デメリット(2)専門知識の習得が不可欠



最近のホームページ作成ツールは非常に優秀で、専門知識がなくても基本的なサイトを公開することは可能です。
しかし、運用中に発生するトラブルに対応したり、テンプレートの範囲を超えて思い通りのカスタマイズを実現したりするためには、ある程度のWeb関連知識の学習がどうしても必要になります。
ホームページは、ドメイン、サーバー、CMS、HTMLといった様々な技術が複雑に絡み合って動いています。
普段はその仕組みを意識する必要はありませんが、例えば「サイトが正しく表示されない」「フォームからのメールが届かない」といった問題が発生した際には、その裏側にある仕組みの基本的な理解が解決の糸口となるケースが少なくありません。
また、本格的なSEO対策や集客を考えるのであれば、Google Analyticsの数値を読み解き、Webマーケティングの仮説を立てて改善していくスキルも求められます。
もちろん、プログラミング言語を完璧に習得する必要はありませんが、わからない専門用語が出てきた時に、自分で調べて解決しようとする学習意欲は不可欠です。
このプロセスを通じて得られる知識や経験は、自身のスキルアップという大きなメリットにも繋がる、と前向きに捉えることが大切です。
デメリット(3)デザイン品質に限界が生じる
多くのホームページ作成ツールには、プロがデザインした高品質なテンプレートが豊富に用意されています。
しかし、Webデザインの知識がないまま安易にカスタマイズを進めてしまうと、全体の統一感がなくなり、意図せず「素人っぽい」印象のサイトになってしまう可能性があります。
プロのデザイナーは、余白の取り方、文字の大きさや書体、配色のバランスといったデザインの基本原則を緻密に計算して、情報が伝わりやすいサイトを構築しています。
こうした知識がないまま、個人の好みだけでレイアウトや色を大きく変更すると、全体の調和が崩れ、訪問者にとって見にくく、使いにくいサイトになってしまいがちです。
例えば、目立たせたいという思いから多くの色を使いすぎて、かえってどこが重要か分からないページになる。
情報を詰め込みすぎて余白がなく、窮屈で読みにくい印象を与える。
解像度の低いスマートフォンで撮った写真をそのまま使い、サイト全体の品質を下げてしまう、といったケースはよく見られます。
デザインに自信がない場合は、テンプレートの基本的な構造や配色はなるべく崩さず、使用する写真やイラストの品質に徹底的にこだわるのが、失敗を避ける最も効果的な方法です。
デメリット(4)セキュリティ対策は自己責任
自分でホームページを管理するということは、そのサイトの安全を維持するためのセキュリティ対策も、すべて自己責任で行う必要があるということを意味します。
この対策を怠ると、悪意のある第三者によってサイトが改ざんされたり、お客様から預かった個人情報が漏洩したりといった、ビジネスの信頼を根底から揺るがす深刻なリスクに繋がります。
特に、WordPressのように世界中で圧倒的なシェアを誇るシステムは、その人気ゆえにハッカーの攻撃対象になりやすいという側面があります。
ソフトウェアに存在する脆弱性(セキュリティ上の弱点)を狙った攻撃は日々行われており、利用者側での継続的な対策が不可欠です。
例えば、WordPress本体や、利用しているテーマ、プラグインのアップデート通知を放置したために、その脆弱性を突かれてサイトが乗っ取られてしまう。
管理画面へのログインパスワードを安易なものにしていたために、不正にログインされる。こうしたケースは後を絶ちません。
最低限の対策として、「推測されにくい強力なパスワードの設定」「ソフトウェアの定期的なアップデート」「万が一に備えたデータのバックアップ取得」の3つは、サイト運営者の義務と心得ましょう。
デメリット(5)集客・SEOは別途対策が必要



苦労してホームページを完成させ、公開ボタンを押した瞬間の達成感は格別です。
しかし、残念ながら、ホームページは「作って公開すれば、自然とお客様が集まってくる」という魔法の箱ではありません。
Webサイトを公開することは、広大なインターネットの海に一軒のお店を出したのと同じ状態です。
何もしなければ、誰にもその存在を知られることなく、訪問者は誰もやってきません。
多くのユーザーに見つけてもらうためには、Googleなどの検索エンジンに「このサイトはユーザーにとって価値がある」と評価してもらい、検索結果の上位に表示させるための努力、いわゆる「SEO対策」が別途必要になります。
具体的には、あなたのビジネスを探しているユーザーがどのようなキーワードで検索するかを考え、そのキーワードに関連する質の高いブログ記事を定期的に公開する。
アクセス解析ツールを導入し、どのページが人気で、どこに改善点があるのかを分析して修正を加える。
SNSと連携させて、ホームページへの入り口を複数作る、といった地道な活動が求められます。



ホームページ作成はゴールではなく、Web集客のスタートラインに立ったに過ぎない、という視点を持つことが何よりも重要です。
自作でも見栄えを良くするためのデザインの基本とは?


この章では、Webデザインの経験がない初心者の方でも、自作ホームページの「素人っぽさ」を回避し、プロが作ったような洗練された印象を与えるための、具体的な3つの基本ポイントを解説します。
デザインセンスは特別な才能ではありません。いくつかの簡単なルールを知るだけで、誰でも見栄えの良い、伝わるサイトを作ることが可能です。
自作でも見栄えを良くするためのデザインの基本には、主に以下の内容があります。
- テンプレート選び:サイトの第一印象と骨格を決める、最も重要なステップ。
- レイアウトと配色:情報を整理し、サイト全体に統一感とプロの質感を与えるルール。
- 画像とフォント:細部へのこだわりが、サイト全体の品質を格段に引き上げる要素。
ポイント(1)最適なテンプレートを選ぶコツ
ホームページのデザインで失敗しないための最も重要な第一歩は、ご自身の好みだけでなく、「ビジネスの目的」と「ターゲット顧客に与えたい印象」に合ったテンプレートを慎重に選ぶことです。
テンプレートは単なるデザインの着せ替えではなく、サイト全体の設計図そのものです。
情報の配置や構造、訪問者が抱く第一印象を根本から決定づけるため、目的に合わないテンプレートを選んでしまうと、後からいくら細部を調整してもうまくいきません。
例えば、信頼性が重視される士業やコンサルタントのホームページであれば、落ち着いた配色で、情報が整理されたシンプルなレイアウトのテンプレートが適しています。
一方で、若者向けのアパレルブランドであれば、写真を大きく見せられるスタイリッシュで大胆なデザインのテンプレートを選ぶと良いでしょう。
また、どんなテンプレートを選ぶにしても、スマートフォンで見た時にレイアウトが崩れない「レスポンシブデザイン」に対応していることは絶対条件です。



テンプレートはあくまで家でいうところの「モデルルーム」であり、完成形ではありません。
選んだテンプレートをそのまま使うのではなく、自社のロゴを配置し、ブランドイメージに合ったカラーに変更し、オリジナルの写真や文章に差し替えることで、初めて「自分のサイト」になります。
ポイント(2)レイアウトと配色の基本ルール
専門的なデザイン知識がなくても、「余白をたっぷりとる」そして「サイト全体で使う色は3色以内にする」という、たった2つの基本ルールを守るだけで、あなたのホームページは一気に洗練され、プロフェッショナルな印象に変わります。



プロが作ったデザインが美しく見えるのは、情報がすっきりと整理され、見やすいからです。
初心者の方はつい情報を詰め込みがちですが、「余白」は情報を際立たせるための重要なデザイン要素です。
文章や画像の周りに十分な余白(ホワイトスペース)を設けるだけで、窮屈な印象がなくなり、コンテンツが引き立ち、高級感が生まれます。
次に配色ですが、多くの色を使いすぎると、まとまりがなくなり素人っぽい印象を与えてしまいます。
基本的には、3色に絞るのがおすすめです。
- サイトの大部分を占める背景などの「ベースカラー(白や薄いグレーなど)」
- あなたのビジネスを象徴する「メインカラー」
- そして問い合わせボタンなど特に注目させたい箇所に使う「アクセントカラー」



もしデザインの調整に迷ったら、まずは「情報を詰め込みすぎていないか?」「色を使いすぎていないか?」を自問自答してみてください。
勇気をもって情報を絞り、色を限定する「引き算のデザイン」を意識するだけで、驚くほど見栄えは良くなります。
ポイント(3)印象を左右する画像とフォント
サイト全体のプロフェッショナルな品質は、細部へのこだわりによって決まります。
特に、高画質で統一感のある「画像」と、読みやすく整理された「フォント」にこだわることで、サイトの印象は劇的に向上します。
画像は、長い文章よりも一瞬で、そして雄弁にあなたのビジネスの魅力やブランドイメージを伝える力を持っています。
スマートフォンのカメラで撮影したものでも、明るい場所で手ブレに気をつけて撮るだけで品質は大きく向上します。
また、UnsplashやPexelsといった、プロが撮影したような高品質な写真を無料で利用できる海外のストックフォトサイトを活用するのも非常におすすめです。
一方、フォントがバラバラだと、どんなに良い内容でも読みにくく、雑な印象を与えてしまいます。
サイト全体で使う書体を1〜2種類に絞りましょう。
例えば、見出しは力強いゴシック体、本文は読みやすい明朝体など、役割を決めて一貫して使用するだけで、サイトは整然として信頼感のある印象になります。



テンプレートのレイアウトを大きく変更する前に、まずはトップページに表示するメイン画像を一枚、最高品質のものに差し替えてみてください。



そして、サイト内のフォントの種類を揃える。たったこれだけの作業でも、サイトの「素人っぽさ」が消え、プロが作ったような質感に近づくことを実感できるはずです。
ホームページ作成に必要なものは何?


この章では、実際にホームページ作成の作業を始める前に、準備しておくべき重要なものを4つのステップで解説します。
難しそうな言葉が出てきますが、一つひとつを「家づくり」に例えながら分かりやすく説明しますのでご安心ください。これらの準備をしっかり行うことが、スムーズなサイト制作と将来の成功に繋がります。
ホームページ作成に必要なものには、主に以下の内容があります。
- 独自ドメイン:インターネット上の「住所」にあたる、あなただけのURL。
- レンタルサーバー:ホームページのデータを置いておく、インターネット上の「土地」。
- SSL化:サイトの安全を守り、信頼性を高めるための「鍵」のようなセキュリティ設定。
- サイト構成案:どんなページを作るかをまとめた、ホームページの「設計図」。
必要なもの(1)独自ドメインを取得しよう
ビジネスで使うホームページを作成するなら、まず最初に準備したいのが「独自ドメイン」です。
これは、インターネットの世界における、あなたの会社やお店だけの「オリジナルの住所」のようなものです。
例えば「https://あなたの会社名.com」といった、世界に一つだけのURLを取得することを指します。
ホームページ作成ツールなどの無料プランでは、サービスの名称が入ったURL(例:〇〇.wix.com/サイト名)が提供されることが多いですが、これは言わば他社のビルの一室を間借りしている状態。



ドメインは、「お名前.com」や「Xserverドメイン」といった専門のサービスで年間1,500円程度の費用から取得できます。
WordPressで自作する場合は自分で契約が必要ですが、Wixなどの作成ツールでは有料プランの契約にドメイン取得(初年度無料の場合が多い)が含まれているケースが一般的です。
ドメイン名は早い者勝ちなので、ホームページ作成を決めたら、まずは希望のドメインが空いているかを確認することから始めてみることをおすすめします。
必要なもの(2)レンタルサーバーを選ぼう
あなたが作成したホームページの文章や画像といったデータを保管し、24時間365日、世界中からアクセスできるように公開しておくための「インターネット上の土地」にあたるのが、レンタルサーバーです。
特に、前の章で紹介したWordPress(ワードプレス)でホームページを自分で作成する場合には、このレンタルサーバーとの契約が必ず必要になります。
ホームページのデータは、常にインターネットに接続された高性能なコンピューター(サーバー)に置いておく必要がありますが、このサーバーを個人で管理・維持するのは非常に大変です。
そこで、専門の業者が管理するサーバーの一部を月額料金で借りる「レンタルサーバー」というサービスを利用するのが一般的です。
初心者の方にも人気の「ConoHa WING」や「エックスサーバー」といったサービスなら、月額500円から1,000円程度の費用で利用でき、WordPressを数クリックで自動的にインストールしてくれる機能も充実しているため、専門知識がない方でも安心して設定を完了できます。
必要なもの(3)SSL化でサイトを保護する
ホームページの信頼性を確保し、訪問者の情報を守るために絶対に欠かせないのが「SSL化」というセキュリティ設定です。



これは、家で言えば「玄関のドアにかける頑丈な鍵」のような役割を果たします。
具体的には、あなたのホームページと、それを見に来た人のパソコンやスマホとの間でやり取りされる情報をすべて暗号化する仕組みです。
もしSSL化されていないサイトのお問い合わせフォームにお客様が個人情報を入力すると、そのデータは暗号化されないまま送受信されるため、途中で悪意のある第三者に盗み見されたり、改ざんされたりするリスクがあります。
SSL化されているサイトは、URLの冒頭が `http://` ではなく `https://` となり、ブラウザのアドレスバーに鍵マークが表示されます。



これが安全なサイトである証です。
Googleもこの安全性を非常に重視しており、SSL化は検索順位にも良い影響を与えるとされています。
今では、ほとんどのレンタルサーバーや作成ツールで、無料のSSL機能が標準で提供されており、簡単な設定で有効にすることができます。
ホームページを公開したら、まずはご自身のサイトがSSL化されているかを確認しましょう。



これは訪問者への最低限のマナーであり、ビジネスを行う上での基本的な設定です。
必要なもの(4)サイトの構成案を考えよう
ドメインやサーバーといった技術的な準備と並行して、必ず行っておきたいのが、ホームページの「構成案(設計図)」を考える作業です。
いきなりデザインや作成作業に取り掛かるのではなく、まず「どんなページを」「どんな順番で」サイトに掲載するかを事前に整理しておくことが、制作をスムーズに進め、訪問者に意図が伝わるサイトを作るための何よりの近道となります。
設計図なしに家を建て始めると、後から「この部屋は不要だった」「動線が悪い」といった問題が出るのと同じで、構成を考えずに作り始めると、情報が整理されず、訪問者が「どこに何があるか分からない」と迷子になってしまう使いにくいサイトが出来上がってしまいます。



まずは、パソコンのメモ帳や手元の紙に書き出すレベルで構いません。
「トップページ」「会社概要」「サービス紹介」「料金プラン」「お客様の声」「ブログ」「お問い合わせ」など、あなたのビジネスに最低限必要なページをリストアップしてみましょう。
そして、それぞれのページにどんな内容(文章や写真)を盛り込みたいかを、簡単にメモしていきます。
ライバルとなる他社のホームページを見て、どんなページ構成になっているかを参考にするのも非常に有効な方法です。
この構成案を考える作業は、ご自身のビジネスの強みを見つめ直す良い機会にもなります。
無料でホームページを作る方法と限界とは?


この章では、「無料でホームページを作りたい」と考える初心者の方に向けて、代表的な無料作成ツールでできること、そしてビジネスで利用する際に知っておくべき機能やデザイン上の制約、広告表示や独自ドメインの扱いといった「限界」について具体的に解説します。
無料で手軽に始められるのは大きな魅力ですが、その裏にある注意点もしっかり理解しておくことが、後悔しないホームページ作成の第一歩です。
無料でホームページを作る方法とその限界には、主に以下の内容があります。
- 機能と制約:無料で使える基本機能と、ビジネス利用では物足りないかもしれない機能制限。
- 広告表示:無料プランの場合、作成したサイトにサービス提供会社の広告が表示される可能性。
- 独自ドメイン:オリジナルのURL(例:あなたの会社名.com)が無料プランで使えるのかどうか。
- 有料版への移行:無料から始めて、必要に応じて有料プランへステップアップする考え方。
- 時間的コスト:無料でもホームページ作成には相応の時間と手間がかかるという現実。
方法・限界(1)無料ツールの機能と制約
Wix(ウィックス)やJimdo(ジンドゥー)、ペライチといった人気のホームページ作成ツールが提供している無料プランを利用すれば、専門的な知識がない初心者の方でも、基本的なホームページの作成は十分に可能です。
具体的には、あらかじめ用意されたデザインテンプレートを選び、テキスト(文章)や画像を編集し、必要なページをいくつか作成するといった作業は、直感的な操作で進めることができます。
しかし、ビジネスで本格的にホームページを活用しようとすると、無料プランには様々な「機能的な制約」があることを理解しておかなければなりません。
例えば、ネットショップ(ECサイト)を開設して商品を販売したいと思っても、無料プランではその機能が使えないか、登録できる商品数が極端に少ないといった制限が設けられているのが一般的です。
また、お客様からの予約を受け付けるシステムや、特定の会員だけが閲覧できるページを作るといった高度な機能も、ほとんどの場合、有料プランでなければ利用できません。
選べるデザインテンプレートの種類が少なかったり、細部まで自由にカスタマイズできる範囲が限定的だったりすることもよくあります。
さらに、サイトに保存できるデータ容量(ストレージ)や、作成できるページ数にも上限が設定されているケースが多く、例えばJimdoのAIビルダー無料版では最大5ページまで、2024年4月以降のAmeba Ownd無料版は最大10ページまでといった具体的な制限が存在します。



個人の趣味のブログや、ごく小規模なサークルの紹介ページなどであれば、無料プランでも十分に目的を果たすことができるでしょう。
しかし、ビジネスの顔として、本格的に集客や販売を行いたい、あるいはプロフェッショナルな印象を与えたいと考えるのであれば、これらの機能制限によって物足りなさを感じる可能性が高いと言えます。
方法・限界(2)広告は表示されるのか?
「無料でホームページが作れるのは嬉しいけれど、作ったサイトに広告は表示されるの?」これは、多くの方が気になるポイントではないでしょうか。
残念ながら、世の中にあるほとんどの無料ホームページ作成ツールでは、あなたが作成したご自身のサイト上に、そのサービスを提供している会社の広告が自動的に表示されてしまいます。
これは、特にビジネス目的でホームページの信頼性やブランドイメージを重視する場合、大きなデメリットとなり得る点です。
なぜなら、サービス提供会社は、ユーザーのサイトに広告を掲載することで広告収入を得たり、自社サービスの宣伝効果を高めたりすることで、無料プランという形でサービスを提供し続けることが可能になるからです。



つまり、広告表示は、私たちが無料でサービスを利用できるための、ある種の「対価」のようなものなのです。
広告の表示形式は利用するツールによって様々ですが、一般的には、サイトの一番下(フッター部分)や一番上(ヘッダー部分)に、「このホームページはWixで作られました」といった小さなテキスト広告や、サービス提供会社のロゴが表示されるケースが多く見られます。
場合によっては、サイトの内容とは直接関係のないバナー広告がページの途中に挿入されることもあります。
個人的なブログや趣味のサイトであれば、こうした広告表示もそれほど気にならないかもしれません。
しかし、企業の公式サイトやお客様に商品を販売するネットショップに、他社の広告が表示されていると、訪問者に「安っぽい」「あまりお金をかけていないのかな?」といったマイナスの印象を与えかねず、ビジネスの信頼性を損なう可能性があります。
方法・限界(3)独自ドメインは使える?
ホームページの「顔」とも言えるURL(インターネット上の住所)ですが、無料プランを利用する場合、基本的に「独自ドメイン」を使用することはできません。



独自ドメインとは、「https://あなたの会社名.com」や「https://お店の名前.jp」のような、あなただけのオリジナルのURLのことです。
無料プランでは代わりに、ホームページ作成サービスを提供している会社のドメインの一部を間借りする形、いわゆる「サブドメイン」のURLが割り当てられます。
例えば、無料プランで作成したホームページのURLは、「https://ユーザー名.wixsite.com/あなたのサイト名」や「https://あなたのサイト名.jimdofree.com」といった形式になります。
これでは、URLが長くて覚えにくく、お客様に口頭で伝える際や、名刺やチラシに記載する際にも見栄えが良くありません。
また、訪問者にとっては、どこのサービスを利用して作られたサイトなのかが一目で分かってしまうため、プロフェッショナルな印象を与えにくいというデメリットもあります。
さらに、SEO(検索エンジン最適化)の観点からも、長期的にサイトを育てていく上では、独自ドメインの方が検索エンジンからの評価も蓄積されやすく、有利とされています。
インターネット上の「自分の城」であるホームページには、「自分だけの住所」である独自ドメインが不可欠です。



ビジネスとして本格的にホームページを運営し、お客様からの信頼を得たいと考えるなら、独自ドメインが利用できる有料プランを選択することが、確かなブランドイメージを構築するための重要な第一歩となるでしょう。
方法・限界(4)有料版への移行も視野に
これまで見てきたように、無料プランには機能面での制約、サイト上への広告表示、そして独自ドメインが使えないといった、ビジネスで利用するには見過ごせないいくつかの「限界」があります。
そのため、これから「自分でホームページを作成」しようとお考えの方は、無料プランはあくまで「お試し期間」や「ツールの操作に慣れるための準備期間」と割り切り、本格的にビジネスで活用していく段階では、必要な機能や信頼性が確保できる有料プランへの移行を最初から視野に入れておくことが賢明です。
なぜなら、無料プランで感じる機能的な物足りなさや、広告表示・サブドメインといったビジネス上のデメリットは、事業を成長させ、より多くのお客様を獲得しようとする上で、必ず何らかの「壁」としてあなたの前に立ちはだかるからです。
最初から有料プランの存在とそのメリット・デメリットを理解していれば、いざ「もっと本格的にやりたい!」と思った時に慌てることなく、スムーズにステップアップすることが可能になります。
例えば、「最初は無料で試してみて、ホームページの操作に慣れてきたから広告を消したい」「ネットショップ機能を追加して、いよいよ商品を販売したくなった」「もっとたくさんのページを作って、情報を充実させたい」といった具体的なニーズが出てきたタイミングで、各ツールが提供している有料プラン(多くは月額数千円から)の内容を比較検討してみましょう。
幸い、多くのホームページ作成ツールは、無料プランから有料プランへのデータ移行が比較的簡単に行えるように設計されています。
方法・限界(5)無料でも時間はかかる?
「無料」という言葉は、「お金がかからない」という意味合いだけでなく、なんとなく「手軽ですぐにできる」というイメージも伴いがちです。
しかし、ホームページ作成に関しては、「無料」だからといって、作成にかかる「時間」や手間が全くなくなるわけではない、という点をしっかりと理解しておく必要があります。
むしろ、無料プラン特有の機能制限の中でなんとか工夫しようとしたり、必要な情報を探したりするのに、想定以上の時間がかかってしまう場合があることも覚悟しておきましょう。
まず大前提として、サイトの構成を考え、各ページに掲載する文章を作成し、あなたのビジネスのイメージに合った写真や画像を用意するといった、ホームページの「中身」を作る作業は、無料プランでも有料プランでも、必ずあなた自身が行う必要があり、これには相応の時間がかかります。
その上で、無料プランの場合は、使える機能やデザインのテンプレートが限られているため、その制約の中でいかに見栄えを良くするか、必要な情報を分かりやすく伝えるか、といった「工夫」に多くの時間を費やすことがあります。
例えば、無料のテンプレートの中から自社のイメージに合うものがなかなか見つからず、何時間も探し回ってしまう。
やっと見つけたテンプレートをカスタマイズしようとしても、無料プランでは変更できる箇所が限られていて思うようにいかない。
サイトに表示される広告を少しでも目立たないようにするためのレイアウト調整に試行錯誤する、といったケースが考えられます。



「無料」という言葉に過度な期待をせず、ホームページ作成には相応の時間と労力が必要であることを理解しておくことが重要です。
自分でホームページを作成する手順は?


この章では、いよいよ実際にホームページを自分で作成していくための具体的な5つの手順を、初心者の方にも分かりやすくステップバイステップで解説します。
「何から手をつけて良いか分からない…」という方もご安心ください。この手順に沿って一つひとつ進めていけば、誰でも迷うことなく自分のホームページを完成させ、インターネット上に公開することができます。
自分でホームページを作成する手順には、主に以下の内容があります。
- 目的・ターゲット設定:誰に、何を伝えるためのホームページなのか、基本方針を固める。
- コンテンツ準備:サイトに掲載する文章や写真、ロゴなどの「材料」を用意する。
- 作成方法の選定:自分のスキルや目的に合った最適なツールやシステムを選ぶ。
- ホームページ制作作業:実際に手を動かして、サイトのデザインやページを形にしていく。
- 公開前の最終チェック:ミスや不備がないか、訪問者の視点で厳しく確認する。
手順(1)目的・ターゲットを明確にする
ホームページ作成に取り掛かる最初の、そして最も重要なステップは、「このホームページで何を達成したいのか(目的)」そして「どんな人に見てほしいのか(ターゲット顧客)」を、ご自身の言葉で明確に定めることです。
家を建てる前に、どんな家でどんな暮らしをしたいか考えるのと同じです。
この基本方針が曖昧なまま進めてしまうと、デザインの方向性が定まらなかったり、掲載する情報が的外れになったりして、せっかく時間と手間をかけて作ったホームページが誰の心にも響かない、効果の薄いものになってしまう危険性すらあります。
例えば、ホームページを作る「目的」としては、「新規のお客様からの問い合わせを月に10件獲得したい」「既存のお客様に向けて、役立つ情報を発信して信頼関係を深めたい」「お店のブランドイメージを向上させて、採用活動にも繋げたい」などが考えられます。
そして「ターゲット顧客」としては、「都内で一人暮らしをする30代の働く女性で、仕事とプライベートの両立に役立つ情報を探している人」「地方在住で健康への関心が高い60代以上のシニア層で、操作が簡単なオンラインサービスを求めている人」など、年齢、性別、ライフスタイル、抱えている悩みや興味関心を具体的にイメージすることが大切です。
まずは難しく考えず、これらの「目的」と「ターゲット」を紙に書き出すことから始めてみましょう。
この最初の「戦略」フェーズにじっくりと時間をかけることが、訪問者に響き、あなたのビジネスに結果をもたらすホームページを作るための、何よりも強固な土台となります。
手順(2)掲載コンテンツを企画・準備
ホームページの目的とターゲット顧客が明確になったら、次はその大切な人たちに向けて「何を伝えたいか」という具体的な掲載コンテンツ、つまりホームページの「魂」となる中身を企画し、事前に準備しておくステップに移ります。
どんなに美しいデザインのホームページでも、そこに掲載されている情報が薄っぺらかったり、訪問者の求めるものでなかったりすれば、残念ながらすぐに他のサイトへ移動されてしまうでしょう。
事前にコンテンツをしっかりと用意しておくことで、実際のホームページ制作作業が格段にスムーズに進むだけでなく、質の高い情報発信が可能になり、訪問者の満足度も高まります。
まずは、サイト全体のページ構成案(サイトマップ)を作成しましょう。



これは、いわばホームページの「間取り図」です。
例えば、「トップページ」「私たちの想い(会社概要)」「サービス・商品のご案内」「料金について」「お客様の声」「お知らせ・ブログ」「お問い合わせ」といった、あなたのビジネスに最低限必要なページをリストアップし、それぞれのページにどのような情報を、どんな順番で載せるかを箇条書きで整理します。
次に、各ページに掲載するキャッチコピーや説明文、サービスの詳細情報などを、Wordやテキストエディタといった使い慣れたツールで事前に作成しておきましょう。
同時に、ホームページの第一印象を左右するメインビジュアルに使う写真、商品写真、スタッフの紹介写真、説明に使う図やイラストなども準備します。
特に文章作成は思った以上に時間がかかる作業ですので、ホームページ作成ツールを触り始める前に、ある程度まとめて準備しておくことを強くおすすめします。
手順(3)最適な作成方法を選定する
ホームページの目的、ターゲット顧客、そして事前に準備したコンテンツの内容を踏まえ、さらにご自身のITスキルやかけられる予算、ホームページ作成に割ける「時間」などを総合的に考慮して、これまでの章で紹介してきた作成方法(ホームページ作成ツール、WordPressなど)の中から、あなたにとって最適な「道具」を選び抜くステップです。



それぞれの作成方法には一長一短があり、「誰にとってもこれが一番良い」という万能な方法は存在しません。
ご自身の状況やホームページの目的に合わない方法を選んでしまうと、途中で操作の難しさに挫折してしまったり、完成したものの期待した効果が得られなかったりする可能性があります。
例えば、「とにかく早く簡単にホームページを公開したい」「パソコンの操作はあまり得意ではなく、専門知識もない」「デザインセンスに自信がない」という初心者の方には、Wix(ウィックス)やJimdo(ジンドゥー)、ペライチといった、直感的な操作が可能なホームページ作成ツールが向いています。
一方、「将来的にたくさんのページを持つ大規模なサイトに育てていきたい」「ブログを頻繁に更新してSEO対策をしっかり行い、集客に繋げたい」「デザインや機能を細部まで自由にカスタマイズして、オリジナリティの高いサイトを作りたい」といった明確な目的があり、ある程度の学習時間や手間をかける意欲のある方には、WordPress(ワードプレス)が最適でしょう。
無料プランの限界(広告が表示される、独自ドメインが使えないなど)も再度確認し、ビジネスで利用するなら有料プランが基本となることも念頭に置いて検討しましょう。
手順(4)実際のホームページ制作作業
利用する作成方法(ホームページ作成ツールまたはWordPress)が決まったら、いよいよ実際に手を動かしてホームページを形にしていく作業に入ります。
ここが、ホームページ作成において最も「時間」と集中力を要する部分ですが、ここまでの計画と準備がしっかりできていれば、闇雲に作業するよりも格段にスムーズに、そして迷うことなく進めることができるはずです。
ホームページ作成ツール(WixやJimdoなど)を利用する場合は、まずアカウントを登録し、豊富なデザインテンプレートの中からあなたのビジネスイメージに合うものを選択します。
その後、事前に準備しておいた文章や画像を、ドラッグ&ドロップ操作や、あらかじめ用意されたコンテンツブロックを組み合わせる形で、各ページに配置していきます。
WordPressを利用する場合は、契約したレンタルサーバーにWordPressをインストールし、デザインのベースとなる「テーマ」を選んで適用します。
その後、お問い合わせフォームやSEO対策といった必要な「プラグイン」を導入・設定し、会社の基本情報などを掲載する「固定ページ」や、ブログ記事などを投稿する「投稿」機能を使って、コンテンツを流し込んでいきます。
最初から完璧な100点満点のホームページを目指す必要はありません。
まずはトップページやサービス紹介ページなど、主要なページから丁寧に作り込んでいきましょう。
手順(5)公開前の最終チェック項目
ホームページの全てのページが一通り完成したら、すぐに「公開」ボタンを押したい気持ちをぐっと抑えて、必ず複数の視点から最終チェックを行い、訪問者にとって不快な思いをさせる可能性のあるミスや不備がないかを徹底的に確認しましょう。
これが、質の高いホームページを世に送り出すための最後の砦となります。自分では完璧にできたつもりでも、客観的に見直すと、思わぬ誤字脱字やリンク切れ、画像の表示崩れなどが見つかることはよくあります。
こうした不備が残ったまま公開してしまうと、訪問者に「この会社は仕事が雑なのかな?」といった悪い印象を与えてしまい、ビジネスの信頼を大きく損なう可能性があるからです。
チェックすべき項目は多岐にわたります。まず、ご自身のパソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットなど、異なる種類の端末やブラウザで表示を確認し、レイアウトが崩れていないかを見ます。
次に、サイト内の全てのページへのリンクが正しく機能しているか(リンク切れがないか)をクリックして確かめます。お問い合わせフォームからは必ずテスト送信を行い、実際に設定したメールアドレスに通知が届くかを確認しましょう。
そして、会社名や住所、電話番号、料金といった重要な情報に間違いがないか、掲載している情報が最新のものになっているかを、一字一句丁寧に見直します。特にネットショップの場合は、プライバシーポリシーや特定商取引法に基づく表記など、法律で定められたページの用意も必須です。
おすすめのホームページ作成ツールは?


この章では、世の中にたくさんあるホームページ作成ツールの中から、特に専門知識がない初心者の方でも安心して「自分でホームページを作成」できる、おすすめのツールを厳選して紹介します。
それぞれのツールの特徴や料金プラン、どんな目的の方に向いているのかを具体的に比較・解説しますので、あなたにぴったりのツールを見つける手助けになれば幸いです。
おすすめのホームページ作成ツールには、主に以下の内容があります。
- 初心者向け無料ツール:まずは費用をかけずにホームページ作成を体験したい方向けの選択肢。
- 高機能な有料ツール:ビジネスで本格的に活用するための、信頼性と機能性を備えた選択肢。
- ネットショップ開設ツール:商品をオンラインで販売したい方向けの、EC機能に特化した選択肢。
- 自分に合うツールの選び方:何を基準に、どうやって最適なツールを見つければ良いかの最終チェックポイント。
ツール(1)初心者向け無料ツール
まず、「ホームページ作成 自分で 無料」というキーワードで情報を探している方にとって、最も気になるのが無料で使えるツールでしょう。
Wix(ウィックス)、Jimdo(ジンドゥー)、ペライチといった人気のホームページ作成サービスでは、専門的な知識が一切なくても、直感的な操作で手軽にホームページを作り始められる無料プランが用意されています。
これらの無料プランの最大のメリットは、何と言っても金銭的なリスクなしに、ツールの基本的な操作感やデザインテンプレートの雰囲気を実際に試せる点です。
例えば、Wixの無料プランでは、900種類以上とも言われる豊富なデザインテンプレートの中から好きなものを選び、ドラッグ&ドロップ操作で写真や文章を配置していくだけで、視覚的に美しいサイトを作ることができます。
Jimdoの無料プラン、特に「AIビルダー」という機能を使えば、いくつかの簡単な質問に答えるだけで、AIがあなたの業種や目的に合ったホームページの土台を自動で作成してくれます。
また、ペライチの無料プランは、1ページ完結型のランディングページ(LP)を非常に短時間で公開したい場合に特化した便利なツールです。
しかし、これらの魅力的な無料プランには、ビジネスで本格的に利用する際にはいくつかの重要な「限界」があることを理解しておく必要があります。
サイトにサービス提供会社の広告が表示されたり、独自ドメイン(オリジナルのURL)が使えなかったり、ネットショップ機能などの高度な機能が利用できなかったり、作成できるページ数に制限があったりする点が主なものです。
例えば、Ameba Owndの無料プランは2024年4月の仕様変更でページ数制限などが厳しくなったという情報もあり、利用前には最新の規約確認が不可欠です。



まずはこれらの無料プランでホームページ作成の第一歩を体験し、操作に慣れることから始めるのがおすすめです。
ツール(2)高機能な有料ツールを比較
ビジネスで本格的にホームページを活用し、お客様からの信頼性を高め、集客や売上アップに繋げたいと考えるなら、無料プランのデメリット(広告表示、サービス名が入ったURL、機能制限など)を解消できる有料ツールの検討が不可欠です。
WordPress.com(ワードプレスドットコム)、Wix(ウィックス)、Jimdo(ジンドゥー)などが提供する有料プランは、初心者にも比較的扱いやすく、かつビジネスニーズに応える高機能な選択肢として有力です。
有料プランに移行する最大のメリットは、プロフェッショナルな印象を与えるホームページ運営が可能になる点です。
具体的には、サイト上の広告が非表示になり、ご自身の会社名やサービス名を使った「独自ドメイン」が利用できるようになります。



これにより、訪問者からの信頼感が格段に向上します。
さらに、SEO対策機能の強化、アクセス解析ツールとの連携、オンライン決済機能の導入、手厚いカスタマーサポート体制など、ビジネスを加速させるための様々な機能やサービスが利用可能になるのも大きな魅力です。
例えば、WordPress.comの有料プランは、月額500円程度の「パーソナルプラン」から広告非表示や独自ドメイン(初年度無料の場合もあり)の利用が可能です。
より本格的なカスタマイズやSEO対策を望むなら、月額2,900円程度の「ビジネスプラン」以上でプラグイン(拡張機能)を自由に追加できるようになります。
Wixの有料プランも月額1,200円程度から広告非表示と独自ドメイン接続が可能で、豊富なデザインテンプレートと専用アプリ(App Market)を組み合わせることで、デザイン性と機能性を高いレベルで両立できます。
Jimdoの有料プランも月額1,000円程度から広告非表示・独自ドメインが利用可能で、AIがサイト作成を補助してくれる「AIビルダー」と、ある程度のカスタマイズが可能な「クリエイター」の2つのモードから選べるのが特徴です。
ツール(3)ネットショップ開設も可能
ご自身の作った商品やサービスを、実店舗だけでなくオンラインでも販売したいと考えている個人事業主や小規模ビジネスの担当者の方も多いでしょう。
そんな時、BASE(ベイス)やShopify(ショピファイ)といったネットショップ作成に特化したサービス、あるいはWixやJimdo、WordPressといったホームページ作成ツールのEC機能(電子商取引機能)を活用すれば、専門的な知識がなくても、スマートフォン中心の操作でも手軽に自分だけのオンラインストア(ネットショップ)を開設・運営することができます。
これらのツールやサービスは、商品の登録から在庫の管理、クレジットカードをはじめとする様々な決済システムの導入、お客様からの注文管理といった、ネットショップ運営に必要な基本的な機能が、初心者でも簡単に扱えるように設計されているのが大きな特徴です。
複雑なプログラミングやサーバーの設定は一切不要で、アカウントを登録し、商品の情報を入力すれば、すぐにでも販売をスタートできます。
特に「BASE」は、初期費用や月額費用が「無料」でネットショップを始められる(別途、商品が売れた際に決済手数料とサービス利用料が発生します)という手軽さが人気を集めています。
専用のスマートフォンアプリ「BASE Creator」を使えば、店舗の開設から商品の写真撮影・登録、日々の売上の確認まで、ほとんどの作業がスマホ一台で完結できるのも魅力です。
また、「Shopify」には、既存のウェブサイトやSNSの投稿に「購入ボタン」を簡単に設置できる低価格な「Starterプラン」(月額数百円から)があり、本格的なECプラットフォームの機能をスマートフォンからでも手軽に利用開始できます。
WixやJimdoの有料プランにも、ホームページと一体化したネットショップを運営できる機能が搭載されています。
WordPress(ワードプレス)であれば「WooCommerce」という無料のプラグインを導入することで、世界で最も利用されている非常に自由度の高いネットショップシステムを構築することも可能です(ただし、設定や運用にはある程度の知識が必要となります)。
ツール(4)自分に合うツールの選び方
ここまで、初心者向けの無料ツール、ビジネスで本格的に使える有料ツール、そしてネットショップ開設に特化したツールなど、様々なホームページ作成の選択肢を紹介してきました。



しかし、「結局、自分にはどのツールが一番合っているの?」と迷ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
最終的にどのツールを選ぶべきかという問いに対する答えは、あなたが「ホームページを作る目的は何か」「ホームページ作成にかけられる時間と予算はどれくらいか」「どんな機能が絶対に必要か」「ご自身のITスキルやWebに関する知識はどの程度か」という4つのポイントを、ご自身の状況に照らし合わせて総合的に比較検討することで、自ずと見えてくるはずです。
残念ながら、「誰にとってもこれが一番良い」という万能なホームページ作成ツールは存在しません。
それぞれのツールには得意なことと不得意なことがあり、あなたの状況や目的に合わないツールを選んでしまうと、せっかくの「時間」や「費用」が無駄になったり、操作の難しさから途中で挫折してしまったりする可能性があるからです。
例えば、「とにかく名刺代わりの簡単なホームページが、今日明日にでも欲しい」というスピード重視の目的なら、ペライチやJimdoの無料プランまたは低価格な有料プランが最適かもしれません。
「デザイン性の高い、おしゃれなブランドサイトを作って、お客様に良い印象を与えたい」というなら、Wixの豊富なテンプレートと自由な編集機能が魅力的に映るでしょう。
「ブログを積極的に更新してSEO対策をしっかり行い、将来的にはネットショップも展開して集客から販売までを一貫して行いたい」といった長期的な展望があるなら、WordPressの圧倒的な拡張性が最も適しています。
そして、もし「パソコンの操作は本当に苦手で、専門知識は全くない」ということであれば、JimdoのAIビルダーやペライチのような、操作が極めて簡単なツールから始めるのが安心です。



もし迷ったら、まずは気になるいくつかのツールの無料プランやお試し期間を積極的に利用して、実際にをご自身の手で触ってみることを強くおすすめします。
まとめ


「ホームページを自分で作成したい」その想いを実現するため、この記事ではツールの選び方を中心に、無料と有料の違い、デザインのコツ、作成手順まで網羅的に解説しました。
WixやWordPressなど選択肢は多様ですが、目的やかけられる時間、予算を明確にすれば最適なツールが見つかります。



無料プランで試すのも良いでしょう。
この記事が、あなたのホームページ作成の不安を解消し、自信を持って第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。あなたの手で、ビジネスを成功に導くホームページを完成させてください。