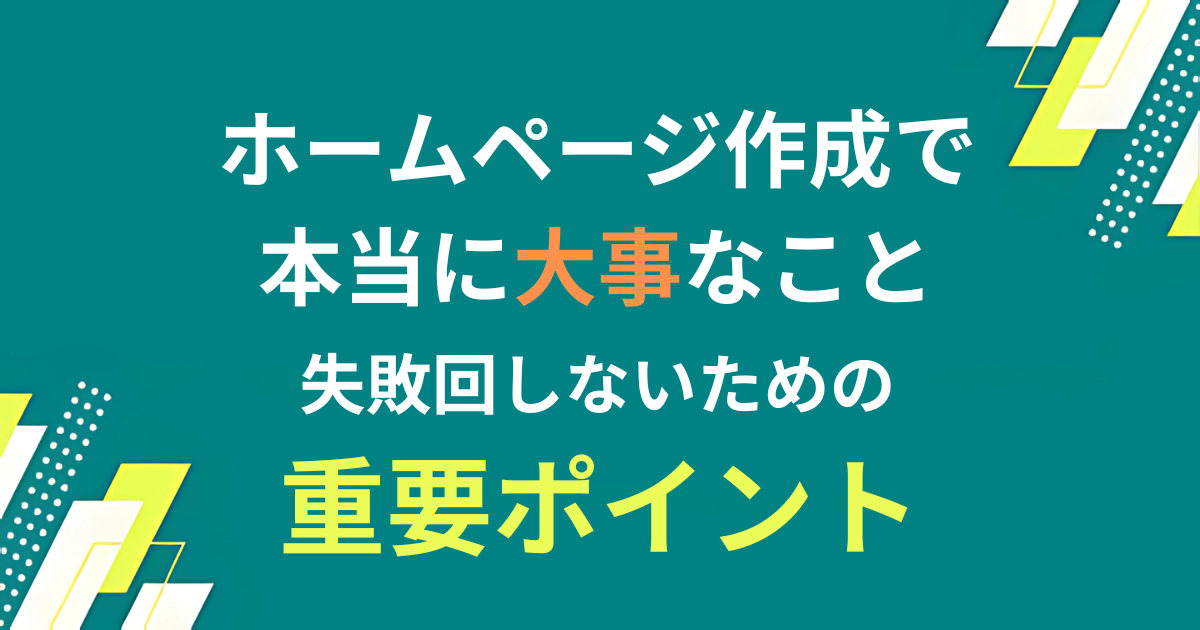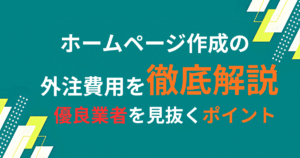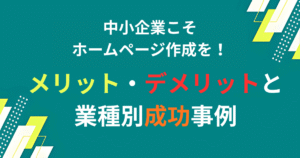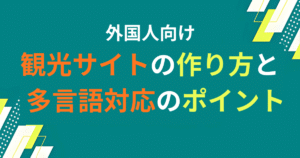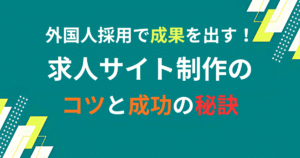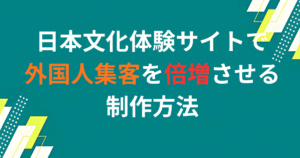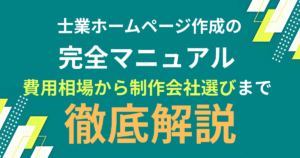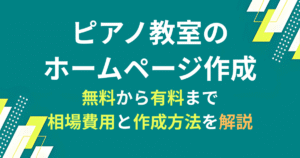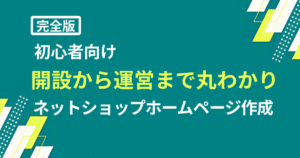ホームページ作成で大事なことは「見た目の美しさ」ではなく、実際に集客効果を生む設計だと知っていましたか?
初心者が制作会社選びで失敗したり、自作で時間を浪費したりする原因は、準備不足と優先順位の間違いにあります。
費用対効果を最大化する判断基準から、デザインよりも重要なSEO対策まで、成果の出るホームページ制作の本質を解説します。



この記事を読めば「作って終わり」ではなく「作ってから始まる」サイト運営の全体像が見えてくるでしょう。
ホームページ作成で大事なことは?制作前に決めるべき要素


この章では、ホームページ作成で失敗しないために制作前に必ず決めておくべき大事な要素について紹介します。



2025年現在、多くの企業がホームページ制作で失敗する原因は、デザインや技術的な問題ではなく、制作前の戦略設計が不十分であることです。
成果につながるホームページ制作には主に以下の内容があります。
- 明確な運営目的の設定と一本化
- 具体的なターゲット像の詳細な定義
- 競合他社との差別化ポイントの明確化
- 目的に応じた必要ページと機能の洗い出し
- 現実的な予算・スケジュール・体制の構築
要素(1)何のためにホームページを運営するのかという目的を決める
ホームページ作成において最も大事なことは、運営する目的を明確に定めることです。
目的が曖昧なままホームページ制作を開始すると、デザインや機能の選択で迷いが生じ、結果として誰の心にも響かないウェブサイトが完成してしまいます。
主要な目的として、見込み顧客の獲得、直接的な売上創出、企業の信頼性構築、人材採用、顧客サポートの5つが挙げられます。
重要なのは、これらの中から必ず一つだけに絞り込むことです。
例えば見込み顧客獲得が目的なら、サービス紹介ページと問い合わせフォームを中心とした構成になり、人材採用が目的なら社員インタビューや企業文化を伝えるコンテンツが主役となります。
複数の目的を同時に達成しようとすると、ユーザーの動線が複雑になり、かえって成果が下がってしまうため注意が必要です。
要素(2)誰に向けて情報を届けるのかを決める
ホームページ作成で大事な要素の一つが、具体的なターゲット設定です。
20代から60代の女性といった広すぎる設定では、効果的なホームページ制作はできません。
現代の情報過多な環境では、ユーザーのニーズが多様化しており、すべてのユーザーが同じ情報を求めているわけではないからです。
成果を出すためには、32歳フリーランスWebデザイナーで都内在住、集中できるカフェを探しているといったレベルまで具体化したペルソナを作成する必要があります。
このように詳細に設定することで、その人が検索しそうなキーワード、響く言葉遣い、求める情報の優先順位が明確になります。
ペルソナ作成には、既存顧客へのインタビューやGoogleアナリティクスのデータを活用し、実在するデータに基づいて行うことが重要です。



作成したペルソナは制作チーム全員で共有し、すべての判断の基準として活用しましょう。
要素(3)自分たちだけの特徴や魅力は何なのかを考える
競合他社との差別化ポイントを明確にすることは、ホームページ作成において極めて大事な要素です。



独自の価値提案がなければ、価格競争に巻き込まれ、ユーザーに選ばれる理由がありません。
2025年のWebトレンドでは、検索エンジンが独自の経験や専門性に基づいた価値を重視するため、SEO効果の面でも差別化は重要です。
差別化ポイントの発見方法として、技術・ノウハウ面では20年間無事故の建設実績や特許取得済みの独自製法、サービス体制面では24時間対応や初回相談無料、地域性・専門性では地元密着50年や女性専門といった要素が考えられます。
実績・評価面では顧客満足度98%やリピート率85%などの具体的な数値も効果的です。
競合他社のウェブサイトを3から5社分析し、自社だけが訴求できるポイントを見つけ、それをファーストビューで3秒以内に伝わるキャッチコピーとして表現することが成功の鍵となります。
要素(4)必要ページと機能要件の洗い出し
目的とターゲットが決まれば、必要なページと機能は自動的に決まります。
優れた情報アーキテクチャは、ユーザーが必要な情報を見つけやすくするだけでなく、検索エンジンがサイトの内容を正しく理解するのを助けるため、UXとSEOの両面で重要です。
サイトの構造を固める前にデザインの議論を始めてしまうことが、多くのプロジェクトが失敗する原因の一つとなっています。
3クリックルールを意識し、ユーザーがどのページにいても3クリック以内で目的の情報にたどり着けるように設計することが大切です。
見込み顧客獲得型ならサービス詳細・導入事例・料金・会社概要・お問い合わせ、採用特化型なら会社理念・社員インタビュー・働く環境・福利厚生・採用情報といった構成になります。
2025年対応として、SSL化やスマートフォン対応に加え、ウェブアクセシビリティ対応やダークモード対応も重要な機能要件となっています。
要素(5)予算・スケジュール・体制を決める
自作か外注かの判断は、ホームページ作成において最も大事な経営判断の一つです。
これは単なる費用の問題ではなく、コスト・時間・品質・期待される成果のトレードオフをどう判断するかという問題です。
自作の場合、初期費用をほぼゼロに抑えることが可能ですが、特に集客を目的とする場合、SEOやコンバージョン設計に関する専門知識がなければ、プロが作ったサイトとの競争に勝つのは極めて困難です。
一方、外注の場合は高コストですが、専門的なノウハウが盛り込まれた成果につながりやすいサイトが手に入ります。
オンライン名刺代わりや事業内容の簡単な紹介が目的なら自作も検討できますが、見込み顧客獲得やECサイト運営が目的なら外注を推奨します。



2025年度は小規模事業者持続化補助金やIT導入補助金といった制度が充実しており、これらを活用すれば外注費用を大幅に削減できるため、積極的に検討しましょう。
ホームページのデザインで大事なこと





この章では、2025年のホームページデザインにおいて最も重要な「ユーザー体験を重視した機能性と視覚的美しさの融合」について紹介します。
現代のホームページ制作では、見た目の美しさだけでなく、すべてのユーザーが快適に利用できる設計が求められています。
成果を出すホームページデザインには主に以下の内容があります。
- 直感的で迷わないナビゲーション設計
- スマホ・PC・タブレット対応のレスポンシブデザイン
- 3秒以内の高速ページ表示速度
- 3秒で価値が伝わるファーストビュー設計
- すべてのユーザーに配慮したアクセシビリティ対応
ポイント(1)直感的に操作できること
2025年のWebデザイントレンドでは、従来の使いやすさ重視から、ユーザー体験を損なわない範囲での体験重視へとシフトしており、直感的に操作できるナビゲーションが最重要となっています。
ユーザーが迷わずに目的の情報にたどり着けるデザインこそが、成果につながるホームページの基盤です。
具体的には、会社概要やサービス、お問い合わせなど誰でも理解できる言葉を使用し、パンくずリストで現在位置を明示することが効果的です。
3クリック以内で目的の情報にたどり着けるようなサイト構造を設計し、Google AnalyticsやHotjarなどのツールを活用してユーザーの行動パターンを分析し、改善を重ねることが重要です。
ポイント(2)スマホやPCなど見るデバイスによって自動でデザインが最適化されること
モバイルファーストデザインの重要性は2025年も増す一方で、ユーザーがスマートフォンで快適に閲覧できるレスポンシブデザインは必須要件となっています。



現在、国内の画面サイズシェア率では1920pxが最も高いものの、実際には多様なデバイスが使用されているため、すべての画面サイズに対応する必要があります。
フルードグリッドによる要素の自動リサイズ、デバイスの解像度に応じた最適な画像表示、スマホでのタップ操作を考慮した最低44px四方のボタンサイズ、モバイルでは最低16px以上の読みやすいフォントサイズの確保が重要です。
ポイント(3)読み込み速度が早いこと
2025年現在、Core Web VitalsのLCP、INP、CLSがSEOとユーザー体験の両面で極めて重要であり、ページ表示速度はホームページの成果を大きく左右する要素です。
楽天24がCore Web Vitalsに投資した結果、訪問者あたりの収益が53.37パーセント、コンバージョン率が33.13パーセント増加した実例があるように、表示速度は売上に直接影響します。
具体的には、LCPでページ読み込みから2.5秒以内の表示、INPでユーザーのアクションに対して200ミリ秒未満での視覚的反応、CLSで0.1未満の視覚的安定性スコアが目標となります。
画像最適化やWebP形式の使用、不要なコードの削除、CDNの活用などの改善方法を実施し、Google PageSpeed Insightsで定期的にチェックすることが重要です。
ポイント(4)ファーストビューで魅力が伝わること
ユーザーはウェブサイトを訪れた最初の3秒で、そのページが自分にとって有益かどうかを無意識に判断し、読み進めるか離脱するかを決めるため、ファーストビューでの魅力的な情報伝達が成果を決める最重要要素です。
ファーストビューで離脱してしまうユーザーは70パーセント以上といわれるため、最初の印象で勝負が決まります。
効果的なファーストビューには、3秒で価値が伝わる簡潔で力強いキャッチコピー、ターゲットが自分のことだと感じる画像や動画、無料相談や資料ダウンロードなど具体的な行動を促すCTAボタン、実績数値や顧客ロゴなどの信頼性を示す要素、競合との違いを一目で理解できる差別化ポイントが必要です。
ポイント(5)アクセシビリティの配慮があること
2024年4月に改正障害者差別解消法が施行され、民間事業者も合理的配慮の提供が義務化されました。
ウェブアクセシビリティ自体は努力義務ですが、2025年のWebデザイントレンドでは視覚的な美しさだけでなく、アクセシビリティや持続可能性、UXの向上など、より深い価値が求められています。
ウェブアクセシビリティを確保することで、人だけでなく検索エンジンのクローラーでもウェブサイトの構造や内容を理解しやすくなり、SEO効果が向上します。
基本的な対応として、高コントラストな色使い、画像へのalt属性設定、キーボード操作対応、明瞭で使いやすいナビゲーション、動画の字幕などがあります。



JIS X 8341-3:2016やWCAG2.2を参考に、段階的に対応を進めることをお勧めします。
ホームページのSEOで大事なこと





この章では、2025年のSEO対策において最も重要な「AI時代に対応したユーザーファーストの検索最適化戦略」について紹介します。
現代のSEOは単なるキーワード最適化を超え、検索エンジンとユーザーの両方に価値を提供する総合的なアプローチが求められています。
成果を出すホームページのSEO対策には主に以下の内容があります。
- 実体験に基づく事例や体験談の充実
- 構造化データや内部リンクなどテクニカルSEO要件の実装
- 検索意図を捉えたロングテールキーワード戦略
- E-E-A-Tを意識した信頼性の構築と提示
- 継続的なコンテンツ更新と品質改善
施策(1)事例や体験談を充実させる
2025年のSEOでは、Googleが従来のE-A-Tに経験(Experience)を追加したE-E-A-Tが最重要評価指標となっています。
AIが再現しにくい実体験に基づく情報が高く評価される傾向にあり、人間の独自性を示す重要な差別化要因です。
具体的な成果数値や現場で直面した課題と解決方法、実際の導入プロセスなど、第三者には得られない情報をコンテンツに盛り込むことが効果的です。
著者の経験や資格を明記し、顧客の声や実績を積極的に掲載することで、検索エンジンからの信頼性向上につながります。



特に健康や金融などの重要な決断に影響するトピックでは、専門性と経験の両方を示すことが重要です。
施策(2)内部リンク・構造化データなどテクニカルSEO要件を盛り込む
構造化データを活用することで、検索結果にリッチリザルトが表示され、クリック率の向上が期待できます。
適切なメタタグの設置、内部リンクの最適化、インデックス登録の申請などは、検索エンジンがサイトを正しく理解するための基盤となります。
ページタイトルや説明文、見出しタグ、画像のalt属性を適切に設定し、グローバルナビゲーションやパンくずリスト、関連ページへのリンクを活用してサイト構造を明確にすることが重要です。
また、Core Web VitalsでLCP2.5秒以内、INP200ミリ秒未満、CLS0.1未満を目標とし、モバイル対応やHTTPS化も必須の要件となっています。
施策(3)キーワード戦略を誤らない
従来のビッグキーワード戦略から、競争が少なく検索意図が明確なロングテールキーワードがより有利になっています。
2025年のSEOでは、単にキーワードを入れるだけでは効果がなく、検索意図に合ったコンテンツを提供できるかが最も重要です。
AI Overviewが検索結果に表示される状況で、より詳細で専門性の高いコンテンツが評価される傾向にあります。
Search ConsoleやGA4を活用してユーザーの検索行動を分析し、競合調査を行いながら関連キーワードでページを作成し内部リンクで結合するクラスター戦略が効果的です。
一般的な質問はAIに任せ、自社の専門分野に特化したロングテールキーワードを選定することが重要です。
施策(4)信頼性の提示
2025年のSEOでは、ブランド力が大きくランキングに影響し始めているため、企業や個人の信頼性を明確に示すことが重要です。
執筆者の経歴、保有資格、専門分野の経験年数、事業実績、取引先、受賞歴、認定資格などを明示し、顧客レビューやメディア掲載実績、業界団体への加盟状況も積極的に掲載することが効果的です。
統計データや調査結果、公的機関の情報引用により信頼性を裏付け、連絡先情報やプライバシーポリシーの明記により透明性を確保することも重要な要素となります。
施策(5)定期的に更新する
質の高いコンテンツ制作はこれまで以上に重要になっており、Googleは役に立つコンテンツアップデートを通じて、ユーザーにとって有益で信頼性の高いコンテンツを評価する姿勢を明確にしています。
情報が古くなると信頼性が低下し、SEOパフォーマンスにも悪影響を与えるため、定期的な更新が不可欠です。
既存記事の情報更新や最新データへの差し替え、業界の最新動向や新しい事例の追加、季節性コンテンツの修正、よくある質問への対応など、多角的な更新戦略が効果的です。
月1回程度の定期的なコンテンツレビューを実施し、Google Search Consoleを活用して効果的な更新計画を立てることが成功の鍵となります。
ホームページ運用で大事なこと
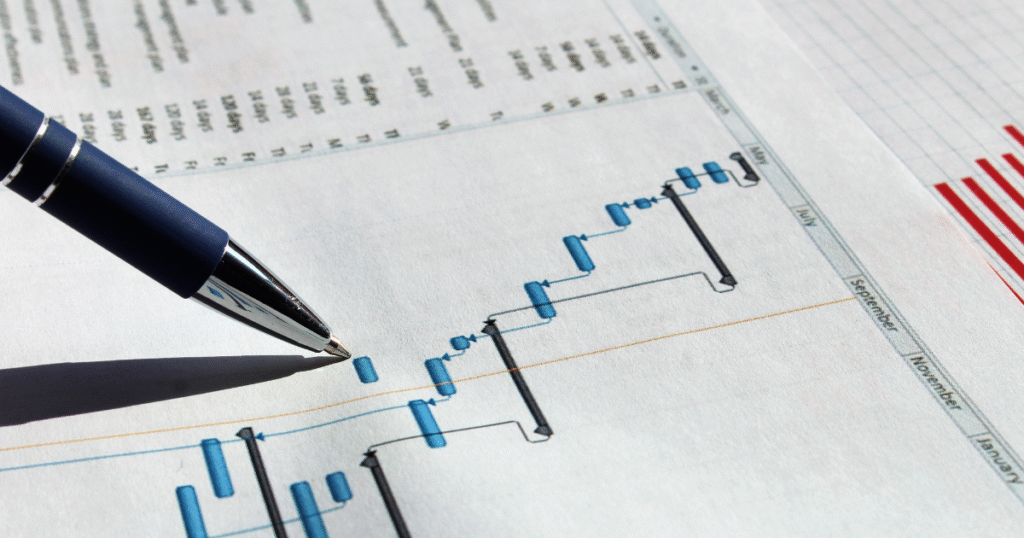
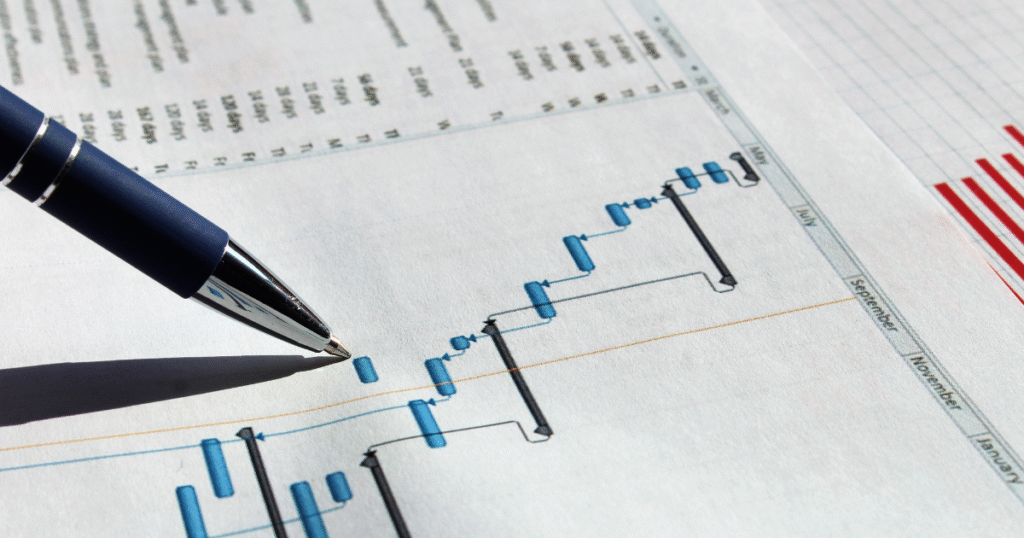
この章では、ホームページを公開した後の継続的な運用について紹介します。



ホームページは「作って終わり」ではなく、むしろ公開後の運用が成果を左右する重要な要素です。
運用には主に以下の内容があります。
- アクセス状況の定期的な計測と分析
- SEO効果を測定するための検索順位チェック
- サイバー攻撃や情報漏洩を防ぐセキュリティ対策
- 情報の鮮度を保つための更新管理
- 継続的な運用を可能にする体制構築
運用(1)アクセスの計測を行う
ホームページの運用において、アクセス解析は効果測定と改善のために不可欠な取り組みです。



適切なツールを導入し、定期的にデータを確認することで、サイトの問題点を発見し、成果向上につなげることができます。
初心者が見るべき最重要指標は、Googleアナリティクス4でのユーザー数・セッション数・コンバージョン率、Googleサーチコンソールでの表示回数・クリック数・検索クエリです。
まずは無料で利用できるこれらのツールを導入し、月1回30分程度のデータ確認習慣から始めることをお勧めします。
数値に圧倒される必要はありません。最初は「先月と比べてアクセスは増えたか」「どのページがよく見られているか」の2点だけでも十分効果があります。
運用(2)狙ったキーワードの順位を計測する
検索順位チェックツールを活用することで、SEO対策の効果を客観的に測定し、改善すべきポイントを明確化できます。
検索からの流入は特に大きな割合を占めることが多く、検索順位によって自社サイトへの訪問者数が大きく変化します。



初心者には「検索順位チェッカー」や「ohotuku.jp」といった無料ツールがお勧めです。検索順位チェッカーは3大検索エンジン(Google、Yahoo!、Bing)の順位結果が表示可能で、ohotuku.jpはGoogleとYahoo!に対応しています。
より本格的な運用を考える場合は、GRCやRankTrackerなどの有料ツールを検討しましょう。
まずは3から5個の重要キーワードから始めて、週1回の頻度で順位をチェックすることで、SEO対策の効果を確実に把握できるようになります。
運用(3)セキュリティ対策
2025年のサイバーセキュリティ環境では、ランサムウェア攻撃やフィッシング攻撃が増加傾向にあり、中小企業でも最低限のセキュリティ対策が必須となっています。
基本的なセキュリティ対策として、SSL証明書の導入は必須で、通信が暗号化され第三者による盗聴や改ざんを防ぐことができます。
WordPressを利用している場合は、コアシステムやプラグインの定期的なアップデート、バックアップの取得、不正アクセス監視が重要です。
最低限として、SSL証明書の導入・自動更新設定、WordPressの自動アップデート設定、週1回のバックアップ取得から始めましょう。



予算に余裕がある場合は、セキュリティ専門業者による定期診断サービスの利用も検討してください。
運用(4)古くなった情報を検知できるようにする
ホームページは新しい情報の更新が信頼性に直結し、何年も放置されたホームページは検索エンジンからの評価が低くなりやすく、ユーザーが競合他社に流れてしまう原因となります。
定期的に更新されるホームページは、企業が活動的で信頼できるという印象を与えます。
特に営業時間、料金、サービス内容、連絡先などの基本情報が古いままだと、顧客との信頼関係を損なう可能性があります。
情報の鮮度管理には、コンテンツごとに「更新日」「有効期限」を設定する方法が効果的です。
例えば、イベント情報は開催後に削除、料金表は年1回見直し、スタッフ紹介は半年ごとに確認するといったルールを作ります。
Googleカレンダーやスマートフォンのリマインダー機能を活用して、定期的な見直しスケジュールを設定しましょう。
運用(5)担当者が忙しくても更新できる体制を整える



ホームページの運用保守を成功させるには、事前に運用体制を整えることが不可欠で、担当者やチームを明確にし、各作業に対して責任者を割り当てる必要があります。
多くの企業では「管理の担当者が通常業務と兼任で、ホームページを更新する余裕がない」「ホームページの運用や更新に関する専門的な知識がない」という課題を抱えています。
効果的な体制作りとして、社内の複数名で更新権限を共有する(CMSの活用)、簡単な更新は社内、専門的な作業は外注と役割分担する、保守作業の手順・トラブル対応を社内WikiやGoogle Workspaceに集約する方法があります。
まずは更新頻度と作業内容を整理し、「緊急度:高×難易度:低」の作業は社内で対応できる体制を作り、月1回30分の「ホームページ見直し会議」を設定することで、属人化を防ぎ継続的な運用が可能になります。
契約前の最終チェックリストは?


この章では、ホームページ制作会社との契約前に確認すべき重要なポイントについて紹介します。
契約後のトラブルを避け、期待通りの成果を得るために、事前のチェックには主に以下の内容があります。
- プロジェクトの範囲と成果物を明確にする要件定義
- スケジュールと品質基準の合意形成
- 知的財産権とデータ所有権の整理
- 全体コストの透明性確保
- 運用開始後のサポート体制確認
チェック(1)要件定義書・RFP:ページ数・機能・スコープの明文化
要件定義書やRFP(提案依頼書)の作成は、制作会社との認識齟齬を防ぎ、プロジェクトを成功に導くための最重要ステップです。
ホームページ制作の失敗の最大の原因は「明確な目的を設定しないまま始めること」であり、曖昧な要件はデザインや機能の選定が個人の好みに左右され、誰の心にも響かない結果を招きます。
例えば「企業サイト10ページ」という曖昧な依頼ではなく、「トップページ・会社概要・サービス紹介3ページ・導入事例2ページ・ブログ機能・お問い合わせフォーム・採用ページ・プライバシーポリシー、計10ページ、スマートフォン対応、SSL対応、WordPress導入」といった具体的な要件を記載することが大事なことです。
チェック(2)納期・修正回数・検収基準:合意とエビデンス化
納期、修正回数、検収基準の明確化は、プロジェクトの品質と進行を管理するための必須要件です。
ホームページ制作は創作的な要素が強く、完成品の評価が主観的になりがちなため、客観的な検収基準がないと「完成」の定義が曖昧になり、無限の修正要求や品質への不満が生じます。
契約書には「初回デザイン提案から3回まで大幅修正可能、以降は軽微な修正のみ」「各ページの表示速度3秒以内」「スマートフォンでの表示確認必須」「SSL証明書導入確認」といった具体的な基準を記載し、納期についても段階的なマイルストーンを設定することで、制作会社とのトラブルや期待値の不一致を防ぐことができます。
チェック(3)権利関係:著作権・データ納品・ドメイン管理
著作権、データ納品、ドメイン管理権の所在を契約前に明確化することは、将来的な事業継続性とリスク回避のために極めて重要です。
ホームページは長期的なビジネス資産であり、制作会社との契約終了後も継続して利用する必要があるため、権利関係が曖昧だと制作会社との関係悪化時にホームページが使用できなくなるリスクがあります。
理想的な契約条件として「ホームページの著作権は納品時に発注者に完全移譲」「WordPressの管理者権限、FTPアクセス権限、ドメイン管理権限をすべて発注者が保有」「ソースコードとデザインデータの完全納品」を確保し、ドメインは発注者名義で取得することが安全です。
チェック(4)総額の把握:初期・月額・追加・解約費の合算
ホームページ制作の真のコストは初期費用だけでなく、月額維持費、追加作業費、解約時費用を含めた総額で判断する必要があります。
ホームページ管理費の相場は月額5,000円から2万円程度ですが、制作会社によって保守内容や料金体系が大きく異なり、「初期費用は安いが月額費用が高い」「軽微な修正でも高額な追加料金が発生する」といった事例が報告されています。
例えば初期費用30万円、月額1万円の場合と、初期費用50万円、月額5,000円の場合を3年間で比較すると、前者は総額84万円、後者は総額68万円となり、初期費用の安さに惑わされると結果的に高額になる可能性があります。
チェック(5)保守とSLA:対応範囲・連絡窓口・緊急時フロー
保守サービスの対応範囲、SLA(サービス品質保証)、緊急時対応フローの確認は、ホームページの安定運用と事業継続性を確保するために必須です。
ホームページ運用では定期的なセキュリティ対策、システムアップデート、バックアップ取得が必要で、2025年のサイバーセキュリティ環境ではランサムウェア攻撃やフィッシング攻撃が増加傾向にあり、専門的な保守対応の重要性が高まっています。
明確にすべき保守内容として「WordPressコアアップデート、プラグイン更新、セキュリティパッチ適用、週1回バックアップ取得、SSL証明書更新、表示速度監視」があり、SLAについては「障害発生時2時間以内に第一報、営業時間内8時間以内に復旧、月間稼働率99.9%保証」といった具体的な数値を確認することが大切です。
まとめ


本記事では、ホームページ作成で大事なことを設計・デザイン・SEO・運用の各視点から解説しました。
多くの要素がありますが、最も重要なのは制作に着手する前の「設計」です。
「誰に、何を伝え、どうなってほしいのか」という目的とターゲットを明確にすること。



この土台がしっかりして初めて、効果的なデザインや必要な機能、正しいSEO戦略が決まります。
見た目の良さや機能の多さに惑わされず、まずは自社の目的をじっくりと言語化することから始めてください。



その軸さえ固まれば、制作の過程で判断に迷うことなく、本当に成果の出るホームページを実現できるでしょう。