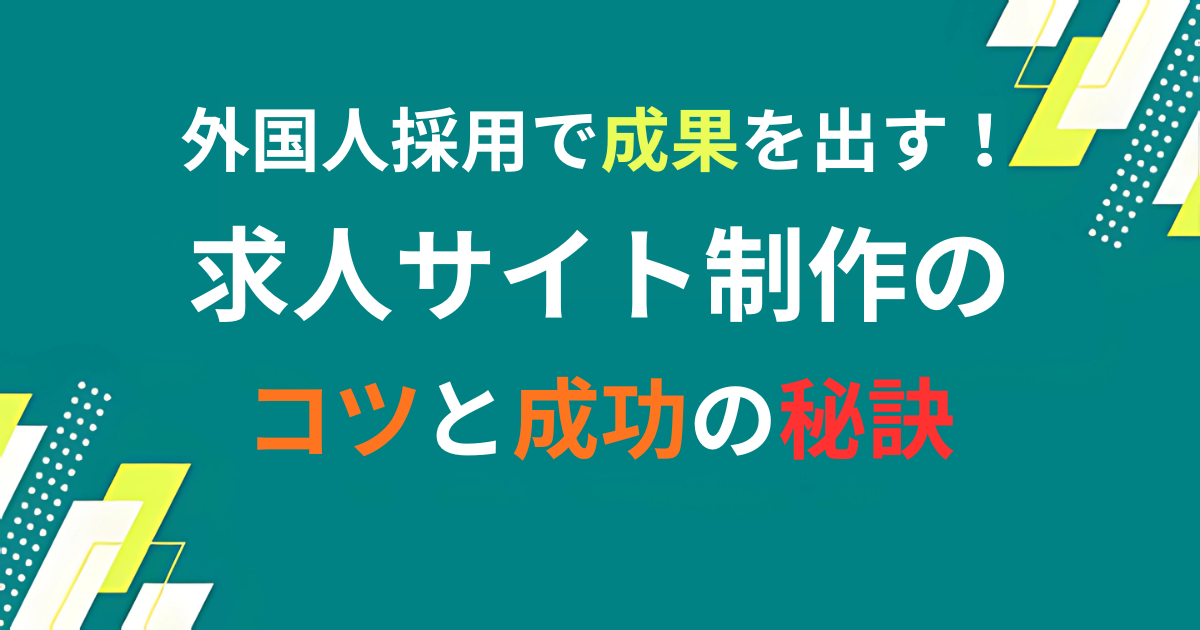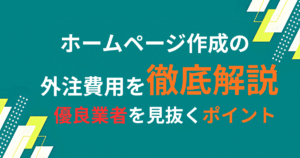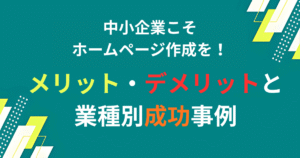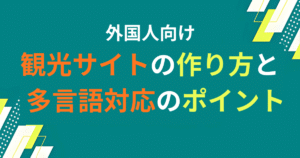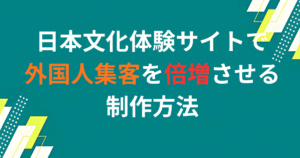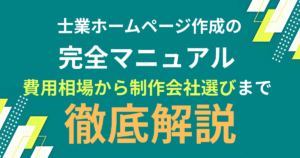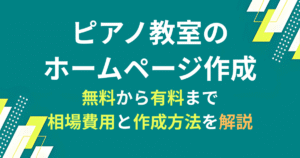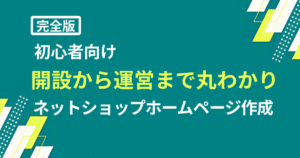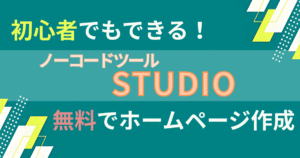外国人向けの求人サイトの作り方を探している採用担当者へ、応募が伸びない原因を“伝わる設計”で解決しましょう。
求人ページは、多言語対応とやさしい日本語、ビジュアルで信頼を伝えることが重要です。
応募導線はスマホ最適化と短いフォーム、WhatsApp・LINE併記で離脱を抑え、文化差に配慮したFAQで不安を先回り。
さらにGoogle しごと検索対応の構造化データとSNS流入、ローカルSEOを組み合わせれば、低予算でも質の高い応募が集まります。



本記事では成功事例と設計ポイント、使えるテンプレとチェックリストまで提供—今すぐ“伝わる採用サイト”で採用効率を上げませんか?
外国人向け求人サイトの作り方は?作成前に決めること





この章では、外国人向け求人サイトの制作を成功させるために企画段階で決めておくべき重要な前提条件について紹介します。
2025年現在、外国人労働者数は約230万人に達し過去最高を更新する中、自社サイトでの採用強化は競合に差をつける重要な戦略となっています。



制作前の準備が不十分だと、ターゲットに響かないサイトになり応募効果が得られません。
外国人向け求人サイトの作り方には主に以下の内容があります。
- 外国人向け求人サイトの定義と対象者の明確化
- 一般求人サイトとの違いと自社制作の必要性判断
- 採用市場の動向と応募者インサイトの把握
前提(1)外国人向け求人サイトの定義と対象者(在留資格・言語・職種)を明確にする
外国人向け求人サイトを作成する際は、在留資格・対象言語・募集職種を具体的に定義してターゲットを絞り込むことが成功の前提条件となります。
2025年最新データでは、ベトナム人が24.8%、中国人が17.8%、フィリピン人が10.7%と外国人労働者の上位3位を占めており、国籍によって求める情報や応募行動が大きく異なります。
製造業で特定技能1号を対象とする場合はベトナム語・日本語併記で寮完備をアピールし、IT業界で高度専門職を対象とする場合は英語メインでキャリアアップ制度を前面に出すなど、ターゲットに応じた情報設計が必要です。
制作開始前にペルソナシートを作成し、国籍・年齢・在留資格・日本語レベル・職歴・来日動機まで具体化してサイト全体の方向性を決定しましょう。
前提(2)一般求人サイトとの違いと自社で作る必要性を判断する
外国人向け求人サイトは一般求人サイトとは全く異なる設計思想が必要で、自社制作の投資対効果を慎重に判断することが重要です。
一般求人サイトでは伝わらないビザサポート詳細、多言語対応、文化的配慮、生活支援制度が外国人採用の決定要因となります。
YOLO WORKやGuidable、WORK JAPANなどの既存媒体では月数万円で求人掲載できる一方、自社サイト構築には初期費用50万円から300万円、月額運用費1万円から5万円がかかります。
しかし自社サイトでは企業文化の詳細な発信、長期的な採用ブランディング、応募者との直接コミュニケーションが可能になるメリットがあります。
まず外部求人媒体での応募状況を3ヶ月から6ヶ月テストし、自社サイト構築による採用品質向上が投資額を上回ると判断できる場合に制作を開始することをおすすめします。
前提(3)採用市場の動向と応募者インサイトを把握する
2025年の外国人採用市場は急成長期にあり、応募者の情報収集行動と求職ニーズを正確に把握することがサイト設計の根幹となります。



厚生労働省の最新データでは外国人労働者数は前年比12.4%増の約230万人と過去最高を更新し、特定技能制度の運用改善により多くの外国人が中小企業への就職を検討しています。
製造業が最多の55.2万人、建設業18万人、介護業でも外国人依存度が上昇しており、情報収集はスマートフォン中心でFacebookなどのSNSコミュニティでの口コミを重視する傾向が強まっています。
また給与条件だけでなく将来的なキャリアパス、生活の安定性、職場の人間関係を重視する応募者が増加しているため、自社の職種と関連する外国人コミュニティに参加して求職時の不安要素や企業選択の決定要因について直接ヒアリングを行い、そこで得られたインサイトをサイト設計に反映させることが成功の鍵となります。
企業が外国人向け求人サイトを作るメリット
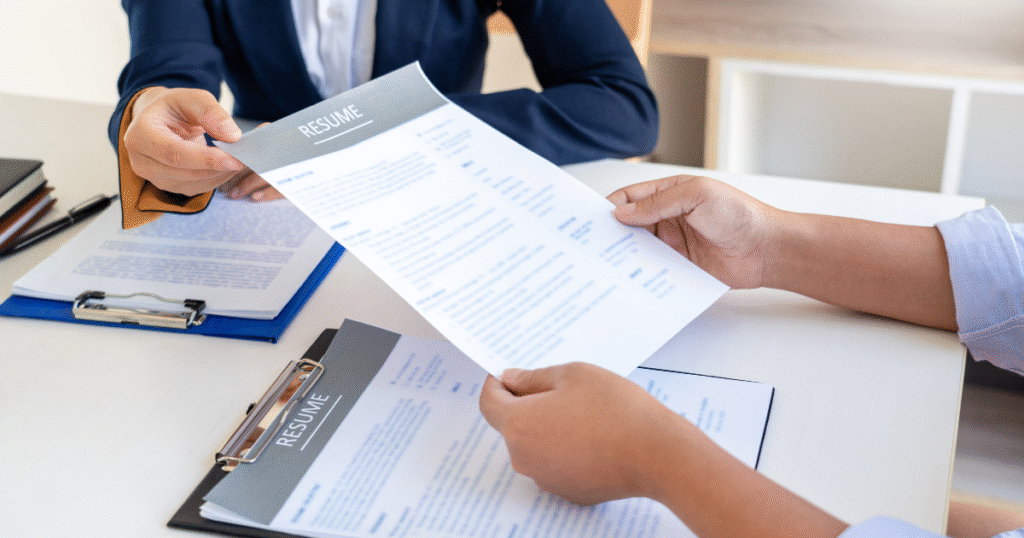
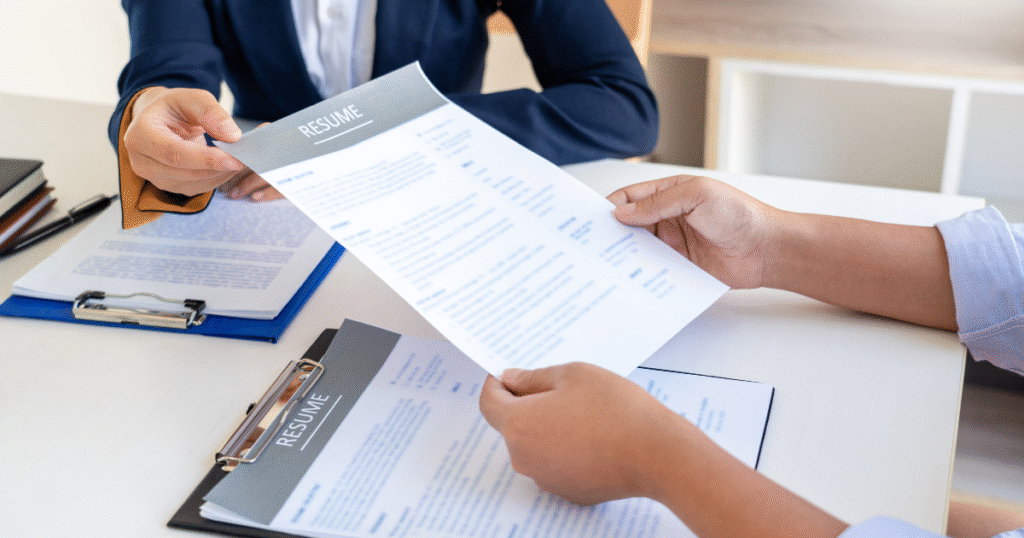
この章では、中小企業が自社で外国人向け求人サイトを制作することで得られる具体的なメリットについて紹介します。
2025年現在、外国人採用・管理支援サービス市場は前年比34.8%増の2,467億円規模に拡大し、多くの企業が外国人材の確保に注力しています。



既存の求人ポータルやSNSでは応募が伸び悩む中、自社サイトを構築することで競合との差別化を図り、採用成功率の向上が期待できます。
企業が外国人向け求人サイトを作るメリットには主に以下の内容があります。
- 自社ブランディング強化による応募率と内定受諾率の向上
- 応募者データの自社蓄積と継続的な再アプローチ
- 媒体費最適化による長期的な採用コスト削減
- 計測データに基づく継続的な改善サイクルの構築
- 言語・職種・地域への柔軟な特化戦略の実現
メリット(1)自社ブランディング強化で応募率と内定受諾率が上がる
自社で外国人向け求人サイトを運営することで、企業文化や職場環境を詳細に伝えられるようになり、応募者の期待値調整が可能となり応募率と内定受諾率が向上します。
外国人求職者は日本での就労に対して言語面、文化面、生活面での不安を抱えており、単純な求人情報だけでは企業選択の判断材料として不足しています。
YOLO WORKやGuidableなどの求人ポータルでは限られた文字数と画像でしか企業の魅力を伝えられませんが、自社サイトでは無制限に情報発信が可能で、応募者の不安を事前に解消できます。
外国人社員による母国語でのインタビュー動画、寮の内部写真、実際の作業風景、日本人社員との交流シーンを掲載することで、入社後のミスマッチによる早期離職率も削減できます。
メリット(2)応募者データを自社で蓄積し再アプローチできる
自社サイトからの応募者データは企業の重要な資産となり、長期的な人材確保戦略の基盤として活用できます。
外部求人媒体を利用した場合、応募者情報は媒体側が管理するため、契約終了後は再コンタクトが困難になります。
しかし自社サイトであれば応募者の基本情報、スキル、希望条件、応募経緯などの詳細データを自社で永続的に保有でき、将来的な人材確保に活用できます。
特に外国人材は転職頻度が高く、数年後に再び転職を検討するケースが多いため、継続的な関係構築が重要です。



不採用となった応募者にも定期的にメルマガで会社の近況や新規プロジェクト情報を配信することで、初回不採用者の再応募や採用された社員からの紹介応募の増加が期待できます。
メリット(3)媒体費の最適化で長期的な採用コストを削減できる
初期投資は必要ですが、自社サイト運営により中長期的に採用コストを大幅に削減することが可能です。
外部求人媒体への掲載費は継続的に発生し、年間で数十万円から数百万円のコストがかかります。一方、自社サイトは初期制作費50万円から300万円、月額運用費1万円から5万円で運営でき、2年から3年で投資回収が可能です。
さらに自社サイトはSEO対策により検索エンジンからの自然流入を獲得でき、広告費に依存しない持続的な集客が実現できます。
年間120万円の求人媒体費を支払っていた企業が200万円で自社サイトを構築後、SEO対策と多言語対応により検索経由での応募が月10件に増加し、2年目以降は媒体費が不要となる事例も見られます。
メリット(4)計測データに基づく継続改善が可能になる
自社サイトではGoogle AnalyticsやSearch Consoleによる詳細なデータ分析が可能で、継続的な改善により採用効果を最大化できます。
外部求人媒体では提供される分析データが限られており、どのコンテンツが応募につながったかを詳細に把握することが困難です。
しかし自社サイトでは訪問者の行動、コンテンツの閲覧状況、応募に至るまでの導線、離脱ポイントなどを詳細に分析でき、データに基づく改善施策を実施できます。
ベトナム語ページの直帰率が高いことを発見し、翻訳の質を改善することでベトナム人応募者数を2.5倍に増加させたり、スマートフォンからのアクセスが80%を占めることが判明してモバイル最適化により応募完了率を45%向上させたりする事例があります。
メリット(5)言語・職種・地域へ柔軟に特化できる
自社サイトでは採用戦略の変更に応じて、ターゲットとする言語、職種、地域を柔軟に調整でき、市場環境の変化に迅速に対応できます。
2025年現在、外国人労働者の構成はベトナム人24.8%、中国人17.8%、フィリピン人10.7%となっており、業種や地域によって求める人材の国籍が変化しています。
外部求人媒体では媒体側の仕様に制約されますが、自社サイトであれば市場動向や採用ニーズに合わせて言語対応や職種カテゴリを自由に追加、変更できます。
当初ベトナム人エンジニア採用を目的として自社サイトを構築していた企業が、市場分析によりインド人エンジニアの需要増を確認し、3ヶ月でヒンディー語、英語ページを追加してインド工科大学出身者向けのコンテンツを制作した結果、6ヶ月で5名のインド人エンジニアの採用に成功した事例もあります。
企業が外国人向け求人サイトを作るデメリット
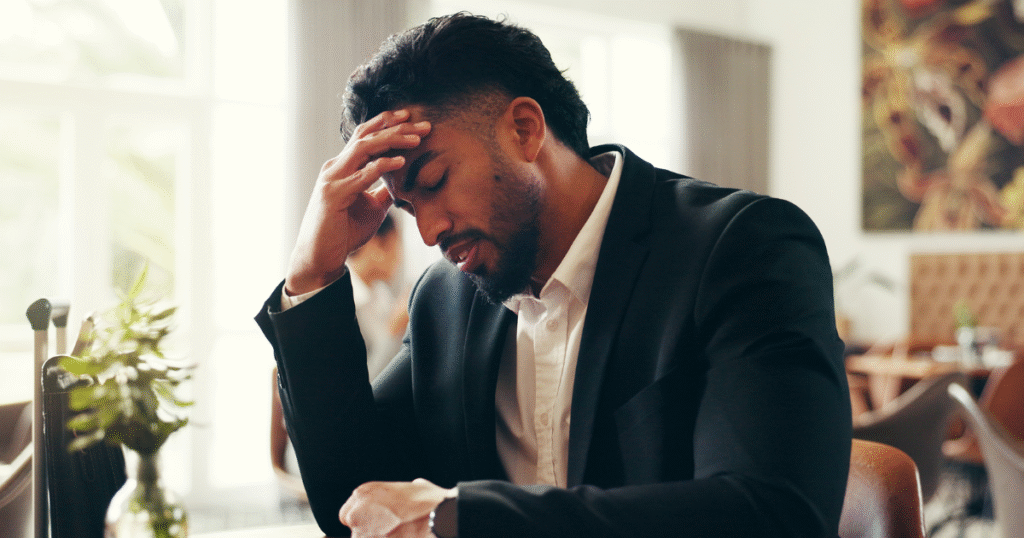
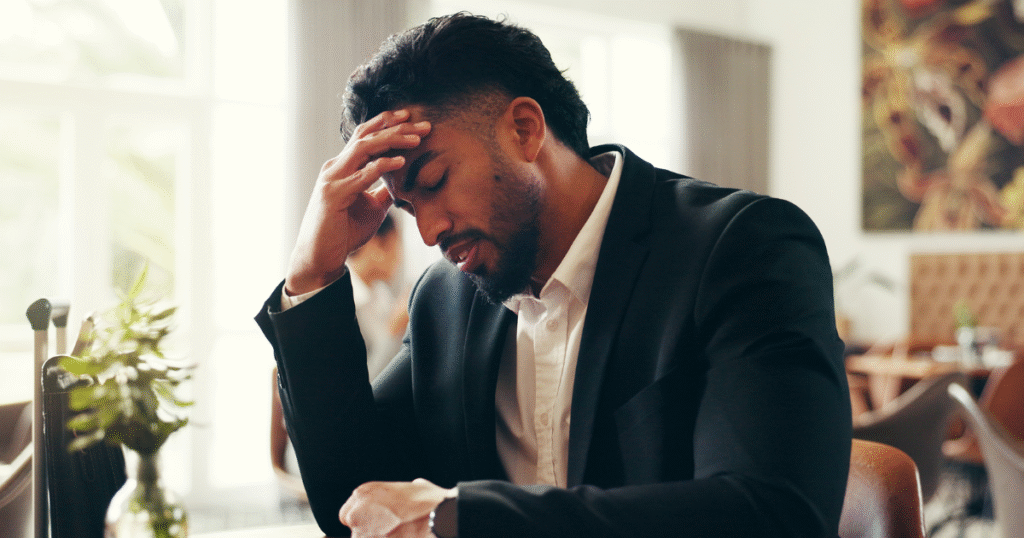
この章では、中小企業が外国人向け求人サイトを制作する際に生じる具体的なデメリットや課題について紹介します。
自社サイト構築には多くのメリットがある一方で、初期投資コスト、運用負荷、技術的な課題など、事前に理解しておくべきリスクも存在します。



特に限られた予算とリソースで運営する中小企業にとって、これらのデメリットを軽視すると、期待した成果が得られないだけでなく、継続的な運営が困難になる可能性があります。
企業が外国人向け求人サイトを作るデメリットには主に以下の内容があります。
- 初期開発費と運用・保守の継続的な工数負担
- 集客施策の不備による応募数の伸び悩み
- 法令遵守と表現における企業責任の発生
- 多言語コンテンツの品質管理と更新体制の複雑化
- セキュリティ対策と個人情報保護への対応義務
デメリット(1)初期開発費と運用・保守の工数がかかる
外国人向け求人サイトの構築と運営には初期費用50万円から300万円、月額運用費1万円から5万円の継続的な投資が必要で、社内リソースも相当程度消費されます。
自社サイト構築は一度作れば完了するものではなく、WordPressやCMSのアップデート、セキュリティパッチの適用、サーバー管理、バックアップ作業、コンテンツ更新などの定常業務が発生します。
これらを外部委託する場合は月額数万円、社内で対応する場合も担当者の工数が月10時間から20時間程度必要になり、予想以上の運用負荷となるケースが多く見られます。
初期費用だけでなく3年間の運用費用を含めた総コストを事前に算出し、社内での運用体制または外部委託費用を予算に組み込んでから着手することが重要です。
デメリット(2)集客施策が弱いと応募が集まりにくい
自社サイトは構築しただけでは誰にも見つけてもらえず、SEO対策、SNS運用、広告配信などの集客施策に専門知識と継続的な努力が必要になります。
YOLO WORKやGuidableなどの既存求人媒体は既に多くの外国人求職者に認知されているため掲載すれば一定の閲覧が見込めますが、自社サイトは検索エンジンでの上位表示、外国人コミュニティでの認知拡大、SNSでの継続的な情報発信などを自力で行う必要があります。
これらの施策が不十分だとサイトへのアクセス数が月数十件程度に留まることがあり、300万円で構築したサイトでも月間アクセス数50件、3ヶ月で応募数2件という事例も報告されています。
デメリット(3)法令・表現のコンプライアンス責任が生じる
自社サイトの求人情報や表現について、労働関連法令、広告表示規制、差別禁止規定などのコンプライアンス責任を企業が直接負うことになります。
外部求人媒体では媒体側が基本的な法令チェックを行いますが、自社サイトでは求人内容の適法性、表現の適切性、外国人に対する差別的記述の回避などを企業が自己責任で管理する必要があります。
特に外国人雇用では在留資格の正確な記載、労働条件の明示、最低賃金の遵守など専門知識が必要な領域が多く、不適切な記載により行政指導やトラブルが発生するリスクがあります。
求人内容の作成前に社会保険労務士や外国人雇用に詳しい専門家への相談を行い、定期的な法令適合性チェックを実施する体制の構築が必要です。
デメリット(4)多言語での品質管理と更新体制の維持が難しい
複数言語でのサイト運営は翻訳の品質管理、文化的な配慮、各言語での同期更新などの複雑な運用体制が必要で、維持コストが想定以上に高くなる傾向があります。
機械翻訳だけでは不自然な表現や文化的に不適切な内容が生まれやすく、ネイティブチェックが不可欠ですが定期的な翻訳者の確保とコストが継続的に発生します。
また日本語での情報更新時に全言語での同期更新を忘れがちで、言語によって情報の鮮度に差が生まれ求職者に不信感を与える可能性があります。
対応言語数を当初は2言語から3言語に絞り、翻訳チェック体制と更新フローを確立してから段階的に言語数を増やす戦略を取ることが重要です。
デメリット(5)セキュリティや個人情報保護への対応が必要
応募者の個人情報を取り扱う求人サイトでは、個人情報保護法やGDPR準拠、サイバー攻撃対策、データ漏洩防止などの高度なセキュリティ対策が義務付けられます。
外部求人媒体では媒体運営会社がセキュリティ対策を担いますが、自社サイトでは応募者の氏名、連絡先、経歴、在留資格情報などの機微な個人情報を企業が直接管理することになります。
これらの情報漏洩は企業の信用失墜だけでなく法的責任も発生するため、SSL証明書の導入、定期的なセキュリティ診断、アクセスログ管理、データバックアップ体制などの技術的対策が必要です。
サイト構築時からセキュリティ対策を組み込み、定期的な脆弱性診断の実施や個人情報取扱規程の整備を行うことが不可欠です。
外国人向け求人サイトの作り方(手順)
-1024x538.png)
-1024x538.png)
この章では、中小企業が外国人向け求人サイトを成功させるために必要な8つの手順について詳しく紹介します。



2025年現在、外国人労働者数は約230万人に達し、特定技能制度の運用改善も4月に施行されるなど、外国人採用市場は急速に拡大しています。



しかし、限られた予算で最大の成果を得るためには、戦略的かつ体系的なアプローチが不可欠です。
適切な手順を踏まずに制作を開始すると、コストオーバーや期待した応募効果が得られないリスクが高まります。
外国人向け求人サイトの作り方の手順には主に以下の内容があります。
- 採用KPIの設定とペルソナ設計・要件定義
- 情報設計と応募導線・コンテンツの骨子策定
- CMS/ATSの選定と多言語設計
- デザイン制作とレスポンシブ・表示速度最適化
- 応募フォーム・面接予約・チャット機能の実装
- アクセス解析とイベント計測の設定
- 表現・個人情報・在留資格の法務チェック
- 公開後の運用・A/Bテスト・改善サイクル
手順(1)採用KPIの設定とペルソナ設計・要件定義を行う
サイト制作前にSMARTの法則に基づいた採用KPIを設定し、ターゲットとする外国人材の詳細なペルソナを作成することでプロジェクト全体の方向性と成功基準を明確化します。
明確な目標設定なしにサイト制作を始めると採用成果に直結しない可能性があります。
2025年現在、ベトナム人が24.8%、中国人が17.8%、フィリピン人が10.7%と外国人労働者の上位を占めており、国籍、在留資格、職種によって求める情報や応募行動が大きく異なるため詳細なペルソナ設計が不可欠です。
KGI、KPIを数値で設定し、ペルソナシートには国籍、年齢、在留資格、日本語レベル、職歴、来日動機、生活状況、不安要素まで具体化して制作チーム全体で共有し、すべての判断基準として活用することが重要です。
手順(2)情報設計(IA)と応募導線・コンテンツの骨子を固める
外国人求職者が抱える不安を段階的に解消し、応募まで迷わず到達できるよう3クリック以内の情報設計と明確な応募導線を構築します。
外国人求職者は言語面、文化面、生活面での不安が大きく、一般的な求人サイトとは異なる情報ニーズがあります。
企業情報から職種詳細、サポート制度、先輩インタビュー、応募という段階的な信頼構築が必要で、情報の配置順序や導線設計が応募率に直結します。
サイトマップは会社概要、職種紹介、働く環境・サポート、社員インタビュー、募集要項、応募フォームの6大カテゴリを基本とし、各ページに明確なCTAを設置することで、ユーザーの心理的段階に応じた情報提供順序を意識した設計を行うことが成功の鍵となります。
手順(3)CMS/ATSの選定と多言語設計(URL・hreflang)を決める
WordPress+多言語プラグインまたはWixなどのクラウドサービスを活用し、SEOに配慮したURL構造とhreflang設定により各言語での検索エンジン最適化を実現します。



多言語サイトの技術的基盤は後から変更することが困難で、初期選択が長期的な運用コストと集客効果を左右します。
2025年現在、WPML、TranslatePress、Weglotなどの多言語化プラグインが進化し、中小企業でも本格的な多言語SEOが実現可能になっています。
予算50万円以下はWix多言語機能、予算100万円以上はWordPress+WPML、予算重視はWordPress+TranslatePress無料版から開始することを推奨します。
URL構造はディレクトリ型を採用し、各言語ページのhreflang設定を必ず実装することが重要です。
手順(4)デザイン制作とレスポンシブ・表示速度の最適化を実施する
外国人求職者の70%がスマートフォンでアクセスすることを前提として、モバイルファーストのレスポンシブデザインと3秒以内の表示速度を実現します。
外国人求職者は移動中や休憩時間にスマートフォンで求職活動を行うケースが多く、PC向けデザインでは応募完了率が大幅に低下します。
またGoogleの検索順位算定でもページ表示速度が重要な要素となっているためSEO効果にも直結します。
デザイン制作はスマートフォン画面から開始し、タブレット、PCの順で拡張するモバイルファーストアプローチを採用することが重要です。
Google PageSpeed Insightsで表示速度90点以上を目標とし、画像のWebP形式採用、不要なプラグイン削減、CDNの活用を実施しましょう。
手順(5)応募フォーム・面接予約・チャットなど機能を実装する
入力項目を最小限に絞った段階的な応募フォーム、オンライン面接予約システム、多言語チャットサポート機能により応募から面接まで一貫したユーザー体験を提供します。
外国人求職者は日本の就職活動に不慣れで、複雑な応募プロセスは大きな障壁となります。
特に履歴書の形式や面接の進め方について不安を抱えているため、段階的なサポートと柔軟な対応が応募完了率と面接参加率を大幅に向上させます。
応募フォームは簡易応募から詳細情報、最終確認の3段階設計とし、面接予約はCalendlyやAirReserveなどのツールを活用することをおすすめします。
多言語対応のFAQページと可能であればSlackやChatworkを使ったリアルタイムサポート体制を構築することが重要です。
手順(6)アクセス解析とイベント計測(GA4・タグ)を設定する
Google Analytics 4とGoogle Tag Managerを活用し、サイト訪問から応募完了まで全プロセスのデータ計測体制を構築し継続的な改善の基盤を整備します。



外国人向け求人サイトは一般的な求人サイトとは異なるユーザー行動パターンを示すため、データに基づいた改善が不可欠です。
どの言語のページが最も効果的か、どのコンテンツが応募につながるか、離脱ポイントはどこかを定量的に把握することでROIの高い改善施策を継続的に実行できます。
GA4でページビュー、応募開始、応募完了、面接予約をコンバージョン設定し、Google Search Consoleと連携して検索キーワードも分析します。
月次レポートを作成し、言語別、デバイス別、流入経路別の詳細データを継続的にモニタリングする体制の構築が必要です。
手順(7)表現・個人情報・在留資格の法務チェックを行う
労働関連法令、個人情報保護法、外国人雇用に関する法規制に準拠し、差別的表現の回避と適切な在留資格情報の記載によりコンプライアンスリスクを最小化します。
自社サイトでは求人内容の法的責任を企業が直接負うため、不適切な記載により行政指導やトラブルが発生するリスクがあります。



特に2025年4月の特定技能制度運用改善に伴い、在留資格に関する正確な情報提供がより重要になっています。
公開前に社会保険労務士による法令適合性チェックを必ず実施し、特に在留資格要件、労働条件、最低賃金の記載内容を重点的に確認することが重要です。
表現ガイドラインを策定し、国籍による差別的記述を避け、多様性を尊重する内容とすることが求められます。
手順(8)公開後の運用・A/Bテスト・改善サイクルを回す
サイト公開後は月次データ分析、四半期ごとのA/Bテスト、年次での大幅改善を継続的に実施し、採用成果の最大化を図るPDCAサイクルを確立します。
外国人採用市場は急速に変化しており、求職者のニーズや行動パターンも変わり続けます。
また競合他社の参入や法制度の変更もあるため、一度作って終わりではなく継続的な改善が成果を維持、向上させる唯一の方法です。
月次でKPIである訪問者数、応募数、コンバージョン率を確認し、四半期ごとに応募フォーム、コンテンツ、多言語表現のA/Bテストを実施します。
年1回は競合分析と市場トレンド調査を行い、大幅なリニューアルの必要性を検討する運用体制を構築することが長期的な成功につながります。
多言語対応やスマホ最適化はどう進める?


この章では、外国人向け求人サイトで最も重要な技術的課題である多言語対応とスマートフォン最適化の具体的な実装方法について紹介します。



2025年現在、外国人求職者の70%がスマートフォンでアクセスし、ベトナム人24.8%、中国人17.8%、フィリピン人10.7%と多様な国籍の人材が求職活動を行っているため、技術的な基盤整備が採用成果に直結します。



単純に翻訳しただけのサイトや、PC向けに設計されたサイトでは応募完了率が大幅に低下するリスクがあります。
多言語対応やスマホ最適化を成功させるには主に以下の内容があります。
- URL構造とhreflangによる多言語SEO最適化
- 自動翻訳とネイティブレビューを組み合わせた運用体制
- モバイル応募完了率向上のためのUI/UX設計
- アクセシビリティと文化的配慮を反映した表現ガイドライン
- ソーシャルログインとメッセージアプリ連携による利便性向上
ポイント(1)URL構造とhreflangで多言語SEOを担保する
多言語サイトのSEO効果を最大化するためには、ディレクトリ型URL構造とhreflangタグの適切な設定により各言語での検索エンジン最適化を実現する必要があります。
検索エンジンが各言語ページの対象地域を正しく認識できないと、日本語で検索した外国人に英語ページが表示される問題が発生します。
2025年現在のGoogle検索アルゴリズムではhreflangタグによる言語、地域の明示が検索順位に大きく影響するため技術的な設定が集客効果を左右します。
予算50万円以下はWixの多言語機能、予算100万円以上はWordPressとWPMLを推奨し、URL構造は必ずディレクトリ型を採用してGoogle Search Consoleで各言語の検索パフォーマンスを定期的に確認することが重要です。
ポイント(2)自動翻訳+ネイティブレビューの運用体制を整える
DeepLなどの高精度AI翻訳ツールを基盤として、重要コンテンツはネイティブスピーカーによるレビューを行うハイブリッド翻訳体制が品質とコストのバランスを最適化します。
全てをプロ翻訳者に依頼すると1言語あたり月5万円以上のコストが発生しますが、機械翻訳のみでは文化的に不適切な表現や業界専門用語の誤訳により企業の信頼性が損なわれます。
特に求人サイトでは労働条件や福利厚生の説明で誤解を与えると応募者とのトラブルに発展する可能性があります。
DeepL Proを基本ツールとし、企業理念、募集要項、労働条件は必ずネイティブチェックを実施して更新頻度の高いコンテンツは機械翻訳で対応する体制構築が効果的です。
ポイント(3)モバイルで応募完了率を高めるUI/UX(入力削減・保存機能)
スマートフォンでの応募完了率を最大化するため、入力項目の段階的収集、途中保存機能、ワンタップ入力支援によりモバイルファーストのユーザー体験を提供します。
外国人求職者の70%がスマートフォンでアクセスするにも関わらず、多くの求人サイトはPC向けの長いフォームをそのまま流用しているため入力途中での離脱率が50%以上になっています。
特に外国人は日本語入力に時間がかかるため、入力項目数と応募完了率は反比例の関係にあります。
初回応募は3項目以内に限定し、簡易応募から詳細面談、最終確認の3段階プロセスを採用してHTML5のautofill属性を活用した自動入力支援と48px以上のタップしやすいボタンサイズを実装することが重要です。
ポイント(4)アクセシビリティと文化的配慮の表現ガイドラインを用意する
多様な文化的背景を持つ外国人に配慮し、差別的表現の回避、宗教や文化への理解、アクセシビリティ対応を含む包括的な表現ガイドラインを策定して運用します。
特定の国籍に対する偏見を示唆する表現は無意識の差別として受け取られ、企業イメージの悪化や優秀な人材の応募敬遠につながります。
また色覚多様性への配慮やイスラム教の祈祷時間への理解など、多様性に配慮した表現が求職者の安心感と信頼感を大きく向上させます。
多様性を歓迎、文化的背景を尊重といったポジティブな表現を使用し、特定国籍への偏見を示唆する文言は完全に排除してWCAG 2.1のAAレベル準拠を目標とした実装が必要です。
ポイント(5)ソーシャルログイン・メッセージアプリ連携を導入する
FacebookやGoogleアカウントでのソーシャルログイン、LINE、WhatsApp、Zaloなどのメッセージアプリ連携により外国人求職者にとって馴染みのあるプラットフォームからのスムーズな応募とコミュニケーションを実現します。



外国人求職者は日本のウェブサイトでの新規アカウント作成に不安を感じる傾向があり、既に使い慣れたソーシャルアカウントでのログインを好みます。
また国籍によって利用するメッセージアプリが異なり、ベトナム人はZalo、フィリピン人はFacebook Messengerなど現地で主流のツールに対応することで応募ハードルを大幅に下げられます。
Google、Facebook、LINEのソーシャルログインを基本実装し、主要ターゲット国の主流メッセージアプリとの連携を段階的に追加することが効果的です。
外国人向け求人サイトのSEO対策は何をすべき?


この章では、外国人向け求人サイトが検索エンジンで上位表示を獲得し、ターゲットとする外国人求職者に効率的にリーチするためのSEO対策について詳しく紹介します。



2025年現在、外国人労働者数は約230万人に達し、多くの企業が外国人材確保に注力している中、検索エンジンでの視認性向上は自社サイトの成功に直結します。



単純にサイトを作っただけでは、YOLO WORKやGuidableなどの大手求人媒体に埋もれてしまい、せっかくの投資が無駄になるリスクがあります。
外国人向け求人サイトのSEO対策で重要なポイントには主に以下の内容があります。
- 在留資格・職種・地域を組み合わせたキーワード設計
- JobPosting構造化データによるリッチリザルト対応
- 多言語での求人詳細・企業情報・FAQ充実化
- SNS・被リンク・口コミによる外部流入強化
- インデックス管理と重複コンテンツ対策の実施
SEO(1)キーワード設計:在留資格×職種×地域でカテゴリを作る
外国人求職者の検索行動に合わせて、在留資格、職種、地域の3軸を組み合わせたロングテールキーワード戦略により競合の少ないニッチ領域で上位表示を狙います。
外国人求職者は製造業求人といった一般的なキーワードではなく、特定技能製造業東京や技人国エンジニア大阪など、自身の在留資格と希望条件を具体的に組み合わせて検索する傾向があります。
2025年現在、特定技能制度の運用改善により在留資格に関する検索需要がさらに増加しています。
Google Keyword PlannerとUbersuggestを使用して、特定技能プラス職種プラス地域、技能実習プラス業種プラス都道府県のパターンで月間検索数10回から100回程度のキーワードを洗い出し、それぞれに専用ページを作成して内部リンクで関連ページ同士を連携させる構造の構築が効果的です。
SEO(2)構造化データJobPostingを実装しリッチリザルトを狙う
Schema.orgのJobPosting構造化データを実装することで、Google検索結果に求人情報が豊富に表示されるリッチリザルトを獲得しクリック率の向上を図ります。
構造化データを適切に実装した求人ページは、検索結果に職種名、給与、勤務地、雇用形態が視覚的に表示され、通常のテキストリンクと比較して3倍から5倍のクリック率を獲得できます。
特に外国人求職者は限られた日本語能力で効率的に情報収集したいため、一目で条件が分かるリッチリザルトを好む傾向があります。
構造化データには最低限jobTitle、baseSalary、jobLocation、employmentType、description、qualificationsを含めて、Google構造化データテストツールで検証後に実装することが重要です。
SEO(3)求人詳細・企業情報・FAQを多言語で充実させる
求人詳細ページ、企業情報、FAQ等のコンテンツを多言語で充実させることで各言語での検索流入を拡大しサイト全体のドメインオーソリティを向上させます。
Google検索では、ユーザーの検索言語とページ内容の言語が一致している場合に上位表示されやすくなります。
外国人求職者は母国語や英語での検索も行うため、日本語のみのサイトでは機会損失が発生します。
また詳細で有用なコンテンツは滞在時間を延ばし、SEO評価の向上につながります。
優先順位は求人詳細から企業情報、福利厚生、FAQ、ブログの順で多言語化を実施し、各言語で月1回以上の新規コンテンツ追加を継続することが重要です。



外国人が知りたい日本の労働法規やビザ更新手続きガイドなど検索需要の高いテーマでSEOコンテンツを充実させましょう。
SEO(4)SNS・被リンク・口コミなど外部流入を強化する
Facebook、LinkedIn、業界団体サイトからの被リンク獲得と外国人コミュニティでの口コミ拡散によりSEOに有利な外部流入と権威性向上を実現します。
Googleのアルゴリズムでは外部サイトからのリンクとソーシャルシグナルがサイトの権威性評価に影響します。
特に外国人採用分野では同業他社との差別化が困難なため、外部からの信頼性指標が検索順位を左右する重要な要素となります。
業界団体への加盟、プレスリリース配信、外国人向けイベント協賛により質の高い被リンクを獲得し、FacebookやLinkedInでの定期的な投稿と採用実績のある外国人社員によるリアルな口コミ投稿を促進する仕組みを構築することが効果的です。
月5件以上の自然なソーシャルシェアを目標として設定しましょう。
SEO(5)インデックス管理と重複コンテンツ対策を行う
多言語サイト特有の重複コンテンツ問題を解決し、適切なインデックス管理により検索エンジンからのペナルティを回避しつつ各言語ページの評価を最大化します。
同一内容を複数言語で提供する多言語サイトは、検索エンジンに重複コンテンツと判定され検索順位が大幅に下がるリスクがあります。
また翻訳の質が低い言語ページがサイト全体の評価を下げる可能性もあるため戦略的なインデックス管理が必要です。
Google Search Consoleでインデックス状況を週次確認し、重複コンテンツ警告が出た場合はcanonicalタグで正規化を実施します。
翻訳品質の低いページは一時的にnoindexし品質改善後に段階的に公開して、XMLサイトマップで各言語の更新頻度を適切に設定しクロール効率を最適化することが重要です。
掲載媒体と集客チャネルはどう使い分ける?


この章では、自社で外国人向け求人サイトを構築した後、効果的な集客を実現するための媒体活用と集客チャネルの使い分け戦略について紹介します。



2025年現在、外国人採用・管理支援サービス市場は前年比34.8%増と急成長しており、多くの企業が外国人材確保に注力している中、自社サイト単体では十分な認知度獲得が困難です。



せっかく質の高い求人サイトを構築しても、ターゲットとなる外国人求職者に届かなければ投資効果は得られません。
効果的な集客を実現するためには主に以下の内容があります。
- 外国人専門求人サイトへの連携・転載による露出拡大
- ハローワーク・公的機関の活用による信頼性向上
- SNS・コミュニティでの情報発信とコミュニティ参加
- 人材紹介会社・教育機関・送り出し機関との連携
- 検索広告・SNS広告による自社サイトへの誘導強化
媒体(1)外国人専門求人サイトへ連携・転載し露出を拡大する
YOLO WORK、WORK JAPAN、Guidable Jobs、NINJAなどの外国人専門求人媒体に求人を掲載し、自社サイトへの誘導導線を設計することで認知拡大と詳細情報提供の役割分担を実現します。
外国人求職者の多くは既に認知度の高い専門求人媒体から仕事探しを始めるため、自社サイト単体では発見されにくい状況があります。
これらの媒体は情報掲載量に制限があるため、認知獲得は外部媒体、詳細理解と信頼構築は自社サイトという役割分担が最も効率的です。
主要3から4媒体に同一求人を掲載し、各媒体の求人詳細欄に自社サイトへの誘導文言を統一して記載することで、月次で各媒体からの流入数と応募率を比較分析しROIの高い媒体に予算を集中投下する戦略的運用が可能になります。
媒体(2)ハローワーク・公的機関を活用して信頼性を高める
ハローワーク、外国人雇用サービスセンター、JETROなどの公的機関を活用することで企業の信頼性を高めつつ、無料または低コストでの求人露出を実現します。
外国人求職者は日本での就労に不安を抱えており、公的機関からの情報提供は高い信頼性を持って受け取られます。
特に在留資格やビザ関連の不安が大きいため、厚生労働省系の機関からの求人情報は安心感を提供します。
また、これらの機関は基本的に無料で利用でき中小企業にとってコストメリットが大きいです。
ハローワークインターネットサービスでの求人公開を基本とし、外国人雇用に関する各種研修やセミナーへの参加実績を自社サイトで積極的にアピールして厚生労働省認定企業などのバッジを活用した信頼性の視覚的表現が効果的です。
媒体(3)SNS・コミュニティ(Facebook・LINE 等)で情報発信する
Facebook、LINE、YouTube等のSNSプラットフォームで各国籍の外国人コミュニティに参加し、有益な情報発信を通じて自然な形で自社の認知度向上を図ります。
外国人求職者の情報収集行動は同国籍者が集まるSNSコミュニティでの口コミや情報交換が中心となっています。
ベトナム人はFacebookとZalo、フィリピン人はFacebook、中国人はWeChatというように国籍によって利用プラットフォームが異なるためターゲットに応じた選択が必要です。
直接的な求人広告よりも有益な情報提供を通じた信頼関係構築が効果的で、主要ターゲット国の大型コミュニティに参加して業界情報、生活情報、法律情報等の有益コンテンツを定期投稿し、信頼関係構築後に自社サイトを自然な形で紹介する戦略が重要です。
媒体(4)人材紹介会社・学校・送り出し機関と連携する
外国人専門の人材紹介会社、日本語学校、現地の送り出し機関との連携により質の高い候補者への直接アプローチと継続的な人材パイプライン構築を実現します。



人材紹介会社や教育機関は求職者の詳細情報であるスキル、人柄、日本語能力等を把握しており企業のニーズとのマッチング精度が高いです。
また送り出し機関との連携は来日前からの関係構築を可能にし、長期的な人材確保戦略として有効です。特に2025年現在、特定技能制度の運用改善によりこれらの機関の重要性が高まっています。
ターゲットとする国の主要送り出し機関への企業情報提供と国内の外国人専門人材紹介会社との継続的な関係構築、セミナーや説明会での自社サイト紹介が効果的です。
媒体(5)検索広告・SNS広告で自社サイトへの誘導を強化する
Google広告、Facebook広告、YouTube広告を活用し外国人求職者の検索行動とSNS利用パターンに合わせたターゲティング広告により自社サイトへの効率的な誘導を実現します。
オーガニック検索での上位表示には時間がかかるためサイト公開初期は有料広告による集客が不可欠です。
外国人求職者は特定技能製造業東京やconstruction job Japan visaといった具体的なキーワードで検索するため、適切なキーワード選定により競合の少ない領域で効率的にアプローチできます。
またSNS広告では国籍、年齢、興味関心での精密なターゲティングが可能で、初期3ヶ月はGoogle広告で検索キーワード広告を中心に実施し効果的なキーワードを特定後にSNS広告を追加する戦略が効果的です。
法務・コンプライアンスで注意すべきこと
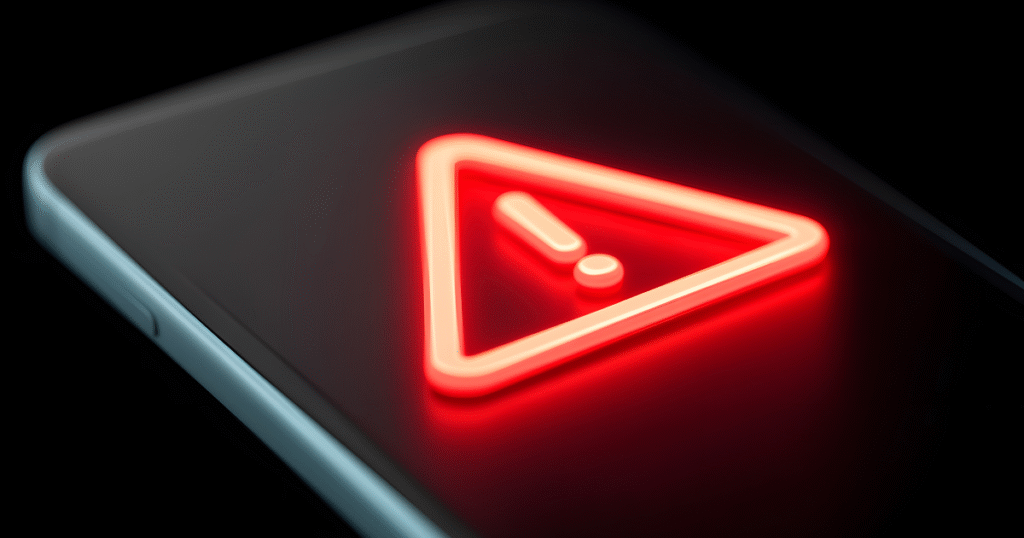
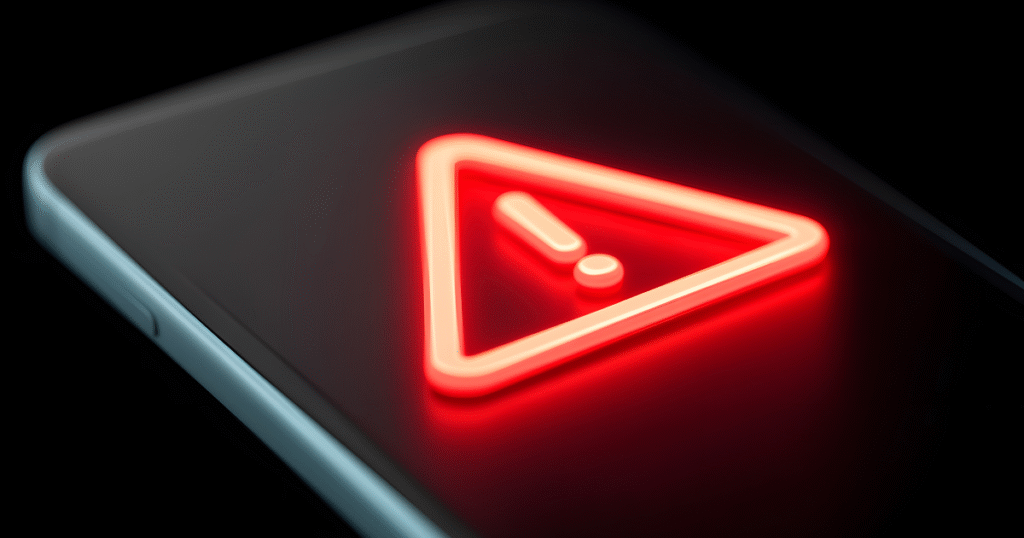
この章では、外国人向け求人サイト運営において企業が直面する法的リスクとコンプライアンス対応について詳しく紹介します。



2025年現在、特定技能制度の運用改善や個人情報保護法の強化により、外国人採用サイトに求められる法的要件が複雑化しています。



自社サイト運営では、外部求人媒体と異なり企業が直接法的責任を負うため、適切な対策を講じなければ行政指導や損害賠償請求のリスクが発生します。
単純な法律違反だけでなく、文化的配慮を欠いた表現により企業イメージが損なわれる事例も増加しています。法務・コンプライアンスで注意すべき点には主に以下の内容があります。
- 在留資格と就労範囲の適正な確認フロー構築
- 差別的・優遇的表現の回避と多様性配慮の表記ルール
- 労働関連法規・職業安定法・個人情報保護法の遵守
- Cookie規制・セキュリティ・著作権に関するリスク対応
注意点(1)在留資格と就労範囲の確認フローをサイトに組み込む
求人情報に対象となる在留資格を明確に記載し、応募段階で在留資格の適法性を確認するフローを構築することで不法就労助長罪などの重大な法的リスクを回避します。
外国人の就労は在留資格によって厳格に制限されており、企業が適切な確認を怠ると出入国管理法違反により3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
2025年4月の特定技能制度運用改善により在留資格の確認要件がより厳格化されているためサイト設計段階からの対策が不可欠です。
求人詳細ページには必ず対象在留資格を具体的に記載し、応募フォームに在留資格確認項目を必須設定して社会保険労務士または行政書士との顧問契約により月1回の在留資格適合性チェック体制を構築することが重要です。
注意点(2)差別的・優遇的表現の回避と表記ルールを徹底する
国籍、性別、宗教等による差別的表現を完全に排除し、多様性を尊重するポジティブな表記ルールを策定、運用することで人権侵害リスクと企業イメージ毀損を防止します。
労働施策総合推進法や職業安定法では国籍等を理由とする差別的取扱いが禁止されており、求人広告での不適切な表現は行政指導や社会的批判の対象となります。
またSNS等での拡散により企業の社会的信用が長期間にわたって損なわれるリスクがあります。
特に外国人採用分野では無意識のバイアスによる表現ミスが発生しやすいため明文化されたガイドラインが必要です。
国籍や文化的背景を問わず、多様性を尊重する職場等のポジティブ表現を統一使用し、求人情報公開前には必ず人事担当者と法務担当者による二重チェックを実施することが求められます。
注意点(3)労働法・職安法・個人情報保護法の遵守を確認する
労働基準法、職業安定法、個人情報保護法の関連規定を遵守し、求人情報の適正表示と個人情報の適切な管理体制を構築することで法的トラブルを未然に防止します。
求人サイト運営には複数の法律が適用され、違反した場合は罰金、業務停止命令、損害賠償請求等の重大な制裁を受ける可能性があります。
特に2022年4月施行の改正個人情報保護法では個人データの漏えい等に関する報告義務や本人通知義務が強化されており適切な管理体制の構築が必須です。
外国人の個人情報は在留資格等の機微情報を含むためより高度な管理が求められます。



社会保険労務士による求人情報の法的適合性チェックを月1回実施し、個人情報保護責任者を任命して年2回の社内研修を開催することが重要です。
注意点(4)Cookie・セキュリティ・著作権のリスクに対応する
Cookie利用規約の適正表示、サイバーセキュリティ対策の強化、第三者著作物の適法利用によりデジタル分野特有の法的リスクを包括的に管理します。
2025年現在、Cookie規制の強化によりユーザーの明示的同意なしにCookieを利用することは法的リスクとなっています。
またサイバー攻撃による個人情報流出は企業の社会的信用を著しく損ない復旧に数百万円から数千万円の費用が発生します。
さらに画像や文章の著作権侵害は損害賠償請求の原因となるため適切な権利処理が必要です。
Cookie利用に関する明確な同意取得システムを導入し、セキュリティ対策としてSSL証明書、WAF、定期的な脆弱性診断を必須実装して使用する全ての画像、動画、文章について権利関係を明確化することが重要です。
まとめ





外国人採用を成功させるには、言語や文化の壁を越え、求職者に自社の魅力を的確に伝えることが不可欠です。
自社専用の求人サイトは、そのための有効な手段です。
成功の鍵は、ターゲットとなる人材像を明確にした上で、計画的な手順に沿ってサイトを構築すること。
多言語対応やSEO対策、応募しやすい導線設計はもちろん、在留資格に関する法務面の配慮も欠かせません。



本記事で解説したメリット・デメリットや具体的な作り方を参考に、継続的に応募が集まる採用の基盤を築きましょう。