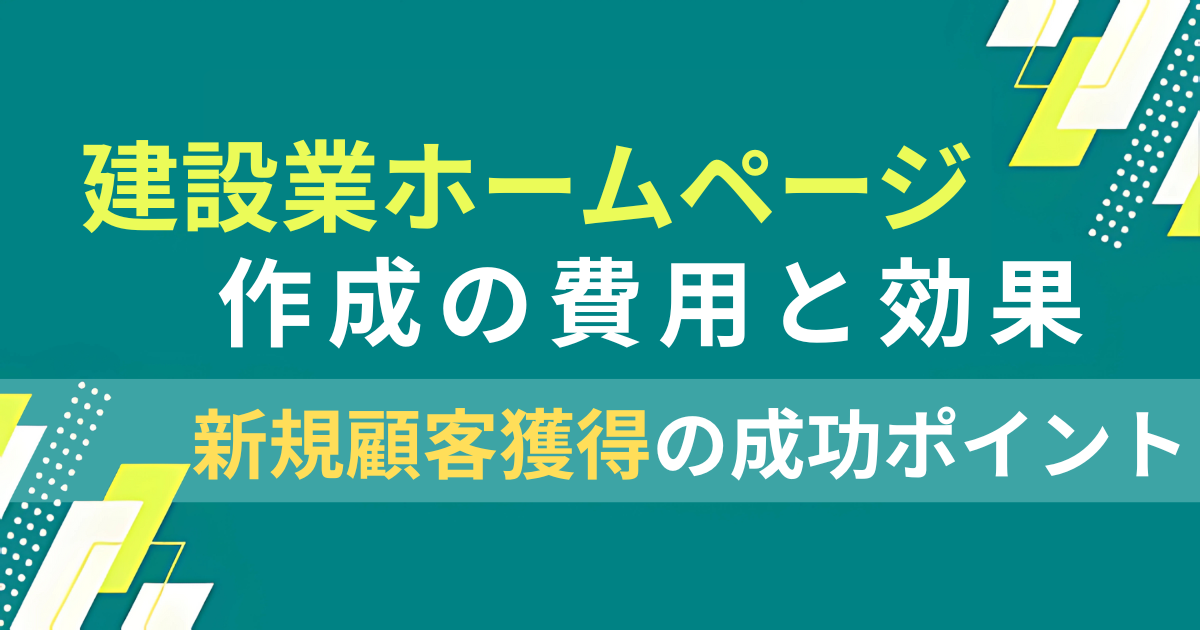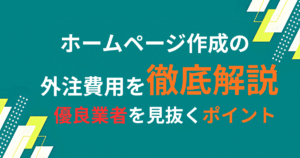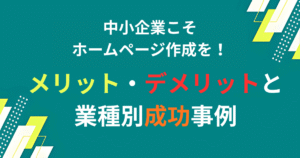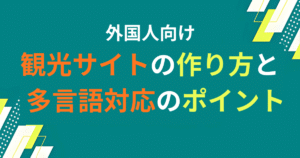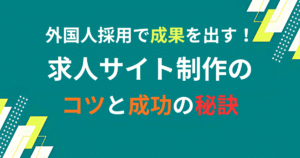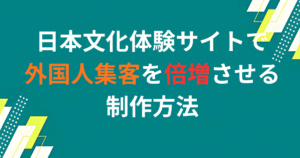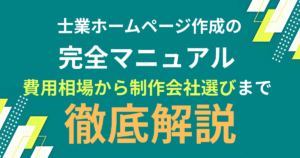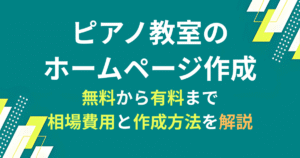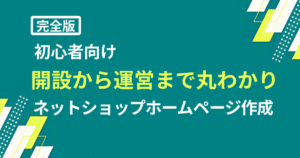建設業のホームページ作成で「どこの制作会社に頼めば失敗しないのか」と頭を悩ませている建設会社の経営者は少なくありません。

古いサイトを放置していては、地域のお客様からの工事依頼も優秀な職人の採用応募も、スマホ対応したデザイン性の高い競合他社のサイトに奪われてしまいます。
制作会社の選び方から費用相場の見極め方、実際に集客効果を上げている工務店やリフォーム会社の施工事例まで、成果の出るホームページ作成の秘訣を全て具体的に解説します。



この記事を読み終える頃には、営業強化と人材確保を同時に実現する信頼性の高いサイト作りの明確な道筋が見えてくるでしょう。
建設業のホームページ作成のメリット


この章では、建設業がホームページを作成することで得られる4つの主要なメリットについて紹介します。
2025年には約90万人の人材不足が予測される建設業界において、現在9割を超える建設業がホームページを運用しており、自社ホームページがないことで不信感を抱かれるリスクが高まっています。



以下の4つのメリットを理解することで、ホームページが単なる情報提供ツールではなく、経営課題解決の戦略的投資であることがわかります。
- 営業効率向上と新規顧客獲得による売上拡大
- 企業の信頼性・安全性の可視化による競合差別化
- 深刻な人材不足解決のための採用力強化
- 協力会社・パートナー開拓による事業基盤強化
メリット(1)営業効率が上がって新規顧客獲得に役立つ
ホームページは24時間働く営業マンとして機能し、営業コストを削減しながら新規顧客の獲得チャンスを大幅に拡大します。



インターネットやスマートフォンの普及により、建設業界でも顧客が施工会社を選ぶ際や、元請けが協力会社を探す際にホームページを比較して情報収集することが当たり前になっています。
現在の建設市場は2023年度で工事費予定額ベースが24兆2,989億円と前年度比104.8%の拡大傾向にあり需要は豊富ですが、従来の人伝てだけでは機会損失が発生しています。
SEO対策により地域名と建設業のキーワードで上位表示されることで地域の見込み顧客に効率的にアプローチでき、施工事例をBefore/After写真で掲載することで技術力を視覚的にアピールできます。
メリット(2)企業の信頼性・安全性の可視化ができる
ホームページは企業の透明性と実績を証明する信頼の窓口として機能し、高額取引が多い建設業において顧客の意思決定を後押しします。



建設業における取引は非常に高額であり、顧客は発注の際に企業の信頼性を最も重要視するため、建設業許可番号や各種資格・認定の明記による法的信頼性の確保が不可欠です。
また、代表者の顔写真と経営理念による人としての信頼構築、過去の施工実績と顧客の声による技術力の証明、安全管理体制や環境への取り組み紹介による社会的責任の表明が重要となります。
ホームページを持つことで企業の専門知識や実績、提供するサービスに関する詳細な情報を提供でき、それが社会的な信用を示すことに直結します。
メリット(3)優秀な人材の採用力強化につながる
深刻な人材不足が続く建設業界において、ホームページは優秀な人材を惹きつけ、ミスマッチのない採用を実現する最重要ツールです。



建設業界では2025年に約90万人の労働人口が不足すると予測され、建設業の有効求人倍率が6倍を超えるなど他業界を大幅に上回る厳しい状況にあります。
求職者の8割以上が求人媒体で気になった会社のホームページを確認する傾向があるため、ホームページの情報が採用の成否を左右します。
採用が成功した企業では求人広告と企業ホームページの活用割合が高く、先輩社員のインタビューや現場動画による働く姿の可視化、福利厚生や教育体制の詳細説明、3K(きつい、危険、汚い)イメージの払拭と働き方改革への取り組み紹介が効果的です。
メリット(4)協力会社・パートナー開拓につながる
ホームページは自社の専門性と信頼性を業界内にアピールし、質の高い協力会社・パートナーとの関係構築を促進するビジネスネットワーク拡大ツールとして機能します。
建設業は元請け・下請けの重層構造で成り立っており、信頼できる協力会社との関係が事業成功の鍵となります。
従来は関係のある取引先や紹介での受注がメインだった会社も、これからはWeb経由での受注を意識する必要があります。
専門工事分野や得意領域の明確化、ISO認証や安全管理体制の表示、デジタル対応状況のアピールにより差別化を図れます。
建設業のホームページ作成のデメリット


この章では、建設業がホームページを作成する際に直面する可能性のある4つの主要なデメリットについて紹介します。



メリットの多いホームページ作成ですが、制作費用は依頼する相手によって異なり、個人や中小企業のWebサイトであれば、適切な制作会社を選定する必要があります。
また、ホームページは制作費(初期費用)と運用費をセットで考えるのが重要で、長期的な視点での検討が不可欠です。



以下のデメリットを理解することで、リスクを最小限に抑えながら成功するホームページ制作が可能になります。
- 初期費用・運用コストの継続的な負担
- 定期的な更新作業に伴う手間と専門知識の必要性
- セキュリティ対策などの技術的リスクと管理負担
- SEO対策の継続的な実施と専門性の要求
デメリット(1)初期費用・運用コストの負担が必要
建設業のホームページ制作には初期費用として20万円から100万円程度が必要で、さらに月額5,000円から2万円の継続的な運用コストが発生します。
特に中小企業では予算オーバーや不明朗な料金体系に悩むケースが多く、想定外の追加費用や納品後の月額費用で後悔する企業が6割以上に上ります。
2024年4月からは建設業にも時間外労働の上限規制が適用され、コスト構造の見直しが急務となっている中で、新たな固定費の負担は慎重な検討が必要です。
制作費用はシンプルなサイトで30万円、機能充実で100万円を超え、セキュリティ性や障害時対応を重視する場合は月額5万円を超える場合もあります。
デメリット(2)更新に手間がかかる
ホームページは公開後の継続的な更新作業が必須であり、社内にWeb担当者がいない場合、更新のたびに外注費用が発生するか、作業負担が経営陣に集中してしまいます。
プログラミング言語によるホームページは専門知識がないと運用・更新が困難で、建設業では施工事例の更新が重要ですが、これまで施工実績を書いた経験がなく、何を書けば良いかわからないため後回しになりがちです。
施工事例の追加には写真撮影、文章作成、レイアウト調整で月2から3時間、お知らせ更新は月1から2回の定期更新作業が必要となります。
制作会社に更新依頼した場合は1回あたり5,000円から2万円の追加費用がかかります。
CMSを活用した自社更新可能なシステムの導入と、社内の更新担当者育成により、長期的な運用コストを抑制できます。
デメリット(3)セキュリティ対策などのリスクがある
ホームページ運用には情報漏洩やサイバー攻撃のリスクが常に存在し、適切なセキュリティ対策を怠ると企業の信頼失墜や損害賠償につながる深刻な事態を招く可能性があります。
SSL証明書の導入や定期的なバックアップ・アップデートの実施が必要で、建設業では顧客情報や工事情報など機密性の高い情報を扱うため、セキュリティ事故が発生すると取引先からの信頼を失い、受注機会の減少につながるリスクがあります。
SSL証明書の年間費用は1万円から5万円程度、定期的なシステムアップデート作業は月1から2回必要で、個人情報保護法への対応も求められます。
信頼できる制作会社との長期契約により、セキュリティ対策を含む包括的な管理サービスを利用することで、専門知識がなくても安全な運用が可能になります。
デメリット(4)ホームページ制作後のSEO対策も必要
ホームページは制作しただけでは検索結果に表示されず、継続的なSEO対策が必要であり、専門知識のない状態で運用すると集客効果を得られないまま費用だけがかかり続けるリスクがあります。
より多くのターゲットを自社ホームページに誘導するためには、ホームページ制作前にどのようなキーワードで流入してほしいか考え、適切に配置することが重要です。
検索エンジンのアルゴリズムは頻繁に変更され、競合他社もSEO対策を強化しているため、一度の設定で永続的な効果は期待できません。
キーワード調査と設定は月1回の見直し作業、コンテンツの定期更新は月2から4回、SEO専門会社への外注費用は月額3万円から10万円程度が必要です。
自社での基本的なSEO知識習得と、専門会社による定期的なコンサルティングを組み合わせることで、費用対効果を高めながら検索順位向上を図ることができます。
建設業ホームページ作成はどう進める?方法と選択肢


この章では、建設業がホームページを作成する際の4つの主要な方法と選択肢について紹介します。
2025年現在、建設業のホームページ制作はプログラミング言語による制作・CMSを使った制作・ホームページ制作会社に依頼する制作の3つの方法がありますが、マーケティング専門会社への依頼も含めると4つの選択肢が存在します。



それぞれの方法には異なるメリット・デメリット、費用相場、適用場面があり、自社のニーズと予算に最適な選択をすることが成功の鍵となります。
- 専門制作会社への依頼による安心感と品質確保
- 自社内製による低コストとカスタマイズ性の確保
- フリーランス依頼による柔軟性とコストバランス
- マーケティングのプロによる成果重視のアプローチ
方法(1)専門制作会社に依頼
建設業に特化した専門制作会社への依頼は、業界知識と制作ノウハウを活用して確実に成果を出したい企業に最適な選択肢です。
特に建設業に特化しており、お客様の7割が建設業界からの依頼という制作会社が増加しており、建設業を始め1,000社以上のホームページ制作の実績を持つ会社も存在します。
価格帯は初期制作費無料、年間38,000円のシステム使用料のみから高品質な100万円超まで幅広く対応可能です。
サポート内容には動画制作、キャラクター制作、リブランディング、SEO対策、Googleマップ対策、補助金申請サポートなどが含まれ、建設業界のホームページ向けにカレンダー機能などの専門機能も搭載されています。
建設業の業界慣習を理解し、施工事例の効果的な見せ方、採用ページの構築、SEO対策まで包括的にサポートできる専門制作会社を選ぶことで、投資効果を最大化できます。
方法(2)自社で内製する
CMSを活用した自社内製は初期コストを最小限に抑えられる一方で、プログラミング言語によるホームページは専門知識がないと運用・更新が困難というデメリットがあります。
2024年4月から建設業にも働き方改革関連法が適用され、限られた時間の中で効率的な作業が求められる状況下で、Web制作スキルの習得は現実的でない場合が多くなっています。
しかし簡単に運用や更新を行いたい場合は、CMSによるホームページ制作がおすすめで、誰でも簡単に操作しやすいのがメリットです。
WordPress活用でテンプレート利用なら月額5,000円程度から開始可能で、Wix、Jimdoなどの簡易CMSなら月額1,000円から3,000円程度で運用できます。
自社更新のメリットには外注費用削減、タイムリーな情報更新、自由度の高いカスタマイズがありますが、技術習得に月10から20時間の学習時間、デザイン品質の限界、SEO対策の専門性不足というデメリットも存在します。
方法(3)フリーランスに依頼
フリーランスへの依頼は制作費用を30から50%程度削減できる可能性がある一方で、品質や対応の安定性にリスクがあり、建設業の業界知識を持つ人材の選定が成功の鍵となります。
フリーランス市場の拡大により、建設業経験者やマーケティング知識を持つ制作者も増加していますが、実績・デザイン・料金・評判等をもとに厳選する必要性は制作会社以上に重要です。
特に建設業では施工事例の魅力的な見せ方や採用ページの効果的な構成など、業界特有のノウハウが求められるため、経験の有無が成果に直結します。
費用相場は制作会社の50から70%程度で20万円から60万円程度が一般的です。
選定基準には建設業界での制作実績、継続的な連絡可能性、アフターサポート体制の確認が必要で、途中での連絡不通、品質のばらつき、保守サポートの限界といったリスク要因も考慮する必要があります。
方法(4)マーケティングのプロに依頼する
マーケティング専門会社への依頼は制作費用が最も高額になる一方で、ホームページ制作後の集客まで一社完結でサポートし、採用や受注に直結する成果を重視する企業に最適なアプローチです。
建設業界の2025年問題による人材不足の深刻化と、デジタルマーケティングの重要性の高まりにより、SEO対策が施されたホームページを制作することで、自社が受注したい工種や地域でのキーワードで検索した時に上位を獲得することができるようになります。
サービス範囲にはSEO対策に加え、リスティング広告やSNS広告、認知度を増やす動画広告など幅広いノウハウが含まれ、予算5万円で48件ものお問い合わせがあった成果事例も報告されています。
費用相場は月額10万円から50万円程度の継続契約が一般的で、ホームページ制作、SEO対策、Web広告運用、アクセス解析、コンテンツマーケティングなど対応領域は多岐にわたります。



本気で営業・採用強化を図りたい企業、年商1億円以上でマーケティング投資により事業拡大を狙う企業には最適な選択肢となります。
建設業ホームページ作成の費用相場は?


この章では、建設業のホームページ制作にかかる費用相場について、最新の2025年データを基に詳しく解説します。
建設業ホームページ作成には主に以下の内容があります。
- 制作会社への外注費用(30万円〜200万円以上の幅広いレンジ)
- 格安制作サービスの利用料金(初期費用無料〜月額数千円の継続課金)
- サーバー・ドメイン等のインフラ維持費(月額1,000円程度)
- 国の補助金制度を活用した実質負担軽減の方法
相場(1)制作会社に依頼すると相場は100万円
建設業のホームページを制作会社に依頼する場合、中小企業向けサイトの費用相場は30万円から100万円が一般的で、機能や規模によっては100万円を超えるケースが多くなっています。
制作費用の変動要因として、デザインがテンプレート利用かオリジナルデザインか、ページ数の多さ、お問い合わせフォームやブログ機能などの追加機能、ライティングや写真撮影の対応範囲が挙げられます。
建設業界では施工事例や技術力のアピールが重要なため、プロの写真撮影や動画制作を含めると費用が高額になる傾向があります。
低価格帯では30万円以下で1から3ページのテンプレートデザインが可能ですが、高価格帯では100万円以上で15から20ページのオーダーメイド制作となります。
相場(2)格安制作サービスは更新料金に要注意
格安ホームページ制作サービスは初期費用無料から月額2,980円程度で利用できますが、更新料金やドメイン所有権、SEO対策の不備など隠れたリスクがあるため注意が必要です。
格安サービスの多くは、SEO対策が不十分で集客力が低い、テンプレートによる制限が多くカスタマイズができない、サーバーやドメインの所有権が制作会社にあるため他社への移管が困難という問題があります。
具体的には、初期費用無料で月額2,980円のサービスを3年間利用すると約11万円、年間38,000円のシステム使用料なら5年間で19万円となり、長期的には高額になる可能性があります。
契約期間中の解約が困難で、他社への移管時に同じドメインが使用できないケースも多いため、契約条件の詳細確認が重要です。
相場(3)サーバー費用は月1000円で十分
建設業のホームページ運用に必要なサーバー費用は月額1,000円程度、ドメイン費用は年額1,000円から3,000円程度で十分対応可能です。



建設業のホームページは一般的に大量のアクセスを処理する必要がなく、基本的な企業サイト機能があれば十分なため、高額なサーバープランは不要となります。
基本サーバーが月額500円から1,500円、ドメインが年額1,000円から3,000円、SSL証明書が無料から年額数万円程度で、合計月額1,000円前後で運用が可能です。
SSL証明書も無料のものから年額数万円のものまであり、企業の信頼性を重視するなら有料版を選択することで、月額1,000円程度の追加で十分なセキュリティを確保できます。
サーバー選びでは価格だけでなく、サポート体制、バックアップ機能、SSL対応を重視することが大切です。
相場(4)補助金・助成金の活用
2025年度は「IT導入補助金」「小規模事業者持続化補助金」「ものづくり補助金」の3つの国の補助金でホームページ制作費用の一部補助が可能で、最大で制作費用の2/3から4/5が支援対象となります。
IT導入補助金は最大450万円、小規模事業者持続化補助金は最大250万円、ものづくり補助金は最大4,000万円から1億円の支援が受けられます。
ただし、これらの補助金は業務効率化や販路拡大が目的のため、単なる会社紹介サイトではなく、集客や業務改善につながる機能が必要です。
具体的には、IT導入補助金でCRM機能付きホームページで最大350万円補助、小規模事業者持続化補助金でウェブサイト関連費として最大50万円補助が可能です。
補助金申請には詳細な事業計画書の作成が必要で、採択率は約37から40%程度のため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
建設業ホームページ作成を成功させるポイント


この章では、建設業のホームページを成功させるために欠かせない重要なポイントについて紹介します。
建設業ホームページ作成を成功させるポイントには主に以下の内容があります。
- ターゲット顧客に的確にリーチするキーワード設計戦略
- 建設業特有の許認可・資格・安全管理体制による信頼性構築
- 視覚的で説得力のある施工実績の効果的な見せ方
- 現代必須のスマホ対応とSEO対策の実装
- 成果に直結する問い合わせ導線の最適化手法
ポイント(1)キーワード設計で狙いの顧客を集客する
建設業のホームページでは、地域名と工事種別を組み合わせたローカルSEO対策が集客成功の鍵となります。
建設業は地域密着型のビジネスが多く、顧客は「地域名+建設」「地域名+リフォーム」といった検索パターンで業者を探すため、地域に特化したキーワード戦略が最も効果的です。
また、潜在顧客は「リフォーム 相場」「塗料 種類」などの疑問解決型キーワードでも検索するため、これらに対応するコンテンツが重要になります。
効果的なキーワード例として「○○市 建設業」「○○区 リフォーム」「○○県 外壁塗装」などがあり、コンテンツSEOとして「リフォーム工期の目安」「外壁塗装の最適な時期」などの専門記事を作成することで、潜在顧客の疑問に答えながら信頼獲得と集客を同時に実現できます。
ポイント(2)許認可・保険・資格・安全品質の明記で信頼を高める
建設業許可番号、各種資格、保険加入状況、安全管理体制の明記は、高額取引となる建設業において顧客の信頼を獲得する最重要要素です。
建設業では数十万円から数千万円の高額な取引が一般的で、顧客は工事を依頼する前に業者の信頼性を最も重視します。



明記すべき項目として、建設業許可番号(国土交通大臣許可・都道府県知事許可)、一級建築士・二級建築士の在籍状況、施工管理技士の資格者数、賠償責任保険・工事保険の加入証明、ISO認証や安全管理の取り組み、過去の事故率や安全表彰歴などがあります。
これらを会社概要ページや専用の「安心・安全への取り組み」ページで詳細に掲載し、なぜその資格が必要なのか、どのような安心につながるのかを顧客目線で説明することが効果的です。
ポイント(3)写真・工程・数値・ビフォーアフターの提示で施工実績を示す
Before/After写真と具体的な数値データ、工程の可視化を組み合わせた施工実績の提示は、建設業ホームページにおける最強の営業ツールとなります。
建設業の成果は視覚的なインパクトが非常に重要で、文字だけでは伝わりにくい技術力や仕上がりの質を、写真と数値で具体的に示すことで顧客の理解と安心感が大幅に向上します。
効果的な実績紹介方法として、施工前後の同じアングルでの比較写真、工事期間・費用・使用材料の明記、工程ごとの写真付き進捗レポート、お客様の具体的な感想コメント、担当者からの工夫ポイント解説があります。
ポイント(4)スマホ最適化とSEO対策
現代では多くのユーザーがスマートフォンでホームページを閲覧するため、モバイルファースト設計とSEO対策の両立が集客成功の必須条件です。
特にBtoC分野のウェブサイトではスマホからのアクセスが多数派となっており、Googleもモバイルフレンドリーなサイトを検索順位で優遇するため、スマホ対応は検索エンジン対策としても必須要素となっています。
必須対応項目として、レスポンシブデザインによる画面サイズ自動調整、タッチ操作に配慮したボタンサイズとメニュー設計、高速読み込みのための画像最適化、スマホ専用の電話発信ボタン設置、フォーム入力の簡素化があります。
SEO面では、ページ表示速度の向上、適切なメタタグ設定、内部リンク構造の最適化、構造化データの実装などが重要で、Google Analyticsなどの解析ツールを導入した継続的な改善が成果向上につながります。
ポイント(5)問い合わせ導線の最適化
ホームページの最終目標である問い合わせ獲得を最大化するには、どのページからでも簡単にアクセスできる問い合わせ導線の設計が不可欠です。
せっかく興味を持ったユーザーでも、問い合わせ方法が分かりにくかったり、入力フォームが複雑だったりすると離脱してしまいます。
建設業では見積もり相談から受注までの検討期間が長いため、初回の問い合わせハードルを下げ、段階的に関係を深めていく導線設計が重要になります。
効果的な導線設計として、全ページ共通のヘッダー・フッターに電話番号と問い合わせボタンを設置、スマホ画面での固定電話ボタン表示、簡単な資料請求フォームから詳細見積もりへの段階的導線、施工事例ページに「類似工事の相談はこちら」といった自然な問い合わせボタン配置などがあります。



問い合わせフォームは「まずは相談だけでも」「概算見積もり依頼」など、ハードルの低い表現を使うことが効果的です。
建設業ホームページ作成でよくある失敗は?


この章では、建設業のホームページ作成で多くの企業が陥りがちな失敗パターンについて紹介します。
建設業ホームページ作成でよくある失敗には主に以下の内容があります。
- 目的やKPI設定が曖昧で成果を測定できない根本的な設計ミス
- 見た目を重視しすぎてユーザビリティや導線設計を軽視する設計上の問題
- スマートフォン対応や表示速度の不備によるユーザー離脱の増加
- 公開後の更新・保守体制が未整備で情報が陳腐化してしまう運用上の課題
失敗(1)目的・KPIが曖昧で効果測定不能
建設業のホームページ制作で最も多い失敗は、「ホームページを作ること」自体が目的になってしまい、本来達成すべき営業・採用・信頼性向上などの具体的な目標設定が曖昧になることです。
多くの建設会社が「競合他社もホームページを持っているから」という漠然とした理由で制作を始めるため、完成後に「問い合わせが増えない」「採用効果が分からない」「投資対効果が見えない」という状況に陥ります。
目的が不明確だと制作会社への要求も曖昧になり、結果として「なんとなくきれいなサイト」しかできません。
制作開始前に「なぜホームページが必要なのか」「何を達成したいのか」を明文化し、「問い合わせ件数月○件増加」「採用応募数年間○名確保」など測定可能な数値目標を設定することが成功の第一歩となります。
失敗(2)デザイン重視で使いやすさ・導線・アクセシビリティを軽視
スタイリッシュなデザインにこだわりすぎて、ユーザーにとっての使いやすさや問い合わせへの導線設計、アクセシビリティを軽視することは、見た目は良いが成果の出ないホームページになる典型的な失敗パターンです。
建設業界では「かっこいいサイト」への憧れが強く、デザイン性を最優先に考えがちですが、ユーザーは情報を探しやすく問い合わせしやすいサイトを求めています。
特に建設業の顧客層は中高年が多く、複雑なナビゲーションや小さな文字、分かりにくい問い合わせボタンは大きな障害となります。
失敗(3)スマートフォン対応や表示速度の不備で離脱増
現代ではスマートフォンからのアクセスが主流となっているにも関わらず、モバイル対応や表示速度対策を軽視することで多くの潜在顧客を逃してしまう失敗が頻発しています。
建設業のホームページでもスマートフォンからのアクセスが60%以上を占めるケースが多く、Googleもモバイルフレンドリーなサイトを検索順位で優遇するため、スマホ対応は必須となっています。
PC版は見栄えが良いがスマホで見ると文字が小さすぎて読めない、ボタンが押しにくい、画像が重くて表示に10秒以上かかるといった問題により、スマホユーザーの90%が即座に離脱するケースもあります。
制作時は必ずスマートフォンでの表示・操作性を最優先に考え、表示速度は2秒以内を目標に最適化を行うことが重要です。
失敗(4)更新・保守体制が未整備で情報が陳腐化
ホームページを「作って終わり」と考え、公開後の更新・保守体制を整備していないことで情報が古くなり信頼性を失う失敗が非常に多く見られます。
建設業では施工実績や現在進行中のプロジェクト、新しい技術やサービスなど、継続的に更新すべき情報が多数あります。
しかし更新作業を制作会社に毎回依頼するとコストがかかるため放置されがちで、「お知らせが2年前で止まっている」「掲載されている施工事例が古すぎる」といった状況が生まれ、「この会社は本当に営業しているのか?」という不信感を招きます。
制作会社に80万円で立派なサイトを作ってもらったものの、更新料金が1回3万円と高額なため更新を控えた結果、3年間新しい情報が一切追加されず顧客から信頼を失うケースも多発しています。
まとめ


本記事では、建設業のホームページ作成におけるメリットや費用相場、成功のポイントを解説しました。
ホームページは、新規顧客や優秀な人材を獲得するための強力な営業ツールです。



制作費用は100万円前後が目安となりますが、これは会社の未来への投資です。
目先の安さだけで制作会社を選んでしまうと、成果が出ないばかりか、企業の信頼を損なうリスクもあります。
まずは自社が抱える課題を解決するために、ホームページで何を達成したいのか目的を明確にしましょう。



その上で信頼できるパートナーを選び、補助金なども賢く活用しながら、事業成長につながる一歩を踏み出してください。